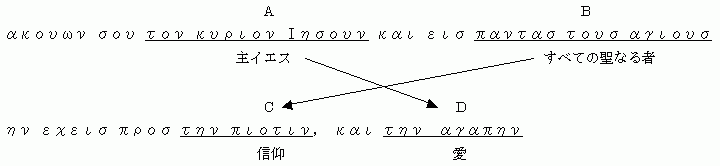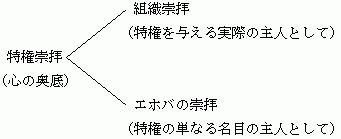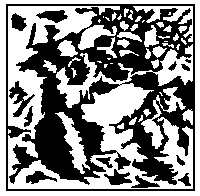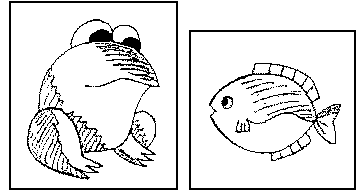6章 ものみの塔協会の体質と新世界訳聖書
(1)組織中心の体質
現在のものみの塔協会の体質の中で最も顕著なものは、何といっても、組織
賛歌、組織主義、組織支配、組織崇拝、組織バアルである。まさに組織の氾
濫、組織一色といえるような状態であるが、最初からこういう体質だったとい
うわけではない。
ものみの塔協会の初代会長であったC・T・ラッセルは、むしろ組織化の動き
を警戒していたと言われている。当初は「組織」ということばを使うこと自体
抵抗があって、クリスチャン会衆を組織とはみなしていなかったようである。
認められていたのはエホバやみ使いたちからなる天的組織だけであった。1985
年3月15日号のものみの塔誌はその当時の状況について、次のように述べてい
る。
「そのような集め出された者たちから成る、目に見える組織を形成すること
が、神のご計画の精神と調和しないことは明らかである。そして、そのように
組織を形成するとしたら、教会の側に、組織とか連盟とかいう今流行の概念に
迎合する気持ちがあることを示すことになるように思われる。(イザヤ8:12)
今の業は、組織することではなく、ユダヤ人の本来の収穫の場合と同じよう
に、分けることなのである。(マタイ10:34〜36)」
(この部分は1894年12月1日号からの引用)
神の会衆を組織化することは世の精神に迎合することであり、神の意志に反
するとまで明言されている。現在の組織化の巨大な潮流を考えると、とても信
じられないような話であるが、かつてはそういう時代もあったということであ
ろう。
しかし、やがて変化の時が訪れる。ラッセルの死後間もなく、神の組織とい
う考え方が登場する。そのいきさつについて、同じ1985年3月15日号のものみ
の塔誌は次のように述べている。
「神の組織」この表現は今から60年余り前、べテルの食卓で日々の聖句の討
議を行っていた時に、ものみの塔協会の編集委員の一人によって用いられまし
た。この言葉は、ニューヨークのブルックリンにある本部の家族に深い感銘を
与えました。「神の組織」というその独特な言葉は、これらの聖書研究者たち
のその後の考え、話、執筆活動を導くものとなりました。(p.10)
「ものみの塔」誌の1922年12月1日号は、「サタンの目的」という副見出し
に続いて、明確にこう述べました。「我々は今、邪悪な日に生きている。戦い
はサタンの組織と神の組織との間で行なわれている。」〈p.17)
「この世には神の組織とサタンの組織しかない。神の組織はものみの塔協会
だけ、あとはみなサタンの組織」という現在の極めて一義的な教義の概念は、
1920年代の初期に導入されたものであることがわかる。組織としては、大きな
方向転換をしたわけであるが、しかし、これは宗教組織の成長から言えばごく
自然なことであろう。
C・T・ラッセルの頃は彼個人に対する組織の依存率が極めて高く、いわゆる
カリスマ的なモードともいえるような形態であった。彼は支配的な投票権を持
ち、協会内の様々な役員を任命したと言われている。当時まだエホバの証人と
いう名称はなく、外部の人々からはラッセル派とかラッセル信奉者と呼ばれて
いた時代のことである。
通常組織がそういう状態のままであれば、指導者の死とともに組織自体も解
体してしまう危険性がある。ものみの塔協会もラッセル死去のとき、そのよう
な危機を経験した。ある人々は「これでもう終りだ」とまで考えたらしい。協
会の会長のポストを巡る後継者争いが起き、理事会も分裂してしまった。本部
ではデモ行進まで行なわれ、ものみの塔協会は分裂の危機に直面した。おそら
く「神の組織」という概念が導入されることになった背景には、このような事
情があったものと考えられる。
一代目の影響が大きければ大きいほど、二代目はその影に悩まされるもので
あるが、この非常に難しい時期を乗り越えて、ものみの塔協会を発展させたの
が二代目の会長、J・F・ラザフォードであった。彼は個人依存型の体制を廃
し、組織主体のモードを確立することに成功した。「神の組織」という概念の
レールが敷かれ、進むべき道とその方向が提示されたのが1920・1930年代であ
ったといえる。
そのレールの上をものすごい勢いで走り始めたのが、1924年から三代目の会
長に就任した、N・H・ノアである。「合理的な管理者、組織者」と言われた彼
は、その才能を十分に発揮し、次々と新しい取り決めを設ける。現在のものみ
の塔協会の組織体制のほとんどは、彼が作り上げたものである。組織の拡大に
対するその貢献には計り知れないものがある。マタイ24章14節の「王国のこの
良いたよりは、あらゆる国民に対する証しのために、人の住む全地で述べ伝え
られるでしょう」という預言は、彼の組織化なくしては成就しなかったのでは
ないかと思う。
第二次世界大戦後、組織は記録的な増加を達成して行く。わずか10万足らず
から300万をはるかに越える人数への拡大である。この数字は会員数ではなく
伝道者数なので、もし一般の宗教団体のように会員数でしかも多少水増しして
数えたら、たぶん現在では全世界で1000万を越えることになるのではないかと
思う。
現在の会長F・W・フランズは1984年10月6日の年次総会で「65年ほど前にJ・
F・ラザフォードと共に、『神の組織』という言葉を初めて聞いた時ほど興奮
を覚えたことはかつてなかった」と述べている。神の組織の概念なくしてもの
みの塔協会は成り立たないということであろう。
組織の拡大はものみの塔協会の最大のよりどころになっている。拡大はエホ
バの祝福のしるし、拡大が続く限りは神の是認を得ているという論理である。
もっとも拡大が止まったら止まったで、それはサタンのせいだということにな
ってしまうとは思うが。
組織は確かに必要なもの、また有用なものである。組織がなければ世界的な
業は何一つ行なうことができない。組織が信仰の支えになっているような人も
大勢いる。しかし、いかに組織が重要なもの、大切なものであるとはいって
も、限度を越えた暴走は問題になる。神の組織と銘打ったからといって、神の
領域まで犯してよいということにはならないし、第一これは増加や拡大で正当
化できるような性質のものではない。
ただ、そういう体制を敷かなければ世界的な拡大を達成することはできなか
ったであろうから、必要悪みたいな面もあるとは思うが、いつまでもそのまま
では成員も困るし、疲労もたまる。もうそろそろ終りにすべき時であろう。組
織の大合唱や暴走などはもってのほかである。いずれにしても、「神の組織」
という概念に明確なワク組みを設定しなかったことが、組織の暴走を許してし
また最大の原因であろうと思う。
福音の理想主義に勝利を収めた組織主義が台頭してきた時期に、新世界訳聖
書の翻訳もまた始まっている。組織が教義を作り、教義が翻訳を作る(この逆
も成り立つ)といった具合に、組織、教義、翻訳は密接な相関関係にあるが、
ものみの塔協会の組織主義的な体質は新世界訳にも反映されている。
《新世界訳は統治体に信仰を置くことを勧める》
問題となる聖句は、出エジプト記14章31節、19章9節、フィレモン5節であ
る。
「民はエホバに対して恐れを抱き、エホバとその僕モーセに信仰を置くように
なった」(出エジプト14:31)
「するとエホバはモーセにこう言われた。『見よ、わたしは暗い雲のうちにあ
ってあなたに臨む。わたしがあなたと話す時に民が聞くため、そして彼らがあ
なたに対しても定めのない時まで信仰を置くためである』。」(出エジプト
19:9)
「わたしは、祈りのなかであなたのことを述べるさい常にわたしの神に感謝し
ています。
あなたが主イエスとすべての聖なる者たちに対して抱く愛と信仰についてつ
ねに聞いているからです」(フィレモン4、5)
このように訳すと、非常に重要な教義上の問題が生じてくる。つまり、信仰
の点で、神と人間が同レベルになってもよいのか、人間が人間に信仰を持つこ
とは正しいのかという問題である。
どうやら新世界訳委員会は、人間に信仰を持っても良いと判断したようで、
エホバとモーセが同列に扱われているし、エホバ自らモーセに信仰を置くよう
イスラエルの民に勧めている。フィレモンの手紙の方は、パウロを含む聖なる
者全員にフィレモンが信仰を持っており、パウロ自身もそれを誉めているとい
うことになっている。
それでは他の聖書もみなこのように訳しているのかというと、決してそうで
はない。例えば共同訳は、
「主イエススに対するあなたの信仰と、聖なる人一同に対
するあなたの愛とについて聞いているからです」
というふうに「信仰」と「愛」を分けて訳している。新改訳、現代訳の翻訳も
これと同様である。新世界訳と同じように訳している聖書には、口語訳、詳訳
聖書などがある。出エジプト記の方はほとんどの聖書が「モーセを信じたとか
信頼した」という表現になっており、新世界訳のように「信仰、faith」を用
いている聖書は、私たちの調べた範囲では他になかった。
訳者によっては見解が分かれているようなので、まず新世界訳翻訳委員会に
「信仰」を選んだ理由を尋ねてみた。しかし残念ながら返事はなかった。
それで今度は、異なった翻訳をしている共同訳委員会に、どのような根拠に
基づいてフィレモンの手紙の方を「主イエスに対するあなたの信仰と、聖なる
人一同に対するあなたの愛」というふうに分けて訳したのかを質問してみた。
すると次のような親切な返事が送られてきた。
「ご質問の箇所についてお答えしましょう。この箇所はテキスト上ではあま
り問題はありません。つまり写本によってギリシャ語が違っているわけではな
く、どの写本も、前置詞に若干の違いがある程度で、ほとんど同じギリシャ語
です。
ではなぜこのような訳文の違いが出てきたのかということになりますが、そ
れはこの箇所のギリシャ語の構造によります。
以下はそのギリシャ語とポイントになる言葉の日本語です。
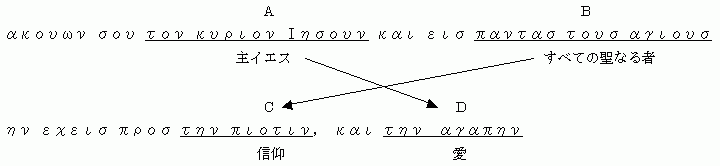
このような形になっていて、このまま訳せば、文語訳などのように『主イエ
スとすべての聖なる者たちに対して抱く、愛と信仰』ということになります。
しかし、この形は『キアスモス』というギリシャ語の特殊な表現方法であると
考えるのが普通で、口語訳や共同訳の訳し方『主イエスに対する信仰』『すべ
ての聖なるものに対する愛』は、この考え方によったものです。
『キアスモス』(ギリシャ語のXに由来する言葉です)とは、ABCDと語や句
があったときに、AはDにかかり、BはCにかかるという形の表現で、ギリシャ語
やヘブライ語などによく使われる方法です。
ですから、どちらの考え方も間違いとは言い切れません。しかし、前後の文
脈、聖書全体の教えるところ(コロサイ1章4節)などから考えて、共同訳聖書
や口語訳聖書では『主イエスに対する信仰』『すべての聖なるものに対する
愛』と分けて訳してあります」
この説明から明らかなように、文法上の絶対的な見解というものはない。結
局は解釈の問題といえる。したがって、どちらの翻訳を選ぶかは、人間に対し
て信仰を持つことが聖書の教えにかなっているのか、それともそうではないの
かという教義上の判断によることになる。
共同訳委員会も述べているように、聖書全体の教えや精神を考慮すると、ど
うしても聖書が人間に信仰を持つように勧めているとは考えにくい。証拠は圧
倒的に新世界訳に不利である。
例えば、コリント人への第二の手紙5章7節は、
「わたしたちは信仰によって歩んでいるのであり、見えるところによって
〔歩んでいるの〕ではありません」
と述べて、クリスチャンの真の信仰は、見える者に依存しているのではないと
いうことを教えている。このように諭したパウロが、フィレモンには自らその
逆のことを書き送るとは、まず考えられない。
さらに、詩編146編3節は
「高貴な者にも、地の人の子にも
信頼を置いてはならない。彼らに救いはない」
と明確に記しているし、加えてモーセが約束の地に入れなかった理由を述べて
いる次のエホバの言葉
「後にエホバはモーセとアロンにこう言われた。『あなた方がわたしに信仰を
示さず、イスラエルの子らの目の前でわたしを神聖なものとすることを怠った
ゆえ、それゆえに、わたしが必ず彼らに与えるその土地に、あなた方がこの会
衆を携え入れることはないであろう』」(民数記20:12)
とも合わない。要するに、文法的にも聖書的にも「モーセに信を置く、聖徒に
信仰を置く」と訳さねばならぬ必然性はまったくないのである。そうである以
上、新世界訳の訳文はものみの塔協会の純粋な解釈または方針ということにな
ろう。
これは組織支配、組織崇拝には非常に都合の良い翻訳である。なぜなら日本
語の「信仰」の感覚では
「神・仏などを固く信じ、その教えを守り、それに従う・こと(心)。ま
た、ある物事を絶対視して、信じる・こと(心)」(学研国語大辞典)
ということになってしまうからである。(英語の「faith」も辞書を見る限り
ではあまり大差はない。)
ここで注目すべきは「信仰」のレベルになると、「絶対視」する傾向が出て
くるということである。ものみの塔協会の場合、「現代の聖なる者」すなわち
「残りの者」、その代表が「統治体」という教義になっているので、これは
「統治体絶対紙組織盲従」の体質を生み出す翻訳であるといえる。
新世界訳委員会、ものみの塔協会、統治体は確かに意識して「信仰」という
訳語を選んでいる。というのは、ものみの塔誌には次のように書かれているか
らである。
「エホバへの信仰、エホバが代弁者として用いておられる人々に対する信
仰、そうですエホバの組織に対する信仰です!わたしたちが今日エホバへの
奉仕に『出て行く』とき、そのような信仰を働かせるのは本当に重要なことで
す。これこそ確かな成功への道であり、エホバとその取り決めに信仰を働かせ
る、献身してバプテスマを受けた証人たち全員がそうした成功を収めるべきで
す」(ものみの塔19847/1、p.15、15節)
組織の代表者に対する信仰、組織そのものに対する信仰を持つべきであると
断言している。
「今年の大会は、三日間全日の大会になります。…プログラムのどの面も、
それが提供される目的は,エホバが現在用いておられる目に見える組織に対す
る信頼を強めるだけでなく、エホバへの信頼を強めることにあります」
(ものみの塔19872/1、p.30)
何とすでに神よりも組織の方が優先されている。組織は当たり前、その次に
神である。
「高い塔の上の部署に就き、前かがみの姿勢を取りながら、昼間は地平線の
あたりをじっと眺め、夜は目を凝らして闇を見据える、常に警戒を怠らない見
張りの者の姿を思いに描いてください。それが、イザヤ21章8節で用いられて
いる『物見の塔』に相当するヘブライ語(ミツぺ)にこめられている主要な考
えなのです。見張りの者はしっかり目覚めているので、正常な人ならこの者が
報告を声高く告げることに疑いを差しはさまないでしょう」
(ものみの塔19873/1、p.12、12節)
見張りの者に疑いを持つ人は、正常な人ではないと述べられている。全くこ
の感性には驚くほかはない。疑われるようなことをしてはいないだろうかと謙
虚に顧みてみるという姿勢ではなく、疑う方が異常だという感覚である。本当
に正常であれば誰に疑われてもそれほど困ることはないと思うのであるが。
《組織的奉仕》
ものみの塔協会は非常に「組織」が好きである。新しく聖書を学んだ人には
「組織の話」というプログラムを組んで、聖書研究のたびごとに組織について
説明するよう取り決めている。こういう組織好きの体質は翻訳にも反映されて
くるようで、日本語版はわずか一箇所だけであるが、まったくその必要がない
にもかかわらず「組織」という言葉を聖書に登場させている。(英語版は
organised が二箇所 organising が一箇所)
その聖句は出エジプト記38章8節で次のようになっている。
「彼は銅の水盤と銅の台とを作ったが、それは会見の天幕の入り口で組織的
奉仕に携わっていた婦人たちの鏡を用いて造られた」
「Then he made the basin of copper and its stand of copper, by the
use of the mirrors of the women servants who did organised service at
the entrance of the tent of meeting」
「organized service」「組織的奉仕」が他の翻訳ではどのようになってい
るかというと、例えば新改訳では、
「彼は…また青銅でその台を作った。会見の天幕の入り口で務めをした女たち
の鏡でそれを作った」
単なる「務め」になっている。口語訳も同じで、ことさら「組織」という言
葉を入れる必要はないところである。
確かに会見の天幕の入り口で働く婦人たちは大勢いたに違いないので、彼女
たちが組織的に務めを果たしていたことは間違いのないことであろう。ただ、
組織的という言葉を付け加えなければ、それではばらばらになって働いていた
ことになるかというと、それは考え過ぎであって普通はそのような心配はいら
ない。文脈を見れば十分わかることである。「組織」という用語をわざわざ入
れたのは、やはりものみの塔協会の好みとしか言いようがない。
ここで使われているヘブライ語「ツァーヴァー」の基本的な字義は
「service」であって、新世界訳が付け加えているような「organize」「組織
する」という意味はツァーヴァーには含まれていない。字義訳を誇る新世界訳
が何故「service」だけにとどまらなかったかは、翻訳委員会に聞いてみない
と分からないが、おそらく「ツァーヴァー」の中の「army or hosts」の意味
を取ったものと考えられる。確かに軍隊は厳しく組織され統制が取られてい
る。その様子を働く婦人たちにあてはめたようだ。
(2)取り決め偏重の体質
「聖書から論じる」によると「組織」の定義は、「ある特定の仕事もしくは
目的のために各人の努力が調和的に作用するようにまとめられた人々の集合体
または社会集団。組織の成員は、管理のための種々の取り決め、また一定の基
準や要求によって結び合わされます。」(p.293)となっている。したがっ
て、組織の強化といえば通常は管理体制の強化、取り決めの強化ということに
なる。
これは別にものみの塔協会に限ったことではなく、すべての組織体にも当て
はまることである。組織中心の体質になって行けば、必ず組織の肥大化と共に
官僚化が始まり、取り決め重点主義、取り決め偏重の体質が生まれて行く。
「取り決めではどうなっていますか、ぜひ取り決めに従ってください、取り決
め通りにやりましょう」という組織の声が、全体を押し潰してゆくことにな
る。
ものみの塔協会がこういう体質を正当化するために用いている聖句は数多く
あるが、ここでは翻訳との関連からその中の一つだけを取り上げることにす
る。
《すべては取り決めに従って》
問題のその聖句とはコリント第一14章40節であるが、それに従うと、物事は
すべて「取り決め」のもとに行なわねばならないということになってしまう。
「しかし、すべてのことを適正に、また
取り決めのもとに行ないなさい」
「let all things take place decently
and by arrangement」
新世界訳の「取り決め」が他の翻訳では、
「秩序を正しく」−共同訳、「秩序を正して」−口語訳、
「秩序があり」−現代訳、「秩序をもって」−新改訳、
「in order」−アメリカ訳、欽定訳
圧倒的に「秩序」になっている。
もとのギリシャ語には両方の意味があるので、訳語としてはどちらでも良い
わけであるが、字義的には「秩序」の意味のほうが強いようである。ものみの
塔協会の「王国行間逐語訳」も「order」にしている。逐語訳の「order」を止
めて「arrangement」にしたのはなぜか。これは新世界訳翻訳委員会に聞いて
みないとわからないが、そのほうがよりものみの塔協会の方針に合っていたと
いうことであろう。「取り決め」と「秩序」たいして違いはないように思える
かもしれないが、組織上の権限を持つ者が「秩序正しくやりましょう」と言う
のと、「取り決めに従ってください」と言うのでは雲泥の差がある。組織の成
員が受けるイメージはまるで違うのである。「取り決め」と訳してあれば組織
の幹部はいつでも、「聖書のここに書かれているように、取り決めに従いまし
ょう。神が勧めておられるのは皆さんが取り決めに従うことです」と皮肉タッ
プリに言うことができるのである。
会衆の運営や集会が秩序正しく行なわれねばならないのは当然のことであ
る。パウロが指摘しているように、神は無秩序の神ではなく平和の神だからで
ある。会衆が混乱状態にあれば聖霊は喜ばず、その働きも低下する。当時コリ
ント会衆はこの面で深刻な問題を抱えていた。
しかし、問題があるからといってすぐに「取り決めに従ってください」とや
ってしまうのでは、聖霊の働く余地を大いに狭めてしまう。もしかしたら、聖
霊が心に働きかけて、自発的に問題を正すよう人々を動かすかもしれない。あ
るいは、予想も付かないような方法で問題を解決する可能性も残っている。ま
た人々に健全な精神があれば、その必要に気づかせるだけで問題はなくなるか
もしれない。始めから取り決めとやるとこうした可能性をみな奪ってしまう。
もしコリント会衆がその段階をすでに過ぎていたというのであれば、この聖句
の適用をそういう範囲に限定すべきであろう。
加えて、新世界訳の翻訳では「取り決め」を造る権限を組織が独占するのに
も、非常に都合が良いものである。
《取り決めが先》
取り決め偏重の体質が進行して行くと、次のような傾向も出てくる。つま
り、聖書の教えが先ではなく、組織の取り決めが先になるという現象である。
組織の方針が咲きに決まっていて、まず必要な取り決めを造る。そして、その
取り決めを正当化できるような聖句を、聖書の中から捜してくるというやり方
である。これは直接翻訳とは関係のない問題であるが、ものみの塔協会の体質
を示す例として一つだけ上げることにする。
エホバの証人が毎月提出しなければならないものに、奉仕報告というのがあ
る。正規開拓者以上は特別の用紙を使うが(もしかしたら現在は変わっている
かもしれない)、一般の伝道者は次のような用紙に記入して提出する。これを
会衆で集計して支部事務所に送る。

通称「組織の本」には、奉仕報告の必要性やその根拠について多くのことが
述べられているが、簡単にまとめると次のようになる。
- イエス・キリストの初期の追随者たちは、奉仕報告に関心を持っていた。
(マルコ6:30)
- 聖書には具体的に数字が報告されている箇所がたくさんある。
(Ex)ペンテコステの日に聖霊がそそぎ出された際、そこには120人ほどの人が
いた。まもなく弟子の数は3000人になり、次いで5000人になった。他にも、ノ
アが箱舟の中で過ごした日数、イスラエルが荒野を旅した年数等々。
この考え方でゆくと、おそらく数字の上がっているところはみな、聖書的な
根拠ということになると思う。中でもおもしろいのはヨハネ21:11の「シモ
ン・ペテロは〔船に〕乗り、大きな魚がいっぱい、百五十三匹というふうに端
の数まできちんと数えてあるので、奉仕報告の数字は正確に数えるべきである
という具合になる。初期クリスチャンが毎月組織に対して奉仕報告をしていた
などという記録は、聖書のどこにも記されていない。キリストへの報告にした
ところで、弟子たちが果たして「取り決め」で報告したのか、それともその必
要性を感じて自発的に報告したのかは、明示されていない以上分からないこと
である。また、全員が奉仕報告をするということと、誰かが統計や集計をまと
めるということは決して同じことではない。それをなぜ、奉仕報告の聖書的根
拠一色でみることになるかといえば、つまりは組織がそのようにしたいからに
他ならない。
こういう取り決め中心の体制では、組織が大きくなると共に必ず取り決めの
数も増えてゆく。生じてくる問題やあいまいな部分を取り決めで解決しようと
するのであるから、増えるのは当然である。やがてはいかに多くの規定が必要
になるかはタルムード、ミシュナ、ゲマラや現代の法律を見れば良いであろ
う。2年ほど前になるが、すでに長老の数の少ない会衆では、ものみの塔協会
から送られてくる書類をこなすだけでも大変だという状況になっていた。
加えて、取り決めが多くなればなるほど、それを管理するための官僚も大勢
必要になってくる。取り決めの適用を巡って、骨の折れるような様々な問題が
生じてくるからである。組織化が進むにつれ専門の管理職が存在するようにな
り、階級制度が発達して行く。やがて落ち着く先は、パリサイ的体質というこ
とになる。
「ピーターのピラミッド法則」という本は、組織の成長を3段階に分けて説
明しているが、この過程と特徴は宗教組織にもそっくりそのまま当てはまる。
- サービス中心の段階
成員のすべてがまだ組織本来の主旨や目的を認識しており、組織は顧客を中
心に機能する。まだ組織が組織外の人々に奉仕する段階である。
- 組織中心の段階
業務の拡大とともに組織化が進み、取り決めが増大する。
- 管理者中心の段階
成員の関心は主に組織内の管理者に向けられるようになり、フレキシビリテ
ィー(柔軟性)は消えてゆく。組織が顧客にサービスするのではなくて、顧客
の方がかえって組織の取り決めや書式に従い組織に仕えるという本来の主旨と
は全く逆の状態が出現する。
ものみの塔協会は、この段階のどこまできているであろうか。おそらく3段
階の末期ではないかと思う。特に宗教組織という性質上、ものみの塔協会の場
合、組織支配による弊害には著しいものがある。この組織病に対する有効な処
方箋はまだない。
(3)特権体質
エホバの証人の社会で非常によく耳にする言葉に「特権」という用語があ
る。一般にはあまり使われない言葉なので、最初はその頻度の多さに驚く。お
そらく組織用語の中では、最もよく使われているのではないかと思う。
試しにどのくらい出てくるのか数えてみた。次に上げた数字は、ものみの塔
誌に載った経験の中で用いられている「特権」という語の使用回数である。
「統治体のメンバー」
カール・クライン(12回)ケアリー・バーバー(3回)ダニエル・シドリ
ック(4回)ジョン・バー(4回)
F・W・フランズ(6回)故グラント・スーター(10回)
「その他の兄弟、姉妹」
エーリッヒ・カットナー(3回)スタン・ウッドバーンとジム・ウッドバー
ン(3回)ベルナルド・デ・サンタナ(1回)エバ・キャロル・アボット
(0回)工藤百合子(1回)ポール・スミット(1回)アーサー・グスタ
ブソン(0回)ワイカト・グレー(0回)フェルナンド・マリン(0回)
マグダレーナ・クセロウ・ロイター(1回)エリック・ブリッテン(1回)
サムエル・B・フレンド(3回)ハロルド・E・ギル(1回)P・J・ウェンツ
ェル(2回)タリサ・ゴット(2回)
他の兄弟たちに比べて統治体の方が、はるかに多く特権という言葉を使って
いる。統治体の経験は他の人より紙面が多いので、そのせいもあるとは思う
が、しかし、傾向ははっきりしている。全般的に組織のピラミッドを上がって
行くほど、特権の使用回数は多くなってくる。やはりそれだけ、特権だと心か
ら感じることが多いのであろう。また特権志向の強い人が特権を捕らえやすい
という背景も関係しているのではないかと思う。普通のエホバの証人よりは、
ものみの塔協会の代表者ほど頻度は高い。
《特権にこめられた意味》
この「特権」という言葉の使い方は、意味合いから分類するとだいたい二通
りになる。たぶん多くの人は、はっきり意識することもなく使っているのでは
ないかと思うが、深層心理からいうと二つに分けることができる。ひとつは快
感神経を刺激するような使い方で、これが最も多い。特権という言葉の性質上
当然そうなるとは思うが。もう一つは少々屈折した使い方で、大会会場や集会
などでよく耳にするものである。
次に挙げるのは、最初の方の使用例であるが、中にはこういう言い方が口癖
のようになっている人もいる。
「ものみの塔協会の当時の会長だったJ・F・ラザフォードを親しく知るという
まれな特権にも恵まれました」
「ノア兄弟は私を戒め、より大きな奉仕の特権を提供されたら、それを熱心な
態度で受け入れなければならないと言いました」(1984年10/15号p.28カ
ール・クライン)
「ラザフォード判事はそのような人の一人で、私はカリフォルニア州サンディ
エゴにあった同兄弟の家に伺う特権を得ました」(1985年6/1号p.27D・
シドリック)
「私が1920年代にあずかった大変貴重な特権の一つは、1926年に英国のロンド
ンで開催された国際大会でラザフォード兄弟と一緒に奉仕したことです」
「ネイサン・H・ノアと共に交われたことは、非常に大きな特権でした」
(1987年5/1号p.28、29F・W・フランズ)
「そのプログラムのためにラザフォード兄弟のアナウンサーを務めさせていた
だいたのは特権でした」
「1941年10月1日に、ラザフォード兄弟が欠席したためにペンシルバニア州の
ものみの塔聖書冊子協会の年次総会を司会する特権を私がいただきました」
「数々の歴史的な退会の際に話し手の一人として奉仕するのも特別な特権でし
た」
(1983年12/1号p.12、13グラント・スーター)
「1977年9月には、米国ニューヨーク市ブルックリンにあるエホバの証人の統
治体の成員になるようにという比類のない特権が差し伸べられました。」
(1987年7/1号p.29ジョン・バー)
「1961年9月から1963年9月まで、ニューヨーク市ブルックリンにある協会の本
部で、特別な翻訳関係の仕事をする特権をいただきました」
(1987年4月1日号p.25エーリッヒ・カットナー)
「大勢の子供たちが、当時のものみの塔協会の会長ラザフォード兄弟から『子
供たち』という本を無料でいただいたのもその大会のときで、私の子供も3人
全部その特権にあずかりました」
(1987年6月1日号p.23ある姉妹)
アメリカの年鑑から
「わたしは1916年10月29日にロサンゼルスで行われた、ラッセル兄弟の最後の
講演会に出席する特権を得ました」
(P.79ドワイト・T・ケニヨン)
「1906年に、J・F・ラザフォードはエホバへの献身を象徴しました。マクミラ
ン兄弟は次のように書いています。『わたしはミネソタ州セント・ポールで彼
に浸礼を施す特権にあずかりました。…』」(P.83)
「わたしは兄弟たちが監禁されていた1918年の夏の終わりごろにブルックリ
ン・べテルを訪問する特権にあずかりました」「兄弟たちからの報告を聞く特
権を得ました」
(P.109,110T・J・サリバン)
1959年の1月から…姉妹たちにも神権宣教学校に入学する特権が与えられま
した。(P.198)
これは一見すると謙遜ふう、中には本当にそういう気持ちで使っている人も
いるかもしれないが、しかし、実際はほとんどが経歴の自慢、奥底に晴れがま
しいという感情が見え隠れしているものばかりである。「…は特権です」とい
うとき、本人はさぞかし気持ちが良いかもしれないが、記事を読む人の霊的高
揚には少しも役立たない。
ある特定の人物と特権意識が結びつくとすれば、それは人物崇拝になりかね
ない。「教祖様の御顔を拝する光栄に浴しました」というのと、「ものみの塔
協会の会長ノア兄弟と交わる特権に与りました」というのは、それほど大きな
違いはないからである。あるいは、そういう言い方をすることによって自分の
立場や組織を誇示しているのであれば、真のキリスト教とはまったく無縁の世
界である。
次はもう一つの特権の使い方。
「兄弟たちの物質的な必要物をわずかながら融通して援助する特権に与れたこ
とは喜びでした」
(アメリカの年鑑P.209)
「神のみことばと王国を宣明するというすばらしい特権をエホバに感謝してい
ます」(P.255)
「エホバの民は、……神の目的や救いのための数々の備えを知らせるというな
んとすばらしい特権を享受しているのでしょう!」(P.256)
「アメリカ全土の兄弟のために雑誌用かばんを縫う特権にあずかりました」
(P.163)
「地上で永遠に住むすばらしい見込みをもつすべての人々に、その王国政府が
もたらす数々の優れた祝福を語りつづけており、その特権に感謝しておりま
す」(1986年9月1日号P.13)
大会会場や集会では、
- 「兄弟、ゴミの運搬も特権ですから頑張ってください。」
- 「姉妹、お掃除本当にご苦労さまでした。」「いいえ、特権ですから。」
- 「皆さん、トイレ掃除は特権です。ぜひ自発奉仕を申し込んでください。」
等々、
このような使い方がよくなされている。
これはどちらかといえば、そう思うように努力しているという建前的な特権
の使い方で、組織上はそういうふうに言わないと、締りが付かないという一面
もある。この種の特権には、ときに非常に鬱積した暗い感情が伴う場合があ
る。本当はもっと良いポジションに付きたいのであるが、そのようにはならな
かったので、せめて「特権です」といって自分を慰める。欲しい特権を手に入
れた人は満足しているので、「ゴミ拾いだって特権でしょう。同じようにエホ
バに仕えているわけですから。」といかにも励ますように余裕を持って言う。
心の中では少しもそうは思っていないのに。不自然さを通り越して、何か奇異
な感じすらする使い方である。
この特権と言う言葉は何度聞いても、ついに最後までなじむことができなか
った。
<<新世界訳の中の特権>>
新世界訳聖書に「特権」を登場させたのは、もちろん新世界訳翻訳委員会で
ある。それでは、エホバの証人の中に「特権」を定着させたのは一体誰であろ
うか。この語の背景については説明している記事がないので、私たちにもよく
わからない。今は不可能であるが、機会があれば是非ものみの塔協会に尋ねて
みたい。ただ出版物を読むと、この語はかなり前から使われていたことがわか
る。ラザフォード兄弟の時代にも出てきているところを見ると、特権の歴史は
相当に古いと言えるようだ。
新世界訳聖書には、「特権」は全部で7回出てくるが、いかにその聖句のす
べてを引用することにする。ただし、[特権]は新世界訳翻訳委員会が挿入した
ものである。
「いつの日もみ前で忠節と義とをもって恐れなく神聖な奉仕をささげる特権を
わたしたちに得させるためなのです」(ルカ1:75)
「あなたがたには、キリストのために、彼に信仰を置く特権だけでなく、彼の
ために苦しむ[特権]をも与えられたからです」(フィリピ1:29)
「ペテロから、わたしたちの神と救い主イエス・キリストの義により、わたし
たちと同じ特権としての信仰を得ている人々へ」(IIペテロ1:1)
「彼(ダビデ)は、神のみ前に恵みを得、ヤコブの神のために住まいを備える
[特権]を請い求めました」(使徒7:46)
「そして、わたしの主の母に来ていただくこの[特権]がわたしのものになるの
はどうしてなのでしょうか」(ルカ1:43)
「それでも彼は自ら進んで、親切に与える[特権]と、聖なる者たちへの奉仕に
あずかることとをわたしたちに請い求め、しきりに懇願したのです」(コリン
トII8:4)
この聖句の中で「特権」と訳すべきところは全くない。もちろん挿入しなけ
ればならないようなところは一箇所もない。もとのギリシャ語本文で字義的に
特権に相当する言葉は、どこにも使われていないからである。ただし、特権と
いう意味がそのギリシャ語の中に無いということではない。そのように訳した
いと思えば、そういう訳語を選んでくることはできる。しかし、その必然性は
全くない。これは完全に好みの問題である。
完全逐語訳であるものみの塔協会の王国行間逐語訳聖書にさえ「特権」は出
てこない。それではなぜ、新世界訳には特権があるのか、これはやはり、新世
界訳翻訳委員会の解釈、好みとしか言いようがない。挿入してまで登場させよ
うというのだから、よほど「特権」が好きなのであろう。新世界訳が出版され
るかなり前から、ものみの塔協会には根深い特権体質があったと考えてよいと
思う。
特権を使っている聖句をもう一度よく読んでみていただきたい。そこには、
ものみの塔協会が何を特権と考えているか、あるいは、何を特権と考えさせた
いかが反映されている。
「神に奉仕すること、信仰を持つこと、キリストのために苦しむこと、仲間
の一員でいること、神殿を建てること(現在で言えばべテルや王国会館を建て
ることと考えてよい)、マリアのような著名な人の訪問を受けること、組織の
代表者をもてなすこと」などである。
<<特権体質の弊害>>
1.イメージを悪くする
好きな人は愛着すら感じるであろうが、普通の人ならば、特権と言う言葉に
良いイメージを持っている人はほとんどいないと思う。どちらかといえば、こ
れは非常にイメージの悪い言葉である。
なぜなら「特権」とは、「特定の人、身分、階級、国家などに与えられる特
別の権利」(学研国語大辞典)「特定の(身分や階級に属する)人に特別に与
えられる優越的な権利」(広辞苑)という意味で、すぐに「特権階級」という
言葉を連想させるからである。一部の人にとって特権とは、階級差別、階級制
度の代名詞のような言葉になっている。英語のprivilegeも意味にたいした違
いはない。
したがって、「特権」を連発すると、組織のイメージは悪くなると考えるの
が普通の感覚である。しかし、ものみの塔協会は幹部ほど特権を使っているわ
けだから、感覚がよほど特異なのか、特権体質の人を集めて養成したいかのい
ずれかであろう。
2.動機が汚染される
特権欲を動機とする人々のエネルギーはすさまじいものである。組織にとっ
ては、こういう人々こそ大変ありがたい存在であろう。拡大には欠かせない貴
重な人材であろう。せめて特権をもって報いるということになるのかもしれな
い。
しかし反面、動機が汚染され、霊的な荒廃は進行してゆく。特権のポストは
限られているので、満たされない人々のねたみ、嫉妬、そねみが渦巻くことに
なる。特権競争が激しくなり、霊的パラダイスは名ばかりの存在になってしま
う。なんとも難しいものである。
結局のところ、特権欲とは自己顕示欲である。エネルギーはすごいが、利他
的な誠心にはならない。本人が利他的だと思っていても、それは表層的な意識
に過ぎず、よく分かっている人は偽善的になる。これは神の名を付したミーイ
ズムとも言える。
3.エホバの神性、キリストの精神に反する
子どもが親のために苦しみにあっているときそれを特権とみなしなさいとい
う親はいったいどういう性格をしているか考えてみたらすぐにわかるだろう。
厳しい迫害にあっているとき、それを特権と自発的に考えるのと、神がそのよ
うに勧めるのとは、全然話が違う。
また、イエスが「私はメシアになれて特権でした、人類のために死ぬことが
できたのは比類のない特権でした、神の王国の王になれたのは類い稀な特権で
した」と言って自己満足にひたっている姿を果たして想像できるであろうか?
4.特権崇拝
崇拝の構造はこうである。
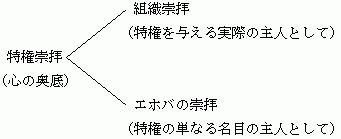
もう充分の特権を得たと思えば、何とかしてそれを失うまいと腐心する。も
っと特権が欲しいと思う人は、さらに上を狙う。いずれにしても、エホバの証
人としての節操をかなぐり捨て、ひたすら上部の機嫌取りに精を出すことにな
る。特権なくして生活ができるだろうかと言う人が出てきたり、特権のためな
らば、平気でウソをつき、聖書を脇に追いやっても何ともないという監督たち
が増えてくる。このレベルになると、もはや完全に特権崇拝であろう。
この特権体質、特権欲の世界は、自己顕示欲が絶え間なくうずいている世界
でもある。ものみの塔協会の体質の中でも、これは最も醜い一面であろう。
(4)体質の持つ恐ろしさ
仮にキリストがごく普通の兄弟の姿になって、神からのメッセージを伝える
ため、ものみの塔協会の本部を尋ねたとしたらどうなるであろうか。受け入れ
られる可能性はほとんどゼロに近いと思う。「私はイエス・キリストです」と
言おうものなら、気違いと思われるのがせいぜいではなかろうか。
ものみの塔協会の教義では、神の組織に対する指示はキリストを通して、真
っ先に統治体に来ることになっている。それからものみの塔協会を経由して組
織の末端まで送られることになる。このルートは神権的秩序と呼ばれ、神がこ
のルートを否定することはありえないとされているので、誰がキリストだと言
っても、エホバの証人は信用しないのである。
それでは今度は逆に、サタンが立派な背広を着て、組織上の権威を持って尋
ねたらどうなるだろうか。おそらく受け入れられる可能性は、限りなく100%
に近いと思う。よほど変なことをしなければ、見破られるには相当の期間がか
かるであろう。
これはあくまで単なる仮想実験、思考実験に過ぎない。それでもこういうこ
とが言えるというのは、ものみの塔協会の体質が問題だからである。この章で
指摘してきたように、現在のものみの塔協会は、真理そのものによって判定す
るのではなく、組織の権威によって判断するシステムになっている。真理とは
すなわち組織なのである。組織の代表者、組織のスタンプ、組織上の特権には
非常に弱い体質である。もしサタンがこのシステムを利用するなら、組織内に
容易に潜り込むことができるであろう。
<<パターン認識>>
この種の絵は心理学のテストなどでよく使われるものであるが、まず最初に
次の絵をご覧になっていただきたい。
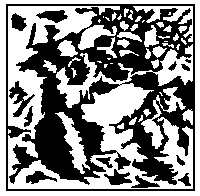
おそらくほとんどの人は一見しただけでは何の絵か分からないと思う。こう
いう絵を見ると、人間にはそこに何らかの意味を読み取ろうとする傾向がある
ので、しばらくすると、人の顔とか動物の姿とか何かの形が見えてくるかみそ
れない。しかし、それが正しいかどうかの確信はまだないはずである。
今度は、このページの絵を見て、もう一度前のページの絵をご覧になってい
ただきたい。カエルの顔の部分はちょっと分かりにくいかもしれないが、両方
ともはっきり見えてくるはずである。
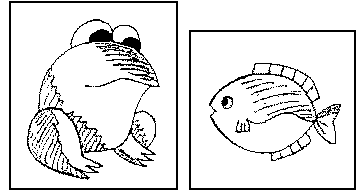
これは情報の意味を解釈できるだけの認識パターンが形成されたことによ
る。このパターンができあがると、もはや識別するのに困難を覚えることはな
くなる。加えて、他の人にも確信をもって、これは魚です、これはカエルです
と言えるようになる。
宗教の場合この認識パターンのアウトラインを決定してゆくのは教義である
が、実際もっとも強力なのはその組織の体質である。教義は建前、体質は本音
の世界だからである。特定の体質の中で長い間育まれてゆくと、細胞のレベル
までそのパターンがしみついてしまう。変えようとすると、生理的な拒否反応
が起きてくるようになる。これは実に強力なものである。
また意識するにせよそうでないにせよ、一度形作られたパターンは、その後
の判断を支配してゆくことになる。最初の絵はもう魚かカエル以外には見えな
いはずである。
このように体質の持つ本当の恐ろしさは、体質が判断や認識の支配的な基準
になってしまうという点にある。そのモードに染まった人には、そのパターン
でしかものが見えなくなってしまう。
再度繰り返すがこれは非常に恐ろしいものである。体験者がいうのだから絶
対に間違いはない。組織がカエルといえばカエルになり、魚といえば魚になる
のである。それ以外の見方はみな組織に対する反逆、神に対する不忠節にされ
てしまう。組織が一つの見方に神の名を付してそれを絶対化すると、他の見方
はすべて排撃されてしまう。このようにして極端に一義的、一律的な体質が出
来上がる。
輸血や武道その他不評を買っている教義のほとんどは、本来の精神そのもの
は悪くないにしても、適用の仕方に問題のあるものばかりである。なぜそうな
るかといえば、ものみの塔協会の体質があまりにも一義的だからである。組織
の適用が本来の精神を越えてしまったところに、この教義の真の問題がある。
(詳しくは現在広島会衆で検討中である。)
この宗教的パターン認識の図式を考えてみると、キリストの述べた次の言葉
の心理的なからくりが、よく分かるのではなかろうか。
「人々はあなた方を会衆から追放するでしょう。事実、あなた方を殺す者がみ
な、自分は神に神聖な奉仕をささげたのだと思うときが来ようとしています」
(ヨハネ16:2)
パターン認識が殺人と判定しなければ、殺人も殺人ではなくなる。
<<ものみの塔協会の体質は癒せるか>>
ものみの塔協会の代表的な体質として、組織主義、組織崇拝、取り決め偏
重、特権崇拝を上げたが、もう一つ、偽善的な体質を付け加える必要がある。
今回の広島会衆が直面した事件で明らかになった最大のものは、この偽善的な
体質であったからである。
これらの体質はどれを取ってみても、キリスト教の価値観から言えば、致命
的な病ばかりである。癒しは非常に難しい。第一本人たちに直す気が全くない
のだから、エホバも癒しようがないのではなかろうか。
特権こそ命のような人々にとって、そのよりどころとする体質を変えられた
ら非常に困るであろうし、一度吸った甘い汁はそう簡単には忘れられないと思
う。おそらく、体質を変えようとする者がエホバとキリストであっても、彼ら
は今の体質を維持するために必死に戦おうとするのではないだろうか。ものみ
の塔協会の反応を見ていると、そのように思えて仕方がない。
今回私たちは、政治と宗教が分離されている国に住んでいて、本当に良かっ
たと思った。もし、ものみの塔協会が政治上の実権を握っていたなら、おそら
く広島会衆のかなりの成員が処刑されてしまったのではないかと思う。まさに
雰囲気は中世の異端審問、宗教裁判をほうふつとさせるものがあった。半分冗
談交じりではあったが、山にでも籠ろうかと話していたくらいである。
ものみの塔協会の幹部が実際に政権を握ったら、間違いなく恐怖政治、神権
ファシズムの体制になる。霊的には今でもそういう体質なのだから。彼らが天
に行って神の王国の成員になったら、それこそ一番迷惑するのは地上の住民で
はないだろうか。もっともエホバとキリストがいれば大丈夫かもしれないが。
それにしても、自覚症状のない人が多いので、危険な存在ではある。
古代ユダヤ教の体制は神に捨てられ、一世紀のユダヤ教の体制もまた神に退
けられた。癒すことができなかったからである。果たして、ものみの塔協会は
どうなるであろうか。