
1982年夏の大会で、待望久しい日本語版の新世界訳聖書(ものみの塔協会発行)が発表されました。その新しい聖書は日本中のエホバの証人から、そして彼らと共に聖書を学ぶ大勢の人々から、歓呼を持って迎えられた。
それまで、一巻にまとめられた聖書はなく、ほとんどのエホバの証人は、ギリシャ語聖書(新約1973年刊行)が新世界訳、ヘブライ語聖書(旧訳)の方は文語訳(日本聖書協会発行)という具合に、二冊の聖書を使っていた。中には特別に製本してもらい一巻にまとめている人もいたが、たいていの人は集会や奉仕に二冊の聖書を持ち歩かねばならず、ずいぶん不便な思いをしていたのである。
こうして大いに歓迎された新世界訳ではあったが、しばらくすると、どうにも引っかかるものを感じて仕方がなくなった。何とも読みにくいのである。思わず首をひねってしまうような文章がかなりの数に上る。極めて難解だ、分かりにくいという印象を深めるようになった。新改訳や文語訳と比較してみると、新世界訳よりもずっと意味が分かりやすいというところが沢山あった。究極の聖書、世界一の聖書というものみの塔協会の宣伝のわりにはどうにも冴えないのである。
しかし、この当時はまだ翻訳に問題があるとはまったく考えていなかった。まして英語版の方に何か欠陥があるなどとは夢想だにしなかった。ひたすら自分たちの頭が悪いせいである、こちらの理解力不足に原因があると思いこんでいた。聖書はもともと難しいものであるという先入観も働いていたのではないかと思う。
それがどうもこれは私たちの頭のせいばかりではなく、翻訳にも問題があるのではないかと考えるようになったのは、日本語版と英語版を比べて読み出してからである。
特に、英語版を見ていて、「この表現は意味の異なる何通りかの訳が可能である、一体どっちの方を選んだのであろう」と思えるようなところを重点的に当たってみた。すると、なるほどと感じさせられるほど巧みに訳してある箇所もある反面、「これでは分かりにくいのも無理はない、どうしてこんなふうに訳したんだろう、もっと全体の意味を考えればよかったのに、はっきり言えば誤訳ではないか」と思うようなところも幾つか見出されるようになった。「一度、本格的に検討してみる必要があるのではないか」ということになったのは、去年の夏のことである。
9月からチームを組んで、創世記から調査を開始した。作業を始めてみると間もなく、英語版と日本語版を比較するだけではどうしようもないことが分かった。英語のある単語に何通りかの意味がある場合、文脈から判断するだけでは、その意味を固定することはできなかった。幾通りもある意味の中からそのうちのどれを選ぶかということは、単なる英語から日本語への翻訳の問題だけでは片付かないからである。
例えば後でも取り上げるが、最初にぶつかったのが創世記1章2節に出てくる「水の深み」(もとの英語はwatery deep)という語であった。このwatery deepに対して日本語版は統一的に「水の深み」という訳語を当てている。
「deep」には形容詞の他に「淵、深淵、海、大海原、海淵、海溝、大空」など名詞としても多くの意味がある。しかし日本語の「深み」には「(川などの)深い所、深間、深さの程度」というような狭い意味しかない「deep」に比べ、「深み」は非常に意味の振幅が小さいのである。
「watery deep」に対して、はたして全部「水の深み」で良いかどうかを確かめるには、聖書の原語であるヘブライ語を見てその意味にどの程度の幅があるかを調べてみる以外にはない。というわけで、ヘブライ語に関する知識はほとんどなかったが、私たちにできる範囲で資料を集め、ヘブライ語からの検討も始めることにした。
創世記の調査は約一ヶ月で終了したが、多少の疑問は感じながらも、その段階ではまだ英語版に問題があるとは思っていなかった。欠陥のほとんどは日本語訳の悪訳、迷訳、誤訳のせいであろうと考えていた。しかし、調査を進めるにしたがって、しだいに日本語版だけに罪があるとは言えないのではないかと思うようになった。
というのは、感心するくらい日本語版は英語版に忠実なのである。本当にその忠実さには敬服してしまう。英語版を字句通り、ただひたすら忠実に訳せばだいたい今の日本語版になる。
そうである以上、日本語版だけが欠陥聖書で英語版にはまったく問題がないなどということが、果たしてあり得るだろうか。そういうことはとても考えられない。むしろ、日本語版の問題点の大部分は決して日本語版だけのものではなく、英語版と共通の病根を有していると判断するのがごく自然なことであろう。時が立てば立つほど、英語版の抱えている本質的な問題点が、極端に出てしまったのが今の日本語版ではないかと思えるようになった。
では、そうした問題は一体どこから生じてくるのであろうか。翻訳委員会の語学力の不足がその原因になっているのかというと、どうもそうではないらしい。ものみの塔協会の翻訳スタッフの語学力は、相当に優れたものと考えられるからである。
日本語版の前書きには、次のように記されているくらいである。「この日本語への翻訳は、新世界訳聖書翻訳委員会によるものではありませんが、同委員会の作業を反映し、それに基づいたものです。これは、アメリカ、ペンシルバニア州ものみの塔聖書冊子協会のもとに働く、日本人の有能な翻訳者たちによる忠実で良心的な翻訳です。したがって、私たちは、確信と喜びを抱きつつ、祈りを込めて、この新世界訳聖書を日本語の読者のために刊行いたします」(下線は広島会衆)
また「目ざめよ」誌1987年3月22日号には次のような評価が載せられている。
「明らかにこの翻訳は、熟練した有能な学者たちの手によるものである。彼らは、可能な限りの英語表現を駆使してギリシャ語本文の真の意味をできるだけ正確に伝えようとしてきた」(ヘブライ語およびギリシャ語学者アレグザンダー・トムソン・ディファレンシエーター誌、1952年4月号、P.52-57)
「この新約聖書の翻訳は、匿名の委員から成る委員会によって行われた。その委員会はギリシャ語に対する並外れた能力を備えていた」(アンドーバー・ニュートン・クォータリー誌、1986年9月号)
これでは語学力に原因があるとはまず考えられない。実際調べてみるとよく分かるが、新世界訳翻訳委員会が多大の努力を払い、字義を熱心にしかも徹底的に研究していることは間違いのないことである。その調査にはおそらく膨大な時間とエネルギーが投入されたに違いない。新世界訳聖書がそうした絶え間ない研究の成果の結晶であることに疑問の余地はない。
したがって、単なる翻訳の技術の問題といったような、表層的なものが原因になっているとはとても考えられない。本質的な原因は、何かもっと深いところに根ざしているのではないかと思われるのである。
新世界訳聖書というのは字義訳聖書である。この字義訳という翻訳方針は新世界訳の看板になっている。もちろん字義訳にもそれなりの利点はあると思うが、「過ぎたるは及ばざるよりも劣れり」で、字義優先に走り過ぎると深刻な問題が生じてくる。新世界訳聖書の問題の原因を考えて行くうちに、最後に浮かび上ったのは、この字義訳主義ともいえるものみの塔協会の翻訳姿勢、ないしは翻訳のモードであった。新世界訳聖書の欠陥はまさにこうした極めて本質的な部分から来ていると考えられるのである。
さて、たいていの宗教組織は、組織に入るまでは奉仕者、組織に入ってしまえば支配者といった二つの顔を持っている。言い換えると、組織に入るまでは建前で接し、入ってしまえば本音で扱うということである。巨大な組織宗教になるほど建前と本音が巧みに分れているので、組織の成員にはその自覚がほとんどないくらいである。充分わかったときにはもう遅い、つまり、心理的な意味でいえば、仏罰が恐ろしいとかハルマゲドンの滅びが恐ろしいということになりかねないのが普通である。もっとも、あまり深刻に考えない人であれば、強迫観念に苦しめられることはないと思うが。
ものみの塔協会も、もちろん例外ではない。むしろ、そういう組織の典型的な部類に入るであろう。全員がそうだとは言わないが、組織的に円熟した人とは使い分けの見事な人のことであり、そういう人ほど組織の階級制度を上って幹部になっているのが実状である。また、諸教会に脅威を与えるほどの猛烈な伝道のエネルギーも、極端なまでの終末観と決して無関係ではない。
ほとんどのキリスト教の組織の場合、組織の本音の部分における聖書観、取り組み方というのが、その組織の在り方や体質を端的に示すものとなっている。同時にそれは、教義とも密接に関連しており、時には教義自体、聖書教義と組織教義とに分かれていることもある。複雑に入り組んではいるが、組織の本音と建前はまた教義における本音と建前でもある。もし、その組織で独自の聖書翻訳を出すとすれば、こうした諸々の要素が翻訳の姿勢や方針を決定する主要な要因となる。
聖書と教義、組織の体質は一方的な関係ではない。両者は交互に関係し合っている。いったん聖書解釈の規準が定められると、今度はそれがフィードバックシステムのように組織に還元され、逆に組織そのものの体質を育んでゆくという側面もある。そのような組織モードが巨大な潮流に成長すると、もはや組織自体にも制御不能となる。モードを変えることは、一度組織の歩みを止めるほどの大きな変化を求められることになるからである。
このように、教義と翻訳そして組織の体質は、はっきりと境界線を引くことのできない位相関係のようなものであり、どちらか一方を分離して扱うというようなことはできない。それゆえ新世界訳聖書の欠陥と、ものみの塔協会の体質上の問題点もまた、切り離して考えることのできないものと言える。それは同質、同根のものと考えられるのである。
何といっても、現ものみの塔協会の最大の欠陥は、神権ファシズム、組織崇拝ともいえるその体質であり、それが生み出した弊害である。したがって一言でいえば、新世界訳の欠陥とは、この組織崇拝が生み出した欠陥でもある、というのが今回の私たちの調査の最終的な印象であった。それは同時に、組織崇拝を育んだものみの塔協会の教義上の欠陥でもあろう。
さて、2章以降で上げる新世界訳聖書の具体的な問題点は、一部、新世界訳翻訳委員会にも送り、何度かその見解を尋ねたものである。また、早急に改訳が必要であることを伝え、その意志があるかどうかを聞いてみたが、まったく返事はなかった。
彼らには質問に答える責任があるはずである。沈黙は重大な違反行為といえる。なぜなら1982年版の前書きには、次のように記されているからである。
聖書をその原語であるヘブライ語、アラム語およびギリシャ語から現代の言葉に翻訳することは、重い責任の伴う仕事です。・・・・これは人を厳粛な気持ちにさせます。聖書の著者であられる神に対する恐れと愛を抱く翻訳者は、そのお考えや宣言をできる限り正確に伝えるよう、特に神に対して責任を感じます。また、現代の翻訳聖書を熱心に研究し、永遠の救いのために至高の神の霊感の言葉に依り頼む読者に対しても責任を感じます」(下線は広島会衆)
このように表明している以上、良心的なクリスチャンであれば質問に答えるはずである。しかし、新世界訳翻訳委員会は一かけらの誠意も示そうとはしなかった。神に対する恐れ、愛、責任、いったいどこへ行ってしまったのであろうか。どうやら単なる言葉でしかないようである。
至高の神の名を自らに付し、世界の何百万という人々を指導する立場にありながら、平然と偽善的な態度を取り続けるとは・・・・。これが今回の調査を公表するに至った最大の理由である。またできればこれを機会に聖書翻訳、教義、組織等のより本質的な問題点をさらに検討してゆきたいと考えている。
エホバの証人は、カトリックやプロテスタントなどの伝統的なキリスト教会の教えとはかなり異なった、独特の教理を有している。それらの教理は必ずしもエホバの証人がまったく独自に、しかも新たに作りだしたものというわけではないが、世界的な規模を有する宗教団体としては、やはり特異なものであろう。最近はエホバの証人というと、輸血や武道の問題が主にクローズアップされがちであるが、キリスト教のより本質的な面から言えば、以下のような教理を上げることができる。
伝統的なキリスト教の教理を否定するこうした教えこそ聖書の伝える真理そのものであり、三位一体、不滅の魂、地獄の教えなどは背教したキリスト教の教理であると信じるエホバの証人にとって、既存の聖書が満足のゆくものでなくなるのは自然の流れであろう。というのは、それまでの聖書はどれもみな伝統的なキリスト教の教理を反映するものであったからである。
検討してみれば分かることであるが、聖書翻訳には例外なくその訳者の宗教信条が入り込む。なぜなら教義上の判断ないし解釈を下さないと、どうにも訳しようのないところが、必ず出てくるからである。
そういう例の代表的なものとしては、ヘブライ語「シェオール」ギリシャ語「ハーデス」や「ゲヘナ」を上げることができる。これらには「墓、穴、黄泉、冥府、地獄」などの訳語が当てられているが、もし特定の教義上の解釈を入れないとすれば単なる音訳を選ぶことになろう。どういうふうに訳すかはその訳者や翻訳委員会の信条によって変わってくる。これらの語が抱えているこうした問題点について、新改訳聖書の「あとがき」には次のような記述が載せられている。
新約聖書で(ハデス)(ゲヘナ)と訳出されているのは、それぞれ、「死者が終末の裁きを待つ間の中間状態で置かれる所」「神の究極の裁きにより、罪人が入れられる苦しみの場所」をさすが、適切な訳語がないために音訳にとどめたのである。しかし、旧約聖書では、新約の(ハデス)に対応する(シェオル)を(よみ)と訳した。これらの訳語の統一については、さらに検討が必要であろう。
日本聖書協会口語訳(以下口語訳と略す)では「ゲヘナ」は「地獄」「ハデス」は「黄泉」、共同訳では「ゲヘナ」が「地獄」「ハデス」が「死者の国」になっている。新世界訳の場合は両者とも音訳である。
さらに、もう一つだけ教義上の解釈が関係してくる例を上げると、三位一体の問題がある。三位一体を信じる人は、父なる神(エホバ)と子なる神(イエス・キリスト)の区別があいまいになるような、そして聖霊をできるだけ人格を持つ者として印象付けるような表現を選ぶ。「エホバ」とか「ヤーウェ」という神の名を用いるよりも単に「主」や「神」という表現を好むのである。そうすれば、キリストも「主」や「神」と呼ばれているので、どっちがどっちか分からなくなってしまう。三位一体を論証しようとするにはそのような聖書の方がはるかに都合がよい。逆に三位一体を否定する人は、エホバとキリストの区別をできるだけ明確にしようと心がけるし、聖書は非人格的なものとして表わそうとする。神の名を用いることをためらう必要はまったくない。むしろ、できるだけ訳出しようとする。
このように聖書翻訳には必ず宗教信条が入り込む以上、エホバの証人が自らの真理を正しく伝える聖書が欲しいと願うようになるのは、ごく自然なことであろうと思う。
「霊感の本」は1940年代における新世界訳刊行当時のいきさつを次のように説明している。
エホバの証人は神のみ言葉の心理を把握するために用いてきた数多くの聖書翻訳すべてから受けた恩恵に感謝しています。しかし、これらの翻訳はすべて、最新のものでさえ、それぞれ欠陥があります。宗派的伝承やこの世の哲学の影響を受け、またそのためにエホバがそのみ言葉の中に書き記させた聖なる真理と完全には調和しない、一貫性の書けた所や、訳し方の不満足な箇所があります。特に1946年以来、ものみの塔聖書冊子協会の会長は、原語から訳された、聖書の忠実な翻訳ー聖書時代の理解力のある普通の人々にとってその原書が理解できたのと同じように、現代の読者にも理解できるような翻訳を望んできました。
1949年9月3日会長は協会のブルックリンの本部で、クリスチャン・ギリシャ語聖書の翻訳を完成した「新世界訳聖書翻訳委員会」が存在することを理事会に発表しました。同委員会の作成した文章が読まれましたが、同委員会はその文章により、全地で聖書知識の増進を図る当協会の非宗派的事業を認めて、その翻訳原稿の所有・管理および出版を当協会に委任しました。またその翻訳の性格や質を示す実例として原稿の一部が読まれました。理事たちは寄贈されたその翻訳を全員一致のもとに受け入れ、それを印刷するための取り決めが設けられました。1949年9月29日には活字組が開始され、1950年の初夏までに、その製本が幾万冊も完成しました。(p322、323.16、17節)
こうして新世界訳聖書は1950年8月2日水曜日、ニューヨークのヤンキー野球場で開かれた世界大会で新約(ギリシャ語)の部分がまず発表された。次いで1953年〜1960年にかけて旧約(ヘブライ語)聖書の分冊が何度かに分けて刊行され1961年には一巻にまとめられたもの(英文)が完成した。三年を経ずして、発行部数は366万2、400部に達したと報告されている。以来、新世界訳は様々な言語に翻訳され世界中のエホバの証人に愛用されてきた。
新世界訳翻訳委員会が新しい聖書を刊行するにあたり、その基本方針として採用したのは「字義訳」というスタイルであった。ものみの塔協会は新世界訳発表以来、機会あるごとに字義訳を宣伝し、その利点を強調してきた。この字義訳というのは、いわば、新世界訳の翻訳理念ともいえるものであるが、その点について1982年版新世界訳聖書の前書きには次のように記されている。
「英語の『新世界訳』は原語の本文を努めて字義通りに訳出していますから、この日本語訳もその字義訳の意図をそのまま反映することに努めています」
「字義訳」と訳しているもとの英語は、「literal translation」という語である。研究社の新英和大辞典は、これに「逐語訳、直訳」という訳語を当てている。他の辞書もほとんど同様で、もっとも多いのは「逐語訳」である。したがって、ものみの塔協会は「字義訳」と訳しているが、だいたい逐語訳と同じようなものと考えてよいであろう。ただし逐語訳には「word for word translation」という表現もあるのでそういう種類の逐語訳ではないということであろう。
言うまでもなく完全な逐語訳、そういう意味での字義訳ではとてもまともな文章にはならないから、字義訳といってもそれなりの幅を考慮に入れねばならない。新世界訳参照資料付き聖書(1985年版)の序文はその点について、次のように記している。
「聖句の意訳のための言い換えはなされていません。むしろ、今日の表現法が許すかぎり、また字義通りの訳出によるぎこちなさによって考えが覆われてしまわない範囲で、できるだけ字義通りの訳出を行なうよう努力が払われています」
さらに、ものみの塔誌1979年11月15日号には
「1950年の『クリスチャン・ギリシャ語聖書』の初版(英文)の前書きには、次のように書かれています。『聖書を意訳することはしていません。現代英語の特質の許すかぎり、字義訳のぎこちなさのゆえに意味が不明瞭にならない限り、できるだけ字義通りの訳をするよう一貫する努力が払われました。そうすることにより、一語一語、できるだけ原文に近づけた、原文そのままの陳述を良心的に求める人々の要望に一番よく答えられると思います』。このような誠実さを考えると、聖書研究者は全き確信を抱いてこの翻訳に接し、霊感による原典の考えを推し計ることができます」(P.15)
と述べられている。
これらの記述から判断すると、字義訳新世界訳とは、一語一語、逐語訳した聖書というほどではなくとも、全体としては直訳ふうに訳出した逐語訳聖書ということがいえるであろう。
新世界訳委員会が「字義訳」を選んだのはいったい何故であろうか。「霊感の本」325ページはその点について次のように述べている。
「また、翻訳の忠実さは、それが字義訳であるという点にも明示されてます。・・・・原作の趣や色彩やリズムは、字義訳によって正確に伝達できるでしょう。・・・多くの聖書翻訳者は、表現や形式の優雅さと言われるもののために字義訳の考えを断念してしまいました。それらの翻訳者は、字義訳はぎこちなく、不自然で、窮屈であると主張します。しかし、字義訳を断念したために、元の正確な真実の陳述から逸脱した表現が数多く生じました。そして、実際のところ、神の考えをさえあいまいなものにしてしまいました。・・・・・こうして、幾千もの訳文が表現の美しさに関する人間の考えという祭壇に犠牲としてささげられ、その結果、多数の聖書翻訳の中に不正確な箇所が見られるようになりました。今や、神が、明快で正確な訳文の『新世界訳』聖書を備えてくださったのは、実に感謝すべきことです」
字義訳が選ばれた理由として、まず、忠実さと正確さが上げられている。どんなに美しくかつ流麗な文章であっても不正確であれば、神に対して不忠実になるということであろう。字義訳は正確、意訳は不正確というとらえ方がこの背後にはある。おそらく、それまでに出版された意訳による聖書の弊害が著しいと考えられたせいではないかと思われる。 前にも述べたが、聖書翻訳には必ず訳者の宗教信条が入り込む。特に意訳(free translation or loose translation)の場合はそれが色濃く反映されたものとなるのが普通である。日本語の意訳(原文の一字一句にこだわらず、全体の意味を取って訳すこと・・・旺文社国語辞典)の意味は非常に良いと思うのであるが、free(自由な)、loose(勝手気ままな)ではイメージが悪かったのであろうか。ものみの塔協会には、意訳が聖書の真理をはなはだしくゆがめるものに映ったようである。もっとも、新世界訳を「独自の教理を正当化するために作った独自の聖書」と批難しているキリスト教世界からすれば、まったく逆の見方が成り立つであろうが。いずれにしても、個人の主観が入り込むのを避け、神の言葉を正確に伝えようというのが、字義訳の選ばれた第一の理由のようである。
そのほかにも、ものみの塔協会が字義訳を推奨している記事には、さらに次のような点が上げられている。
「批判的な人々からさえ優れた聖書研究者とみなされているエホバの証人は、『新世界訳聖書』が明快さと正確さの条件を見事に満たしていると考えています」(ものみの塔1985年6月15日号P.5)
「聖書全巻を収めた『新世界訳聖書』は、鮮明な読みやすい字体で印刷された聖書です。分かりやすい現代語が用いられているため、聖書が生気あるものになりました。それでも原語の聖書本文に忠実に従っています。」(ものみの塔1983年3月1日号P.32)
「11年をかけて行われた「新世界訳」(英文)の出版作業全体の数多くの特色の中でも特筆すべき点は、それが聖書の原語ヘブライ語、アラム語およびギリシャ語から新たに翻訳されたものであるということです。それは決して他のいかなる英訳の改訂版でもありませんし、文体や語彙あるいはリズムなどの点で他のどれかの訳を模倣したものでもありません。・・・新世界訳の翻訳委員会は聖書の翻訳に新たな仕方で取り組み、その結果、明確で生き生きした訳文が生まれ、神のみ言葉を一層深く、一層満足のゆく仕方で理解する道が開かれました」(霊感の本P.324)
「協会の『新世界訳聖書』は、大変正確で、しかも読みやすい日本語の聖書翻訳として、日本の兄弟たちや一般の人々から評価されています」(1987エホバの証人の年鑑P.8)
こうした字義訳に関するものみの塔協会の宣伝、それが選ばれた理由をまとめると次のようになる。
字義訳が本当にこの通りであれば、字義訳ほど素晴らしいものはないということになるのであるが・・・・はたして実際はどうであろうか。
この点を考慮するには、まず、翻訳の本来の目的や主旨について確認する必要がある。というのはそれが翻訳の良否を判断する規準となるからである。
最初に、ものみの塔協会の記述の方から見てみることにしよう。1982年6月15日号のものみの塔誌「神の言葉を忠節に擁護する」という記事は、翻訳の目標、理念について次のように述べている。
「聖書の翻訳、そしてすべての翻訳についても言えることですが、その目指すところは翻訳された言葉を読む人々が精神的にも、感情的にも、そうです霊的にも、聖書の原文を読む場合と同じような影響を受けられるようにすることです」(p.22)
ここに述べられている翻訳の目標それ自体については全く異論がないであろう。ほとんどの訳者も同様のことを述べている。例えば、「誤訳、迷訳、欠陥翻訳」の著者は、
「そこで欠陥翻訳について述べるには、理想の翻訳をまず表明しなければならないわけだが、私は、原作者の言わんとするところを正確につかんで、それを自分なりのりっぱな日本語(あるいはその他の国語)で表現したものが理想の翻訳であると、とりあえず申し上げておく」(「誤訳、迷訳、欠陥翻訳」P.10別宮貞徳著)
と述べているし、「翻訳上達法」の著者は、
「・・・・少々の誤訳であればその部分だけ活字を入れ換えるなどして訂正も可能である。しかし、原作の持つ雰囲気、リズムを移しそこなった訳はもう訂正のしようがないからである。
原文の持つ雰囲気をいかに効果的に移植するかということは、これから論議する文学作品の翻訳において、すべての技術に先行するもっとも基本的な問題点である」(「翻訳上達法」P13、14河野一郎著)
と述べている。
こうした引用からも明らかなように、翻訳の理想、趣旨、目標については、訳者間に意見の相違はほとんど見られない。見解が分かれてくるのは、その理想を達成する方法、どんな翻訳のスタイルが良いかについてである。
字義訳を推奨している新世界訳翻訳委員会によれば「字義訳」こそ、その理想に適うもの、最善のスタイルであるということになるだろうが、しかし、圧倒的に多くの翻訳者は字義訳では無理だと述べている。むしろ字義直訳は悪訳の代名詞になっているくらいである。 以下にそうした例の幾つかを記す。
「直訳が忠実、など言語道断。日本語としておかしければ、それも欠陥ということになる。これも以前書いたことだが、だいたい悪訳には二つのジャンルがある。一つは原語解釈上の悪訳、一つは日本語表現上の悪訳。このうち前者は一過性の悪だが後者は慢性で根が深い、と私は考えている」(「誤訳、迷訳、欠陥翻訳」P.10、11別宮貞徳著)
「逐語訳が諸悪の根源」
「悪い逐語訳の癖のついた人が一語一語を追って読み、日本語に直すために左から右へ流れている英語を、返り点式に右から左へ逆流させるのは、読む作業を、知らずしていたずらに妨げているわけである。文章の意味に近づこうとする努力が遂に文章の意味から遠ざかる結果になっているのである」(「直訳という名の誤訳」P32、42東田千秋著)
「どうして翻訳の多くが悪文になるのか。それを考えているうちに、文順墨守がいけないのだと思うようになった。つまり、原文のセンテンスの並んでいる順序をバカ正直に守って、それを“原文忠実”なりとする考えに責任がある」(「日本の文章」P49、50外山滋比古著)
ものみの塔協会の記述を見ると「字義訳は正確で意訳は不正確」と決めてかかっているような印象を受けるが、翻訳の良し悪しは字義訳だから、意訳だからどうのということではなくて、あくまでも翻訳の理想や目標を基準にして判定されるべきである。
そもそも「字義訳は正しくて、意訳は間違っている」といったような一義的かつ狭量な見方は成立するはずがない。字義訳を宣伝しなければならないものみの塔協会の立場からすれば、そういわざるを得ないとは思うが、翻訳の評価は、翻訳本来の主旨や目標を達成しているかいないかによってなされるべきである。正確か不正確か、忠実か不忠実か、明快かそうでないかは、そうした基準から判断すべきであって、決して字義そのものの観点からだけで判定を下すべきではない。
翻訳本来の基準で考えると、
「正確、忠実」・・・言わんとしている意味の正確さであり、字句の正確さではない。忠実も同様である
「明快」・・・字句の分かりやすさではなく、意味の分かりやすさである
ということになる。
こうした基準から判断すると、字義訳は決してベストの翻訳スタイルではないということが分かる。現実は、ものみの塔協会の宣伝とはかなり異なっている。字義訳には、意訳の弊害を避けるという利点よりも、問題点の方がはるかに多いのである。
字義逐語訳、字義直訳の問題点を上げると以下のようになる。
これらの問題点は、字義訳の利点として上げられていることとは正反対になるが、新世界訳聖書にも全て当てはまるものである。ものみの塔協会の宣伝とは大いに異なり、新世界訳聖書は逐語訳の欠陥の宝庫となっている。
次章ではその具体的な事例を上げることにしよう。
原典の精神を反映すること、文章を正確に伝えることは決して一語一語の正確な翻訳によって達成されるわけではない。これは文全体の正確な意味が必ずしも、それぞれの単語の字義的な正確さによって構成されるとは限らないことによる。もちろん、文章全体の意味が一語に集約される場合は、一つの言葉が全体の意味を決定してしまうこともあるかもしれないが、そういうことはあったとしてもごく希であろう。一つ一つの単語から文全体の意味を捕えようとすると、大変な思いをするわりには、不正確で分かりにくい文章が増えることになる。おそらく英語を学んだ人なら誰でも、次の記述に思い当たることがあるに違いない。
「これに反して英語の読めない人の場合は、原文の文章全体を読み通す能力に欠けているために、ただ苦しまぎれに各語に英和辞典の訳語を引き当てながら、いわば単語の総計で全体の意味を作り上げようとするものである。数多い訳語の中から一つを選び出すには、その事前に文章全体の意味がわかっていなければならないのにかかわらず文章全体の意味を掴む能力がなければ、訳語を選択することはもちろん無理であり、全く意味をなさない訳文をでっちあげるという結果になる。これが直訳という名の誤訳である。」(「直訳という名の誤訳」P.17東田千秋著)
ここに述べられている通り、各語の意味を決定するのはあくまでも、その語の字義ではなく文章全体の意味である。まず先に単語があってそれから文章がというのではない。先に言いたいことがあり、それから単語が選ばれてくるというのが通常の順序である。しかし、字義訳では、たいてい最も確率の高い訳語が文全体に押し付けられることになってしまう。こうした字義訳のパターンは、語の意味にかなりの幅があるとき、特に問題となる。
数多くの意味を持つ語の場合、その中のどれを取るかは文脈やメッセージの内容から判断する以外にはなく、その単語の字義だけを見ていたのでは絶対に分からない。ところが、字義訳ではまず字義が優先されてしまうので、どうしても訳の分からない文章が増えてゆく結果になってしまう。正確に訳そうと努力して字義の正確さを求めることが、逆に文章全体の不正確さに、さらには、原典に対する不忠実さにつながってしまうとは、なんとも皮肉なことである。これは字義訳の弊害の中でも最大の問題点であろうと思う。
以下はその事例である。(これ以降明記のない場合はすべて新世界訳からの引用である。)
神の主な属性には、愛、公正、力、知恵などがあるが、新世界訳の次の訳文によれば、数多くの犠牲を要求するという貪欲な一面が新たに付け加えられることになろう。
「また、あなた方の中に、扉を閉じる者がだれかいるだろうか。そして、あなた方はわたしの祭壇に火を付けないー何の理由もなしに。わたしはあなた方のことを喜ばない」と、万軍のエホバは言われた。「あなた方の手からの供え物をわたしは喜びとはしない」
「"Who also is there among YOU that will shut the doors? And YOU men willnot light my altar-for nothing. No delight do I have in YOU. "Jehovah of armies has said, "and in the gift offering from YOUR hand I take no pleasure."」
この節の前の方でエホバは、汚れたパンや盲、足なえ、病気の動物を捧げていたイスラエルの民を糾弾している。
神が問題としたのは彼らの精神態度であって、決して犠牲が多いの少ないのということではなかった。犠牲の質が悪いと劣るという非難はイスラエルの民の心に向けられたものであって、決して動物に向けられたものではない。文脈からも明らかなように、エホバはもっとたくさんの犠牲が欲しいといっているのではなく、むしろ実際はその反対で、全く無価値な犠牲を捧げることをやめるようにと促しているのである。そのような犠牲を捧げるよりは、神殿の扉を閉じたほうが良いとみなすほど、神は偽善的な崇拝を嫌っておられたのである。
当然のことながら、犠牲を捧げるためにはその前に神殿の扉を開け、祭壇に火を付けねばならない。「あなた方の中に、扉を閉じる者がだれかいるだろうか。あなたがたはわたしの祭壇に火を付けないー何の理由もなしに」と訳すと、「どうして神殿の扉を閉じるのか。あなたがたは何の理由もなく犠牲を捧げようとしない」の意味になり、犠牲を捧げないことを叱責していることになってしまう。つまり、「もっと犠牲を捧げろ、もっと捧げ物をもってこい」と要求する貪欲なエホバになってしまうのである。これでは神の神性がまるで正反対である。
こういう訳が出てくる原因は、「for nothing」とその前の「will not」にある。「for nothing」には、「無益に、何の理由もなく」などの意味があるので、そのうちのどれを選ぶかによって文章は異なってくる。
「for nothing」を「何の理由もなく」、「will not」を単純否定と考えれば、新世界訳のような訳文になる。しかし「for nothing」を「無益」に、「will not」を強い拒否と考えれば、「無益なことはやめるように」という正しい訳文になる。
原語のヘブライ語にも「無益に、何の理由もなく」の両方の意味があるので所詮は解釈の問題になるが、そのすぐ後でエホバは「捧げ物を喜ばない、受け入れない」と言っているわけだから、どちらが正しいかは言うまでもないであろう。私たちの確認した範囲では、新世界訳のように訳している聖書は他にはなかった。
参考に新改訳とNIVの訳を上げておく。
「あなたがたがわたしの祭壇に、いたずらに火を点ずることがないように、戸を閉じる人は、だれかいないのか。・・・わたしは、あなたがたの手からのささげ物を受け入れない。」(新改訳)
「"Oh, that one of you would shut the temple doors, so that you would notlightuseless fires on my altar ! 」(NIV)
こういう英文であれば、誤訳は生じなかったと思うが、明確な表現を選ばなかった英語版も罪つくりである。
ヨブを慰めに来た偽善的な三人の自称友は、ヨブが性的不道徳のような隠れた罪を犯しており、苦しみにあっているのは神がそれを裁かれたためではないかとほのめかした。その節はそれに対してヨブが自らを弁明しているところである。
「契約をわたしは自分の目と結んだ。それゆえ、どうしてわたしは自分が処女に対して注意深いことを示すことができようか」
「"A covenant I have concluded with my eyes. So how could I show myself attentive to a virgin ?」
新世界訳のように「どうして注意深いことを示すことができようか」と訳すと、「そんなことはできない」と続くことになる。そうすると結局、ヨブは「処女に対して注意深くはない、言い換えれば用心、警戒していたのではない」ということになってしまう。それでは自ら不道徳を認めたも同然で、「目と契約を結んだ」と述べている前の記述と矛盾することになる。
ここで問題となるのは「attentive」という語である。ウェブスターによれば「attentive」には「paying attention (as incourting)」の意味もあるので、「処女を誘う、あるいは処女に言い寄るために(ことに)注意を払う、注意を向けることはできない」の意に解釈することもできるが、日本語の「注意深い」だけではそのように考えるのは無理である。他の翻訳では次のようになっている。
「わたしは自分の目と契約を結んだ。どうしておとめに目を留めよう」(新改訳)
「わたしは、わたしの目と契約を結んだ、どうして、おとめを慕うことができようか」(口語訳)
NIV (New International Vertion) の英文は非常に分かりやすい。
「I made a covenant with my eyes not to look lustfully at a girl」 ( lustfully : 好色に、ものほしそうに)
これなら絶対に誤訳は生じない。新世界訳の訳文ではあまりにヨブがかわいそうであろう。
この詩篇144編はダビデの作である。前半の方は、主にエホバの救いを求める祈りの歌から成っており、後半の方は、エホバを神とする民の幸いがその主題になっている。
問題なのは前半の切れ目から終わりまでの部分であるが、全部を引用すると長くなるので、以下に主な部分だけをあげることにする。
「11 異国の者たちの手からわたしを自由にし、救い出してください。彼らの口は不真実を語りました。その右手は虚偽の右手です。12 彼らは[言います]、『我々の息子たちは、その若いときに成長した小さな植物のようだ・・・・14 我々の牛はよくはらみ、裂傷もなければ流産もなく、我々の公共広場には叫びもない。15 [この]ようになる民は幸いだ!』エホバをその神とする民は幸いだ!」
「11 Set me free and deliver me from the hand of foreigners, Whose mouth has sporken what is untrue, Aud whose right hand is a right hand of falsehood, 12 Who [say]: “Our sons are like little plants grown up in theiryouth, 14 Our cattle loaded down, without anyrupture and with no abortion, And with no outcry in our public squares. 15 Happy is the people for whom it is just like [that]! ”」 Happy is the people whose God is Jehovah ! 」
新世界訳の翻訳によれば「不真実を語る異国の者=12節の彼ら、我々=15節の幸いな民、エホバをその神とする民」となる。剣でダビデを脅かし、偽りを弄して彼を欺こうとした異国の民が、何と、エホバの祝福を受ける幸いな民になってしまうのである。もっとも、敵をも祝福する寛大なダビデ、キリスト教の博愛的な精神に満ち溢れたダビデと考えれば、成り立たないこともないかもしれないが、文脈には全く合わない。この誤訳の原因は12節冒頭のヘブライ語「アシェル」の解釈にある。それを関係代名詞と取るか、それとも接続詞に取るかによって意味は異なってくる。新世界訳は関係代名詞「who」と取ったので、はなはだしい誤訳を生じさせてしまった。意味が通るように訳すには二つの方法がある。一つは新改訳、口語訳のように11節と12節をまったく分けてしまうという方法である。
「11 わたしを残忍なつるぎから救い、異邦人の手から助け出してください。彼らの口は偽りを言い、その右の手は偽りの右の手です。12 われらむすこたちはその若い時、よく育った草木のようです。・・・・13 われらの倉は満ちて様々のものを備え、われらの羊は野でちよろずの子を生み、15 このような祝福をもつ民はさいわいです。主をおのが神とする民はさいわいです。」(口語訳)
こうすると、11節の「彼ら」と12節の「われら」は同じではなく、別の人になるので矛盾は生じない。
もう一つは「アシェル」を12節以降にかかる接続詞、例えば、「in order that(ゲセニウス)」や「because」と考える方法である。「in order that(結果)」ならば、「12〜14節のような結果になります。エホバを神とする民は」となり、「because」であれば、「エホバを神とする民はさいわいです。なぜならば12〜14節のようになるからです」となる。
いずれにしても、11節の「異国の者」と12節の「彼ら」を同じ人々にすると、全体の主旨が全くおかしくなってしまうことくらいは、前後の意味を考えれば、すぐにも気が付くことではないかと思うのだが。
創世記4章10〜12には、アベルを殺したカインに対するエホバの裁きの言葉が記されている。土地が擬人化された次の一文は、12節の前半に出てくる。
「あなたが地面を耕しても、それは自分の力をあなたに返し与えはしないであろう。」「When you cultivate the ground, it will not give you back its power」
この宣言を聞いて、カインはすぐにその意味がわかったのだろうか。おそらく普通ならば、思わず首をひねってしまうところであろう。このような一回聞いただけではよくわからない難解な表現を用いると、神の呪いの宣言も効力が半減してしまう。
自分の力とは地面の力、つまり、地力のことである。簡単に言えば「土地がやせているので何の作物もできない」ということである。したがって、全体としては「あなたが地面を耕しても、もはや何の作物もできないであろう」というような訳文になる。アベル殺害の罰として、農耕者であったカインに対するふさわしい宣告であろう。いくらヘブライ語「コハー」の字義的な意味が「力」であっても、「自分の力を返し与えない」ではいかにも受験英語ふう直訳である。
口語訳は、
「あなたが土地を耕しても、土地は、もはやあなたのために実を結びません。」
と訳している。このような分かりやすい表現を選ぶのが普通であろう。新世界訳のように土地を擬人化しなければならない必然性はまったくない。
シュネムの地に住んでいたある親切な婦人は、エリシャのために屋上に一つの部屋を作ろうと思いたった。列王第二4章10節は、彼女がそのことを夫に提案している箇所の一部である。
「ぜひ、壁の上に小さい屋上の間を造り、寝いすと机といすと燭台をあの方のためにそこに置きましょう。」
「Please,let us make a little roof chamber on the wall and put there for hima couch and a table and a chair and a lampstand」
「壁」とは「家の周囲や内部の仕切り」のことであり、天井や屋根の意味は含まれていない。新世界訳翻訳委員会はいったいどうやって「壁」の上に部屋を作るつもりであろうか。壁の横に部屋をドッキングさせる、あるいは幾つかの壁を仕切りとして立て、その上に部屋をのせるというように何とか考えられないこともないが、通常の建築ではやはり、壁の上に屋上の部屋を造るのは不可能である。
広い城壁の上ならば可能であると思うが、「wall」は城壁と訳される場合、複数形になるのが通例のようである。新世界訳は、「walls」ではなく「the wall」にしているので、そのまま訳せば日本語訳のようになる。
当時、多くの家はボックス型であり屋根も壁のように平であった。それで、屋根も壁の延長と考えられないこともないが、しかし、いくら何でも日本語の場合、屋根は屋根であって壁で屋根を表わすのはやはり無理である。「wall」と訳されているヘブライ語「キール」には「外壁の表面」の意味もあるので、「上の外側の表面」すなわち「屋根」と考えることができるが、普通そういうのは屋根とはいわず「屋上」というので、ここは新改訳のように「屋上」と訳すのが適切であろう。言うまでもなく屋上であれば部屋を作るのに何も問題もない。
「ですから、屋上に壁のある小さな部屋を作り、あの方のために寝台と机といすと燭台を置きましょう。」(新改訳)
あるいは、NIVのように「屋根」にしてしまうこともできる。
「Let's make a small room on the roof and put in it a bed a table, a chairand a lamp for him」
聖書時代、屋上は様々な仕方で用いられた。「続・目でみる聖書の世界」という本は次のように説明している。
仮庵の祭りには、屋上に樹脂で仮庵を結んだ(ネヘ8:16)時には半永久的な涼みの高殿(土師3:20)、また客室も設けられた(II王4:10)。そこは涼しいので、タビタの遺体はこのような屋上の間に安置された(行伝9:37)。窓からは展望がきかなかったので、新鮮な空気を吸いたい者(IIサム11:2)、また屋外で起こった出来事を見ようとする者は自然に屋上に上がった(イザ22:1)。屋上は個人的な談合(Iサム9:25)、哀哭(イザ15:3、エレ48:38)、祈祷(行伝10:9)などの好適の場所とされた。屋上からの墜落を防止するために、屋上の周囲に欄干(らんかん)を設けるべき規定があった(申命22:8)。それは高さ2キュビト(90cm)で腰のあたりまでとどき、体重を支えるに足りる頑丈な作りでなくてはならなかった。屋根の一隅には雨水を集めて貯水槽に送るために桶が取りつけてあった。」(p.52)
この時イサクの妻リベカはヤコブとエソウという双子を身籠っていたが、やがて、子供たちは胎内で激しく争い合うようになった。創世記25章22節にはその時に彼女が語ったことばである。
「ところで、彼女の胎内の子らは互いにもがき合うようになった。そのため彼女は言った、『こんなことなら、一体何のためにわたしは生きているのでしょう』。そうして彼女はエホバに尋ねに行った」
「And the sons within her began to struggle with each other, so that shesaid :"If this is the way it is, just why am I alive ?" With that she went to inquire of Jehovah」
ここはまず「もがく」がおかしい。もがくとは、手足を動かしてもだえ苦しむこと、苦しい状態から抜け出そうとあせることの意であるが、ヤコブとエソウは別に喫煙する妊婦の胎内にいる子供のように、もがき苦しんでいたわけではない。
この胎内の出来事は、やがてヤコブから出るイスラエル人とエソウから出るエドム人という二つの国民の激しい骨肉の抗争を予表するものであった。二人はすでに胎内にいるときから争い合っていたのである。もがくでは、とてもそういう意味合いは出てこない。もっともエドムの国は後に滅んでしまったので、エソウが代表してあらかじめもだえ苦しんでいたと考えられば、預言的にもつじつまが合うとは思うが。
リベカは自分の胎内で生じているこの異常な事態を見て、それが何を意味するのか知りたいと願ったようである。そのことは、22節の終りの「彼女はエホバに尋ねに行った」という記述に示されている。
しかし、新世界訳のように「こんなことなら、いったい何のためにわたしは生きているのでしょう」とやってしまうと、普通は「いっそ死んだほうがましではないか」と続くことになる。つまり、自殺志願のリベカになってしまうのである。普通はお腹の中で子供が暴れても元気がいいくらいで、死ぬほど苦しいとは言わないと思うだがどうであろうか。おそらくこれではリベカの真意はとても伝わらないであろう。
現代訳はかなりの意訳であるが、簡潔でわかりやすい。
「ところが、おなかの子どもは双子で、お互いにけんかをしているようだったので、リベカは不安になった。『いったいどうなるのでしょう』と言って、主にお祈りした」
次に接続詞の誤用を二つほど上げることにする。
「後にロトはゾアルから上っていって山地に住むようになったが、その二人の娘も一緒であった・・・・。」そして彼、つまり彼とその二人の娘は洞窟に住むようになった」
「Later Lot went up from Zo ar and began dwelling in the mountainous region, and his two daughters along with him, So he began dwelling in a cave, he and his two daughters」
「彼、つまり彼とその二人の娘」では「ロト=ロトと二人の娘」になり、物理的には不可能な表現になる。このような例としては他にも「ヨセフ=ヨセフとその父の家」「モーセ=モーセとイスラエルの年長者たち」などがある。ロトは族を、ヨセフは父の全家を、モーセはイスラエルの年長者たちをそれぞれ代表していると考えれば、意味は成り立たないとは思うが。
英文を直訳すると、「それで彼は洞窟に住み始めた、彼と彼の二人の娘たちは」となる。普通であれば、「彼と二人の娘は洞窟に住むようになった」と簡単に訳すのであろうが、字義訳方針で削ることができない、全部訳さねばならないとなると、「彼、つまり彼とその二人の娘」というような翻訳になってしまうのであろう。硬直した字義訳主義の悲劇である。
「そして、イスラエルがその地に幕屋を設けていたときであったが、ルベンは一度、父のそばめのビルハのもとに行ってそれと寝た。そしてイスラエルはそのことについて聞いた。こうしてヤコブの十二人の息子が生れた」
「And it came about while Israel was tabernacling in that land that once Reu'ben went and lay down with Bil'hah his father'sconcubine, and Israel got to hear of it. So there came to be twelve sons of Jacob」
「こうして」という語は、前の部分を受けてその結果を表わす接続詞である。とすると、ヤコブの十二人の息子が生まれたことの要因にルベンの淫行が関係していたことになってしまう。この記述をみたらヤコブの息子たちもさぞかし驚くことであろう。ここで用いられているヘブライ語の接続詞「ヴェ」には、and, so, that, now,or, but, などさまざまな意味があるので、必ずしも「so」や「こうして」に訳さなければならないという必然性はない。
ここは次の新改訳のような訳が妥当であろう。
「イスラエルがその地に住んでいたころ、ルベンは父のそばめビルハのところへ行って、これと寝た。・・・・さて、ヤコブの子は十二人であった」
この詩篇140編は、ダビデが悪い者たちからの救出を神に願い求めている歌である。次の聖句は、邪まな者たちが彼にどんなことを行っていたかについて述べている。
「自分を高める者たちはわたしのために仕掛けを隠し、通り道のそばに綱を網として広げました。彼らはわたしのためにわなを仕掛けました」
「The self-exalted once have hidden a trap for me; And ropes they have spread out as a net at the side of the track. Snares they have set for me」
「綱」と「網」確かに漢字は良く似ているが、実物の「綱」を見て「網」という人はいないであろう。綱はいくら広げても綱で、網にするのは不可能である。もっともロープを編んで網を作るのであれば話は別であるが。
この詩編140編に出てくるワナは、網とロープが一体になったタイプのものである。次の絵はものみの塔誌(19753/1p.156)に載った当時のワナの絵である。
「net」を「網」と取って字義通り訳すと、日本語版のように「ロープを網として広げた」という変な訳になってしまう。「net」には「計略、ワナ」という意味もあるので、「綱を張ってワナをしかけた」と訳すこともできるが、しかし、明確な表現を選ばなかった英語版にも責任があろう。特に「as a net」という表現は問題になると思う。
次のNIVの訳と比べてみるとその点がよく分かる。
「Proud men have hidden a snare for me; they have spread out the cords of their net and have set trap for me along my path」
「the cords of their net」を直訳すると「アミのつな」になるが、これは当時のワナのイメージにピッタリの表現である。
ホセアは紀元前8世紀、北の王国イスラエルがアッシリア帝国に滅ぼされる直前に働いた預言者の一人である。彼は、道義的にも霊的にも腐敗していたイスラエル王国をぶどうの木に例え、次のように述べた。
「イスラエルは衰退してゆくぶどうの木。彼は自分のために実を付けてゆく。その実が満ちあふれるにしたがって彼は[自分の]祭壇を多くした。その土地が良いので彼らは良い柱を立てる」
「"Israel is a degenerating vine. Fruit he keeps putting forth for himself. In proportion to the abundance of his fruit he has multiplied [his]alters. In proportion to the goodness of his land, they put up good pillars」
「衰退する」とは「おとろえて勢いがなくなること(学研国語大辞典)、おとろえくずれること、おとろえ退歩すること(広辞苑)」という意味である。したがって、「衰退してゆくぶどうの木」といえば、「おとろえ、くずれ、枯れてゆくぶどうの木」ということになってしまう。ところが、次に「実を付けてゆく」「その実が満ちあふれる」と続いているので、このぶどうは、枯れてゆくのにたくさんの実を付けるという実に摩訶不思議な木になってしまうのである。
日本語版が「衰退する」と訳している元のヘブライ語「バーカク」は、衰退するどころかそれとは全く反対の意味を持つことばである。たいていの辞書は「beluxuriant」(繁茂する、生い茂る)「spreading」(広がって行く、伸びて行く)などの訳語を当てている。
ホセアが預言したころ、滅びが間近に迫っていたイスラエル王国は末期症状の状態にあった。偽り、偽証、殺人、淫行といった背教の腐った実が国中に広がっており、偶像崇拝の祭壇がいたるところに築かれていた。事態はもはや癒しようのないレベルまで進んでいたのである。ホセアはそうしたイスラエルの状態を生い茂ってゆくぶどうの木に例えた。イスラエルは決して衰退してゆくぶどうの木ではなく、腐った実を豊かに実らせるぶどうの木であった。
もっとも偶像崇拝が盛んになるということは逆に真の崇拝が衰えてゆくということなので、日本語版が真の崇拝という意味でイスラエルを衰退してゆくぶどうの木に例えたのであれば一応意味は通る。ただしそれだと、裁きの預言との呼応関係が完全に壊れてしまうので、文脈にはまったく合わなくなってしまう。
確かに、英語版の「degenerate」は「衰える、衰退する」なので、そのまま訳せば日本語版のようになる。しかし、「degenerate」にはその他にも「堕落する、変質する」などの意味があるので、「イスラエルは堕落する(変質する)ぶどうの木」というふうに訳すこともできるが、英語版が何故わざわざ誤解を招きやすい表現を選んだのかは理解に苦しむ。
次の節も前の10章1節と同じように、ホセアがイスラエルの悪行を糾弾しているところである。
「8 ギレアデは有害な事柄を行う者たちの町。その足跡は血である。9 また、祭司のともがらは、人を待ち伏せしているかのようであり、略奪者の群れとなっている。路傍で、シェケムで、彼らは殺人を犯す。彼らはただみだらな行いをしてきたのである」
「8 Gil'e. ad is a town of practicers of what is harmful; their footprints are blood. 9 And as in the lying in wait for a man, the association of priests aremarauding bands. By the wayside they commit murder at She'chem, because they have carried on nothing bet loose conduct」
「ともがら」とはいうまでもなく、仲間のことである。したがって新世界訳の翻訳では、略奪行為をしていたのは「祭司そのもの」ではなく、祭司のともがらすなわち「祭司の仲間」ということになってしまう。
しかし、ここは祭司の「仲間」が殺人や淫らなことを行っていたというよりは、祭司たちが「自ら」そういう行為を行っていたと考える方が文脈に合う。本来は公正な裁きやいやしを行うべき立場にいた祭司たちが、むしろ率先して、徒労を組んで略奪行為をするほど腐敗、堕落していたということである。
辞書を見ると「ともがら」と訳されている英語の「association」には、まず「団体、会、組合」というような訳語がのっている。また、仲間の意味では「association」よりも「associate」を用いるのが普通のようなので、日本語版がなぜ「ともがら」という訳語を選んだのかはよく分からない。
確かにもとのヘブライ語「ヘベル」には仲間という意味があるので、ともがらで良いといえばそういえないこともないとは思う。が、しかしヘベルには「一体、一団、一行」という意味がはっきりあるわけだから、もっと文脈を考えて訳語を決定すべきであろう。
ここは新世界訳のように「association」を用いるよりも、NIVの次の訳の方がはるかに分かりやすい。
「9 As marauders lie in ambush for a man, so do bands of priests; they murder on the road to Shechem, committing shameful crimes」
古代の祭司たちは腐敗の元凶になっていた。はたして、現代の自称「祭司たち」はどうであろうか。
エレミヤはバビロンにいる流刑の民、第一次補囚でエルサレムから連れ去られた人々に手紙を書き送り、エルサレムは滅びること、その荒廃の期間は70年に及ぶことなどを伝えた。ところがこの時バビロンにはエレミヤに敵対する偽預言者たちがいた。次の節はそうした二人の預言者について語ったものである。
「21 イスラエルの神、万軍のエホバは、わたしの名によってあなた方に偽りを預言しているコラヤの子アハブに関して、またマアセヤの子ゼデキヤに対してこのように言われた。『いまわたしは彼らをバビロンの王ネブカドネザルの手に渡し、彼は彼らをあなた方の目の前で必ず打ち倒す。22 そして彼らから、バビロンにいるユダの流刑者の全員によって呪いが取られる。こう言うのである。「エホバがあなたを、バビロンの王が火で焼いたゼデキヤやアハブのようにされますように!」
「21 This is what Jehovah of armies, the God of Israel, has said concerning A'hab the son of Ko lai' ah and to Zed・e・ki'ah the son of Ma・a・sei'ah, who are prophesying to YOU falsehood in my own name, 'Here I am giving them into the hand of Neb・u・chad・rez’zar the king of Babylon, and he must strike them down before YOUR eyes.」 22 And from them a malediction will certainly be taken on the part of the entire body of exiles of Judah that is in Babylon, saying; "May Jehovah make you like Zed・e・ki'ah and like A'hab, whom the king of Babylon roasted in the fire!"」
22節の「彼ら」は偽預言者のアハブとゼデキアを指している。それで日本語版の訳文どおりに考えてゆくと、「呪いがかけられているのは彼ら偽預言者、そしてその呪いは彼らから取られる、それはユダの流刑者全員によって」ということになる。言い換えれば、偽預言者の上にある呪いをユダの流刑者が全員で取り去ってあげるという意味になってしまう。 しかし、そのすぐ後に続く言葉はまさに彼ら偽預言者に対する「呪いそのもの」であり、しかも、その呪いの言葉を語るようになるのはユダの流刑者たちなので、この翻訳では文意が前後で矛盾してしまう。
問題は「彼らから取る」という部分であるが、同じ取るでも「take」には「〜から取ってくる」とか「〜から引用する」というような意味がある。例えば、プログレッシブ英和中辞典には次のような例文が載っている。
The hero was taken from life.(主人公は実在の人物をモデルにしたものである)
The book takes its title from Dante.(その本の書名はダンテからとったものである)
それで英語の takeを「取る」と考えるにしても、日本語版のように「呪いを取り去る」ということではなく、彼ら偽預言者から「エホバがあなたを・・・・のようにされますように」という呪いの言葉が取られる、つまり、二人の偽預言者がそうした呪いの言葉の起源になるというふうに解釈すれば、意味は通ると思う。が、しかし実に分かりにくい表現ではある。
ここは新改訳のような次の訳が妥当であろう。
「22 バビロンにいるユダの補囚の民はみな、のろうときに彼らの名を使い、『主がおまえをバビロンの王が火で焼いたゼデキヤやアハブのようにされるように。』と言うようになる」
最後に傑作を一つ。
この「タコを忍ぶ人」は新世界資料付き聖書の脚注の中に登場する。本文の方は次のようになっている。
ロマ7:15または、「自分の意図する」。24「実に惨めな」。字義、「[皮膚の]たこを忍ぶ」。「わたしは実に惨めな人間です!こうして死につつある体から、だれがわたしを救い出してくれるでしょうか」
「Miserable man that I am ! Who will rescue me from the body undergoing this death ?」
パウロはこの24節の前の方で、自分の中に働く二つの律法、すなわち思いの律法と罪の律法について述べている。
内面では神の律法を喜んでいるのに、肉体は罪の律法に支配されている。戦いは罪の力の勝利に終り、結果として罪のとりこにされてしまう。パウロが「実に惨めである」といって嘆いているのはこうした状態のことである。
参照資料付き聖書の脚注によれば、この「実に惨めな」の字義が「[皮膚の]たこを忍ぶ」であると説明されている。体のどこにたこができていたのかは分からないが、パウロは「たこを忍ぶ人」であったわけである。よほどタコに悩まされていたのに違いない。
さて、文脈から明らかなように、パウロがここで論じているのは、肉と霊の戦い、そして罪の力からのキリストによる救いという人間の本性、およびキリスト教の本質に関するきわめて重要な側面である。「わたしは実に惨めな人間です!」と記されてはいるが、この記述はパウロ個人に関してというよりは、むしろ人類一般の抱えている状況について述べられたものと解釈されている。人はだれもみな罪の力に悩まされるからである。
したがって、いくら字義とはいってもこういう論議の中に、皮膚のたこのような個人的な問題が出てくるとはちょっと考えにくい。というのは、すべての人が「たこ」に悩まされているとは限らないからである。
[たこを忍ぶ]と訳されている英語は[callus-bearing]である。[callus]をたこ[bearing]をがまんする、辛抱する、忍耐すると取ると、[callus-bearing]で「たこを忍ぶ」になる。しかし、[callus]を皮膚硬結、[bearing]を生じる、抱えると考えれば、「皮膚硬結を抱える、あるいは持っている」と訳すこともできる、がやはり、たいして意味は変わらない。
かなり無理をして、「皮膚硬結」を老化現象によるものと仮定すると「人はみな年を取ると皮膚がこわばりカサカサになってゆく」という意味に考えられないこともない。それだと「実に惨めな状態です!」と嘆くこととも合うかもしれないが。
新世界訳聖書の一つの大きな特徴は、ヘブライ語やギリシャ語のある特定の言葉に対して同一の訳語が当てられているということである。こうした翻訳の統一性について「霊感」の本327頁7節は次のように述べている。
「新世界訳」はその翻訳に一貫性を保つようあらゆる努力を払っています。ヘブライ語やギリシャ語の特定の言葉に対して同一の訳語が当てられ、その訳語は慣用または文脈の許す限り、十分理解できる範囲内で統一的に用いられています。例えば「ネフェシュ」というヘブライ語の言葉がありますが、これは一貫して「魂」と訳されています。「プシュケー」というギリシャ語の言葉も、その出てくるすべての箇所で「魂」と訳されています。
このように訳語を統一することには、一体どんな利点があるのだろうか。幾つかの点が考えられるが、まず聖句の相互参照に役立つ、索引を使って聖句を捜すときに便利であるといったことが言えると思う。これは1章では字義訳が選ばれた理由の一つとして上げておいた。
その他には、似たような概念ではあっても厳密な意味分けを必要とする場合などがあると思う。そういうとき訳語の統一は確かに威力を発揮することになる。「霊感」の本にはそのことを示す次のような経験が載せられている。
「新世界訳」の一貫性は、野外で行われた聖書の専門的な討論で幾度も勝利を収めるものとなってきました。ある時、ニューヨークの自由思想家たちの一教会が、そのグループに二人の講演者を派遣して聖書について話してもらいたいと、ものみの塔教会に要請し、その要望が受け入れられました。それらの学者たちは、“ファルスムインユーノーファルスムイントートー”つまり一つの点で偽りと証明された議論は全体が偽りであるというラテン語の格言を信じていました。その討論の際、ある人が聖書の信頼性に関してエホバの証人に挑戦しました。彼は創世記1章3節を聴衆のために読むよう求めたので、「新世界訳」からその節が読まれました。「それから神は言われた、『光が生じるように』。すると光があるようになった」。次に、彼は自信満々の態度で創世記1章14節を読むよう求めたので、その句も「新世界訳」から読まれました。「次いで神は言われた、『天の大空に光体が生じて・・・』」。すると彼は言いました。「待ちたまえ。君は何を読んでいるのかね。わたしの聖書は、神が第一日に光を造り、第四日にも光を造ったと述べているのだが、これは矛盾している」。当人はヘブライ語を知っていると言ってはいましたが、3節で「光」と訳されているヘブライ語は「オール」であるのに対し、14節の言葉はそれとは違って、「光体」という意味の「メオーロート」であることが指摘されなければなりませんでした。この学者は敗北して腰を下ろしました。「新世界訳」が忠実に一貫性を保っていることがこの問題で勝利を得、聖書が信頼できる有益なものであることを擁護するものとなりました。(P. 327,328)
この経験はかなり宣伝の色彩が濃いようにも思えるが、訳語を統一することには確かにこのような利点もあるに違いない。新世界訳翻訳委員会が字義訳のメリットを十分考慮し、それなりの根拠を持って翻訳の一貫性を決定したことは、間違いのないことであろうと思う。
しかし、見逃してならないのは言葉と文化の関係である。文化が異なれば物理的には同じような内容を指す言葉であっても、その語の持つイメージは異なってくる。つまり、象徴的な意味合いの格差は激しくなるのである。「greenhorn」は「青二才」「bule film」は「ピンク映画」である。また、日本語の「犬」には動物としての犬の他に、「まわしもの、スパイ、権力の手先」の意味があり、さらには「犬死に」や「犬侍」などの用法もあるが、英語にはそのような用法はない。逆に「bitch」(雌犬)で「淫婦」を表すような言い方は日本語にはない。
この文化の違いによる語の意味の格差は、名詞だけでなく動詞にもまったく同じように当てはまる。例えば、日本語の「打つ」には字義的な意味の「たたく」の他にも様々な慣用表現、「相槌を打つ」「注射を打つ」「庭に水を打つ」「電報を打つ」「芝居を打つ」「心を打つ」「句読点を打つ」などがある。しかし英語の「hit」にはそうした意味はないので、他の動詞「agree」「inject」「sprinkle」「telegraph」「play」「impress」「punctuate」で表現することになる。逆に「hit」の持つ「頼む、当たる、出くわす、ぴったりする、(魚が)餌に食い付く」といったような意味は日本語の「打つ」にはない。このような例は上げてゆけば切りがないと思う。
さらに、同じ表現であっても場面や状況によって意味が異なってくるという問題がある。外人が戸惑う例としてよく上げられるのは、「いいです」という言い方である。どういう場合が「イエス」で、どういう場合が「ノー」か日本人なら何の造作もなく識別できることが、外人にとって非常に難しいというのはやはり文化の違いによる。伝道している宣教者が「いいです」と断られたのに、家の人が奥の方に引っ込んでも玄関でずーっと待っていたというのは有名な話である。
このように二、三の事例を考えてみただけでも、言葉と文化とは決して切り離すことのできないものであるということがよく分かる。すべての言葉はその民族の歴史や文化を引きずってきており、文化を抜きにした言葉というものはありえない。まさに言葉とは、同時に文化そのものであるともいえる。現在、コンピューターによる機械的な翻訳はごく限られた領域でしか使えないと言われている。それはコンピューターに文化を教えることがいかに困難なことかを物語るものである。コンピューターにとって自然原語を理解することが極めて難しいというのは、言葉の意味が逐語的な対応関係よりも文化的な背景で決定されることの方がはるかに多いということの強力な証拠でもある。翻訳が単なる字義的な言葉の移植ではなく、文化の移植といわれるのはそうした理由による。ものみの塔協会は、
「また、翻訳の忠実さは、それが字義訳であるという点にも明示されます。それには、英語とヘブライ語およびギリシャ語本文との間にほとんど逐語的とも言うべき対応関係がなければなりません」(「霊感」P.325)
と述べているが、それは所詮文化の相違や背景を無視しない限り土台無理な話しである。「慣用または文脈の許す限り、十分理解できる範囲内で」という条件を付けてはいるが、あえて平衡を欠くほどに訳語を統一しようとするとどうなるかは、次に見るとおりである。
5つのヘブライ語「アダム」「エノシュ」「イーシュ」「ギベル」「ザカル」はいずれも「人」と訳されている言葉であるが、新世界訳はこれらの語を申し分けている。ものみの塔誌1982年6月15日号は、その点について次のように述べている。
「新世界訳独自の特色として推奨できる別の点は、普通は「人」と無差別に訳出されている五つのヘブライ語の言葉を申し分けている点です。これらの言葉の意味には相違があり、ヘブライ語聖書の筆者たちはその相違を認めていました。ですから、新世界訳は、元の意味と調和させて、アダムという語を「地の人」と訳出し、地の創造物として言及しています。エノシュという語は「死すべき人間」と訳されています。これは人間の取るに足りない、弱い状態を強調しています。ギベルという語は「強健な人」と訳されています。このヘブライ語は力のある人を意味しているからです。イーシュという語は単に「男」と訳されています。これはイッシャーつまり女と区別するものであり、単に人を意味しています。また、新世界訳はザカルという語を「男性」と訳しています。この語は普通、性関係との兼ね合いで用いられるからです」(P.27)
整理すると
| 「アダム」 | ・・・ | 「地の人」 |
| 「エノシュ」 | ・・・ | 「死すべき人間」 |
| 「ギベル」 | ・・・ | 「強健な人」 |
| 「イーシュ」 | ・・・ | 「男」 |
| 「ザカル」 | ・・・ | 「男性」 |
となる。
もちろん新世界訳も同じヘブライ語が用いられているすべての箇所で、一貫してこのように訳しているわけではないから、意味上の問題が生じる聖句の数はそんなに多くはない。それでも不自然な印象を与える聖句となると、かなりの数に上る。以下、その中で特にアダム、エノシュ、ギベルの三つについて取りあげることにする。
最初の人アダムは地の塵から造られたので、確かに「地の人」という表現は彼にピッタリする訳語である。また「地の人」には「地から取られた、地に住む」といったイメージがあるので、創造物としての人間を表すにも適した表現である。
しかし、アダムというヘブライ語のすべてをどうしても「地の人」と訳さなければならない必然性はない。多くの辞書は、アダムの語源について確かなことはいえないと述べている。特別に、何か「地の人」に込められた意味合いを出したいときに用いる程度でよいのではないかと思う。
例えば、次のような場合である。
「そしてアッシリア人は、人間[のもの]ではない剣によって必ず倒れる。地の人[のもの]ではない剣が彼をむさぼり食うであろう」(イザヤ31:8)
アッシリア人は「人間ではなく神によって裁かれる、地上の人間ではなく天が滅ぼすのである」という意味を強調したいときは、天に対して地なのでこのイザヤ書31章8節のように「地の人」という表現には十分な効果がある。
しかし、次のような場合はかえって逆効果であろう。
「そして、地の人は身をかがめ、人は低くなります。あなたが彼らを赦すことはありえません」(イザヤ2:9)
「地の人」と「人」を彼らにしているので、「地の人」と「人」は異なるのかという疑問を生じさせる。
「そしてエラムは、乗用馬[の引く]地の人の戦車の中で矢筒を取った。キルも盾の覆いを外した」(イザヤ22:6)
わざわざ「地の人の戦車」とすると、戦車の中には他の人のものではない戦車もあるのかとの印象を与えてしまう。もちろん、天の戦車のような象徴的な意味ではなく。 批判的な目で見ればまだいろいろとあるのかも知れないが、無理して考えなければ、アダムにはそれほど大きな問題はない。せいぜいニュアンス程度のことである。むしろ、問題なのはアダムよりもエノシュの方である。
ものみの塔誌はエノシュという語が「人間の取るに足りない、弱い状態を強調している」と説明しているが、この語の語源も、やはりよく分からない、はっきりとは断定できないというのが実状のようである。旧約聖書神学用語辞典(ハリス、アーチャー、ウォルトケによる)はエノシュについて次のように述べている。
「エノシュの語源は、はっきりとは分からない。もし、'anash:病んでいる、病気である'から派生したのであれば、基本的には人の弱さや死を避けることのできない運命などが強調されることになる。幾つかの聖句では、人間の取るに足りない低い状態を表わす言葉としてこの語を用いている。(詩編8:4,ヨブ7:17)あるいはこの語は他の語根('ns)から出ているかもしれない。ただし、ヘブライ語の文献にはなく、アラビア語やウガリト語の文献にその使用例が見られる程度である。アラビア語では友好的、社交的であること、そしてウガリト語では同様の概念の親しみやすさを表している。もしエノシュがこの語根から出ているのであれば、エノシュが強調しているのは社会性を持つものとしての人間である。」
このように「エノシュ」にも意味上の幅があるので、全部のエノシュを完全に「死すべき人間」で統一しきれるわけではない。だから、あるところは「死すべき人間」とは訳せないところもある。
最初に、新世界訳がエノシュを「死すべき人間」とは訳さなかったところを紹介しよう。
「わたしが夜の幻の中でずっと見ていると、見よ、天の雲と共に人の子のような者が来るのであった。その者は日を経た方に近づき、彼らはこれをその方のすぐ前に連れて来た。」(ダニエル書7:13)
この聖句はメシアに関する非常に重要な予言の中の一節である。「人の子」はイエス・キリストを、「日を経た方」はエホバをそれぞれ指している。この預言はキリストがエホバの王座の前に連れてこられ、神の王国の王として即位する時の天の光景を描写したものである。ものみの塔協会は第一次世界大戦の始まった1914年に、この預言が天で成就したと説明している。
エノシュが用いられているのは「人の子」の人に相当する部分である。新世界訳の誇る字義訳の方針で全部訳せば、単に「人の子」ではなく「死すべき人の子」と訳さねばならないことになる。しかし、さすがに字義訳新世界訳もイエス・キリストを「死すべき人の子」とはできなかったようである。
もう一つだけこの例として、列王第二2章16節を上げることにする。
「次いで彼らはこう言った。『お願いです、この僕どもと共に五十人の者、勇敢な者たちがおります。どうか、彼らを行かせ、あなたのご主人を捜させてください。エホバの霊が彼を引き上げて、ある山の上か、ある谷に彼を投げたのかもしれません』。ところが彼は言った、『あなた方は彼らを遣わしてはなりません』。」
エリヤが風に運ばれてどこかへ連れ去られてしまったので、同僚の預言者たちがエリシャに主人のエリヤを捜しに行くことを提案しているところである。これは預言の職務が、エリヤからエリシャに引き継がれる際に生じた出来事の一つである。
この聖句の中でエノシュが使われているのは、「五十人の者」の「者」のところであるが、エノシュに死すべき人間を入れて訳すと、「五十人の死すべき人間、勇敢な者たち」という珍妙な翻訳になってしまう。ここはさすがに新世界訳翻訳委員会もすぐに気が付いたものと思われる。
次に「死すべき人間」を入れて訳しているところで、変な意味になる聖句を二つ上げる。
「そうではなく、それはわたしと並ぶ者であった死すべき人間、わたしの親密な者、わたしの知己であったあなただったのだ。」(詩編55:13)
この詩編は、ダビデが息子アブロサムの反逆に遭う、エルサレムから追われてしまった時のことを歌ったものとされている。わたし、つまり、ダビデを裏切り敵になってしまったのは、わたしと並ぶ者、同僚、親友であったとダビデは述べているのである。裏切ったその親友とはアヒトフェルであると考えられているが、彼がいかに重要な人物であったかは次の記述に良く示されている。
「そのころ、アヒトフェルが進言した助言は、人が[まことの]神の言葉を伺うときのようであった。すべてアヒトフェルの助言は、ダビデにとってもアブサロムにとってもそのようであった。」(サムエル第二16:23)
この聖句からよく分かるように、ダビデはアヒトフェルが裏切る前は彼を神のように信頼していたのである。したがって、裏切った後であれば「死すべき人間」というのもうなずけるが、裏切る前に「死すべき人間」というのは変である。というのは、口語としての「べき」は「当然だという話し手の意志や意見、当人に負わされている義務」を表すからである。
詩編55:13を読めばすぐ分かるように、ここはかつての関係について述べているところである。神のように信頼されていたアヒトフェルが「死んで当然の人間であったとか、死ぬことが定められていた人間であった」というのは絶対におかしい。
次の表現は意味不明である。
「わたしが−わたしがあなた方を慰めている者なのである。死んでゆく死すべき人間を恐れ、ただの青草のようにされる人間の子を[恐れる]とは、あなたはだれなのか」(イザヤ51:12)
聖句全体では、「わたし、エホバがあなた方イスラエルの民を慰めている者なのに、どうしてやがては死んで行く草のような人間を恐れ、神に信頼を置こうとしないのか」という意味であろう。イスラエルの民は神よりも周囲の強国、エジプトやアッシリア、バビロンなどにより頼み、しばしばエホバに叱責されている。
ここで問題となるのは「死んで行く死すべき人間」という表現であるが、「死んで行く人間」か「死すべき人間」であれば意味ははっきりしている。しかし、「死んで行く死すべき人間」では、言わんとしていることは分からないわけではないが・・・「やがて死んで行く死んで当然の人間」(そういう人を恐れる必要がないのはあたりまえのことである)「死につつある死に値する人間」(もっと恐れる必要がない)・・・やはりどう考えてみても、なぜ「死んで行く死すべき人間」にしなければならないかはよく分からない。イスラエルの民の不信仰を、とりわけ強調したいというのであれば意味は通るかもしれないが、ここは一般的な形の方がより文意に合うと思う。
このように「べき」を使って「当然である、定めである」というニュアンスを含めると、不自然な印象を与える聖句はかなりの数にあがる。おそらく、意味合いまでおかしくなってしまうような聖句も、捜せばまだまだあると思われる。
「ガーバル」(力強い、強力である)「ゲブーラー」(力)「ゲビーラー」(貴婦人、女王)、これらはみなギベルの同族語である。
先に引用した「旧約聖書神学用語辞典」によれば、「ギベル」は通常、より一般的な用語、アダムやイーシュ、エノシュとは異なり、権力や体力などが最も意気盛んな状態にある男性、あるいはそういうレベルにいる男性を指しており、「力量があり有能な人」を表すと説明されている。そういう意味では、新世界訳の訳語、「able-bodied man」「強健な人」というのは、ギベルの字義を十分反映したものといえる。
ただし、ここでも問題になるのは、あらゆる場合に「力のある人」という字義で統一して訳してよいのかどうかという点である。このギベルはアダムやエノシュと比較すると、特殊な意味合いが強いとはいえ、間違いなくその字義しかないのかというとどうもそうではないようである。
新世界訳委員会もやはり絶対的であるとは考えなかったようで、すべてのギベルを強健な人と訳してはいない。問題となる聖句の数はそれほど多くはないが、しかしそれでも、状況はアダム、エノシュの場合と似通っている。
以下にそうした例を二つ上げることにする。
最初は詩編88編4,5節。
「4 わたしは穴に下る者たちの中に数えられました。わたしは力のない強健な者のようになり、5 埋葬所に横たわる打ち殺された者のように、死者の中に放たれました。」
この詩編はコラの子たちが自らの置かれていた絶望的な状態について歌ったものであるが、その中の一節に「力のない強健な者」という表現が出てくる。英語版も
「I have become like an able-bodied man without strength」
となっているので、確かにそのまま訳せば「力のない強健な者」になる。
「力のない」も「強健な」も共に「者」にかかっているので、素直に考えると「力のない強健な人」とは「力のない、力強い人」ということになり、それは一体どんな人なのだろうかということになってしまう。
意味としては、有能で力強かった人が絶望的な状態ゆえに、力がなくなってしまったということなので、「力のない人のようになった」とか「力が尽きてしまった」といった表現の方が正しい。
次はエレミヤ記22章30節。
「エホバはこのように言われた。『この人を子のない者、一生成功することのない強健な者として書き記せ。成功を収め、ダビデの王座に座して、これ以上ユダで支配する者は、彼の子孫からは一人もでないからである。』」
「This is what Jehovah has said,‘Write down this man as chidless, as an able-bodied man who will not have any successin his days; for from his offspring not a single one will have any success, sitting upon the throne of David and ruling anymore in Judah’」
「必ずしも速い者が競争に勝つのではなく、また力の強い者が戦いで勝利を収めるのでもない。予見しえないことは全ての人に臨む」と伝道の書9章11節は述べているので、強健な人が人生で失敗しても別に不思議ではないが、一生成功しないのに「強健な人」というと、やはり変な感じがする。強健な人であれば、一度くらいは成功してもよさそうなものある。
エホバがこのように宣告しているのは、ユダの王エホヤキンについてである。彼はまもなくネブカデネザルに捕らえられ、バビロンに連れて行かれることになるが、この時は王位についている強健な人なので一生というのはどうしてもおかしい。
五種類の人を訳し分ける一試みとしては決して悪いことではないと思う。むしろ、より正確な意味に近づこうという努力としては、積極的に評価できることかも知れない。ただ、あくまでも語根の意味を含めるか含めないかは、全体との関係で、文脈や言わんとしている主旨との関係で決定すべきであろう。字義が優先され、ある特定の字義が意味上の支配者になるようなことがあってはならない。
かなりの意訳で正確さではあまり信頼を置くことができないとは言われているが、世界最初の聖書翻訳である「ギリシャ語70人訳」は、新世界訳のようなレベルでの「人」の申し分けは行っていないということを付け加えておく。
ここには様々な玄関が登場する。少し長いが全文を引用することにする。
「6 また、“柱の玄関”を彼は造った。その長さは五十キュビト、幅は三十キュビト。その前にはひさしがあった。7 彼が裁きを行うことにしていた“王座の玄関”については、彼は裁きの玄関を造った。人々はそれを床から垂木に至るまで杉材で覆った。8 彼が住むことになっていた、ほかの中庭のその家には“玄関”に属する家から離れていた。それは造りの点でこれと同様であった。また、ソロモンが自分のめとったファラオの娘のために建てた、この“玄関”のような家があった」
さて、言うまでもなく「玄関」とは「建物の正面にある入り口」のことである。それで、上の聖句に出てくる玄関をそういうふうに考えてみると、次のようになる。
このようにいうと「柱だけでできている玄関」という感じになってしまうが、はたしてそのような玄関があったのだろうかという疑問がわく。
これはもう意味不明である。まさか二間続きの玄関ということではないであろうし、仮に続いているとしても普通は一つの玄関と言う。
ソロモンの王座は玄関にあったのだろうか、また、ソロモンは玄関に出てきて裁きを行ったのだろうかという疑問が生じる。
こうはまず言わないのではなかろうか。普通は、家が玄関に属するというのではなく、玄関が「家」に属しているという。それともソロモンの住んでいたのは「途方もなく大きな玄関に付随していた小さな家」・・・ちょっと考えられないことである。
予算の都合で玄関のような家しかできなかった、それでファラオの娘は仕方なく玄関のような家に住むことを余儀なくされた・・・・栄華を極めたソロモンのことだから、こういうことはありえない。また、ソロモンの不興を被って、玄関のような家に入れられていたというわけでもない。
ここはソロモンの建てた壮大な建築物について述べているところである。宮殿、広間、玄関と訳し分けると別に問題はないが、新世界訳のように訳語をすべて「玄関」に統一してしまうと不思議な建て物が出現するという結果になってしまう。
原文のヘブライ語本文を見るとこの“玄関”に当たるところがすべて「ウーラーム」、またはその変化形になっている。新世界訳委員会は英文にする際、それをことごとく「Porch」と訳した。そのため英文に忠実な日本語版も広間や入り口をすべて“玄関”にしたようである。
ここで用いられている「ウーラーム」は「Porch」以外にも「hall, palace, portico :前廊、柱で支えられた屋根付きの玄関」などの意味がある。この6〜8節の中で“玄関”と訳せるところは日本の文化から言えば、一つしかないだろう。
参考に口語訳の訳文を上げておく。
「6 また柱の広間を造った。長さ五十キュビト、幅三十キュビトであった。柱の前に一つの広間がありその玄関に柱とひさしがあった。7 またソロモンはむずから審判をするために玉座の広間、すなわち審判の広間を造った。床からたるきまで香柏をもっておおった。8 ソロモンが住んだ宮殿はその広間のうしろの他の庭にあって、その造作は同じであった。ソロモンはまた彼がめとったパロの娘のために家を建てたが、この広間と同じであった」
広辞苑には、「気遣い」とは「あれこれと心を使うこと、心づかい、気がかり、心配」とあるが、今は主に他の人のために心を配るときに用いるのが普通であろう。「心配だ」というとき「気遣いだ」とは言わないし、「気がかりです」というのも「気遣いです」とは言わない。 こういう「心配り、心づかい」という意味で「気遣い」の統一を見てみると、特にヨブ記に互いに矛盾する箇所や妙な表現が多いのに気付く。次に上げたのはそうした聖句の中の代表的なものである。
「わたしの寝床はわたしを慰め、わたしの床はわたしの気遣いを支えるのを助けてくれる」
「My divan will comfort me, My bed will help carry my concern」(ヨブ7:13)
「わたしの魂は自分の命に対して確かに嫌悪を感ずる。わたしは自分についての気遣いを漏らそう。わたしは自分の魂の苦しみのうちにあって語ろう!」
「My soul certainly feels a loathing toward my life. I will give vent to my concern about myself. I will speak in the bitterness of my soul !」(ヨブ10:1)
「ところが、あなたは、神の前に恐れを無力にさせ、神の前に気遣いを抱くのを少なくする」
「However, you yourself make fear [before God] to have no force ,and you diminish the having of any concernbefore God 」(ヨブ15:4)
「今日もまた、わたしの気遣いの様子は反逆であり、わたしのこの手は嘆きのゆえに重い」
「Even today my state of concern is rebelliousness; My own hand is heavy on account of my sighing 」(ヨブ23:2)
まず、7章13節の「わたしの気遣いを支える」という訳文であるが、分かりにくいのは「わたしの気遣い」という表現である。これだと自分を気遣っている(心配している)のか、それとも誰かを気遣っている(心遣い)のかよく分からない。加えて、「支える」の主語はわたし、つまり、ヨブなので、文意はヨブが自分で自分の気遣いを支えているということになる。何とも妙な文章である。ヨブの状況を考えると、ここはロバート・ゴルディスによる私訳のように「嘆き」か「苦悩」を用いる方がよい。
「わたしの臥所(ふしど)がわたしを慰め、わたしの寝床がわたしの嘆きの重さを共にしてくれる」
ヨブ15章4節テマン人エリパズがヨブを非難しているところである。このエリパズという人は、ヨブを慰めにやって来た三人の偽善者のうちの一人であった。
15章4節を読むと明かなように(ただし、神の前に恐れを無力にさせるというのは何のことかよく分からないが)、エリパズの「気遣いを抱くことを少なくする」という言葉は、ヨブに対する非難であることが分かる。このことからすれば、当然のことながらヨブは「神のことをあまり気遣ってはいなかった」ということになる。
ところが、10章1節の「わたしは自分についての気遣いを漏らそう」(続く2節で『わたしは神に申し上げることにする』と述べているので、この気遣いは神に向けられたものであることがわかる)、23章2節の「今日もまた、わたしの気遣いの様子は反逆であり」から分かるように、ヨブは自分から進んで気遣いを漏らしており、しかもそれは毎日のことであったと考えられる。一方で「少なくする」と非難し、他方で「毎日のように多い」という。これは明らかな矛盾である。
付け加えると、このときヨブは公正な裁きを求めてうめいており、自分の忠誠を証明することに心を砕いていた。そうした状態が、いわゆる「気遣う」素振りでやって来た三人の友には、神に対する反逆に見えたということであって、別にヨブが気遣っていたわけではない。極度の苦悩を気遣いなどとされたら、それこそヨブの苦悩が深まることになろう。
10章1節は、ちょっと代名詞がくどいとは思うが、新世界訳とは対照的なゴルディスの私訳を上げておく。
「わたしはわたしの生命がいやでたまらない。
わたしはわたしの不満の手綱を手放そう。
わたしはわがたましいの苦痛のままに語ろう」 「君は敬虔の念をそこない
神との交わりを減らしている」(ヨブ15:4)「わが嘆きが今になお反抗的であるにもせよ、
わが上に置かれた神の手はわが呻きより重い」(ヨブ23:2)
ここで用いられているへブライ語は「テホーム」である。テホ−ムには「大海、深海、深淵、混沌、計り知れないもの、大量の水」などの意味があるとされているが、新世界訳はそのほとんどを「水の深みと訳している。最初に出てくるのは創世記1章2節である。
「さて、地は形がなく、荒漠としていて、闇が水の深みの表にあった。そして、神の活動する力が水の表を行きめぐっていた」
「Now the earth proved to be formless and waste and there was darkness upon the surface of [the] watery deep ; and God's active force was moving to and fro over the surface of the waters」
ここの訳でまず問題となるのは「荒漠」という言葉である。このとき創造の第一日はまだ始まっていない。陸地はなく、地球全体は水に覆われたままであった。ところが、「荒漠」という表現を用いると、まだ造られていない陸地が、すでに存在しているかのような印象を与えてしまう。「荒漠」とは砂漠や荒野のように「荒れ果てた土地がどこまでも続いている様子」をさし、荒漠とした大地、原野などのように用いる。海に使う場合は比喩的な用法である。「地には形がなく、荒漠としていて」と述べられているので、新世界訳は間違いなく「海」ではなく「地」に用いている。地球全体はまだ水で覆われたままなのに、「荒漠とした地」はいったいどこにあったのだろうか。まさか海の底というわけではないと思うが。次に「水の深み」であるが、おかしいのは「水の深みの表」という表現である。ふつうに順序よく考えれば、「水の深みの表」とは「水の深み、つまり淵、深淵」そして、「その表、すなわちその表面」ということになる。そうすると、地球全体が深みに覆われていたのか、それとも所々が深み(通常の湖や川、沼はそうである)であったのか、また、闇は地球全体を覆っていたのに(光あれは第一日である)深みの上だけ特別、濃い闇に覆われていたのかといった疑問などが生じてくる。ここのテホームが何をさしているかはまったく問題がない。上の水と下の水に分けられる前に地球全体を覆っていた多量の水を表している。ただ、問題は「深み」や「淵(口語訳)」と意味を限定してしまうか、それとも概念を広げて「洪大な水」や「大いなる水(新改訳)」とするかということであろう。
次は創世記7章11節である。
「ノアの生涯の六百年目、第二の月、その月の十七日、その日に広大な水の深みのすべての泉が破られ、天の水門が開かれた」(創世記7:11)
「In the six hundredth year of Noah's life, in the second month, on the seventeenth day of the month, on this day all the springs of the vast waterydeep were broken open and the floodgate of the heavens were opened」
有名なノアの大洪水の始まりであるが、ここで問題とまるのは「広大な水の深みの泉」と「天の水門」をどう考えるかということである。天の水門はもちろん天にあるに決まっているので問題はないが、「深み」の方は、地上にあると考えるかによって解釈が分かれる。この点について新改訳聖書の脚注は次のように述べている。
「一章の『大空の下にある水と、大空の上にある水』を意識した表現。未曾有の大洪水は豪雨だけによらず、地下からの噴出や溢水、水脈や海底隆起のような、異常な現象を伴ったものであろう。ペルシャ湾岸地方は、地質年代上比較的新しい時代に大規模に浸水している。その原因は、海底の突然の隆起であった。これが海底火山の巨大な爆発であれば、豪雨をもたらし得るであろう」
またバルバロ訳聖書では次のように注解している。
「大洪水が地をおおうここの記述は、当時の宇宙論に従っている。当時の考え方によると、大地は大柱の上におかれ、下には深淵がある(創世49:25、詩編24(23):2、75(74):4、格言8:29、ヨブ37:18)地下のその深淵の水は、川などによって上に出てくる(格言8:24、28)ここでは川があふれたことなる。そのうえ「天の屋根」の水門が開いて、上にあった水も流れ出てきた。「ヤビスト」の伝えでは、むしろ、「大雨が降った」ことだけが原因で、洪水になったという」
これらの脚注の説明からも分かるように、訳語を選ぶカギとなるのは「大洪水の水がどこから来た」と考えるかである。天と地の両方からとすると、ここのテホームは「下の水」をさすことになるので、「淵」「深淵」「深み」などの訳語でよいことになる。しかし、天蓋上に地球を覆っていた水が雨となって降り注ぎ、大洪水が起きたと考えるのであれば、「深み」ではふさわしくない。ものみの塔協会は「上の水」説なので、「深み」ではおかしいはずである。新世界訳にはもう一つ意味不明の部分がある。「深みのすべての泉」という表現がそれであるが、いったいどういうことであろうか。いくら深い泉でも泉は泉というので、「深みの泉」だと淵の底からたくさんの泉が沸き出しているくらいにしか考えようがない。それに泉は水の噴き出し口があるので泉というわけだから、その泉が破られるというのも妙な表現である。「spring」には、「水源、源、源泉」の意味もあるので、「源」と考えると「泉」よりはましになるが、それでもやはり、ものみの塔協会が説明している大洪水の記述にはあわない。創造の二日目で分けられた「上の水」を大洪水の原因と考える以上は「水の深み」ではどうしても駄目であろう。
<ヨブ38:30>「水も石によるかのように身を隠しており、水の深みの表は堅くしまる」
「The very waters keep themselves hidden as by stone, And the surface of the watery deep makes itselfes compact」
「水の深みの表は堅くしまる」・・・表面張力のことであろうか。そういうふうにも受け取れるが、この前の節で「霜」や「氷」について述べているので、ここはやはり次のように考えるのが妥当であろう。
「いつ水が石のように凝結し、深淵の面が凍ってしまうのか!」 (ロバート・ゴルディス私訳)
「あなたはそれを知っているのか」とエホバはヨブに尋ねているのである。ただ、この聖句は「水の深み」もさることながら、その前の方、「水も石によるかのように身を隠す」がもっと分かりにくい。水が石の中に隠れるとは普通は言わないので、これは実に不自然な印象を与える。しかし、表面に張った氷を石に例え、その中に水が隠れていると考えれば、ユニークな擬人表現になるのかもしれないが。この他にも「水の深み」にはまだ幾つかあるが、この辺でやめることにする。
基本的には対応関係にある語でも、文化が異なるのでカバーする意味の領域がかなり食い違うときは、一語でその語を表そうとすると聖書解釈のレベルで複雑な解説を必要とすることになる。「魂」という語はそのような例の代表的なものである。日本語の「魂」には
のような意味しかないが、ヘブライ語「ネフェシュ」は (1)生命、(2)魂、(3)思い、精神、(4)意志、(5)人、(6)動物、 (7)魚、(8)その人自身、(9)息、(10)欲望、(11)食欲、貪欲、など、日本語の魂とは比較にならないほど、たくさんの意味を持っている。「魂」で「ネフェシュ」のすべてをカバーするのはとうてい無理である。ものみの塔協会の場合は「不滅の魂」の教えを否定しているので、魂で表せる意味野はもっと狭くなる。「魂」に関してふつう一般とは異なる教義を持ちながら、なおかつ、「魂」という語を使って一般の人々に読んでもらう聖書を出版するとすれば、次のような問題が生じてくる。
「すると人は生きた魂となった」(創世記2:7)医者となった人は医者であると同じように、創造された人間は魂であったのです。それで人間の魂とは人間そのもののことであり・・・・。「あなたの魂は肉を食べることを渇望するのであるが」(申命記12:20)魂を、物質的な食物を求める者として扱っています。「私の魂は悲嘆のあまり眠れませんでした」(詩編119:28)「魂」という言葉は、魂としての人自身をさす場合があります。それで「私自身」という言い方がありますがそれと同じ意味で、「私の魂」ということもできるのです。「それから、彼は三度、その子供の上に身を伸ばして、エホバに呼びかけてこう言った、『わたしの神エホバよ、どうか、この子供の魂をこの子の内に帰らせてください』。ついにエホバはエリヤの声を聞き入れられたので、その子供の魂はその子の内に帰り、その子は生き返った。」(列王第一17:21、22)魂という言葉はまた、生きた魂つまり生きた人間として人が持つ命を表すこともあります。たとえばわたしたちは、生きた人間であるという意味で、だれそれは生きていると言います。あるいはこの場合、人間としての命があるという意味で、彼は命を持っているということもできます。預言者エリヤが死んだ少年に奇跡を行ったとき、少年の魂(魂としての少年の命)は少年に戻り、「彼は生き返り」ました。少年は再び生きた魂となりました。(「とこしえの命に導く真理」P.35、37より)
以下のような妙な翻訳が生み出される原因になる。
「彼らは・・・しかも魂[の願望]の強い犬であり、満足することを知ってはいない」(イザヤ56:10、11)
魂の願望の強い犬とは、貪欲な犬のことである。
「まだ望みのあるうちにあなたの子を打ち懲らせ。これを死に渡すことにあなたの魂の願望をもたげてはならない」(箴言23:2)
食欲が強く自制するのが難しければということである。
「目で見ることは魂の歩き回ることに勝る」(伝道6:9)
この意味は難解で解釈も分かれているが、おそらく欲望の意であると考えられる。つまり、「目で見ているもの」(自分の手にできるもの)の方が「欲望がさ迷い歩く対象」(手に入らないもの)よりも勝っているということであろう。
訳語を統一すると、同一のヘブライ語やギリシャ語の使われているところが分かって便利であると考えるか、それとも、混乱や矛盾を生み出す原因となると判断するかは意見の分かれるところであると思うが、今まで論じてきたような問題が生じてくるのは間違いがない。おそらく、アダムの話していた言語、神が最初に人類に与えた言語がヘブライ語であったとか、イエスの話していた言葉がアラム語やギリシャ語であったというような、ヘブライ語、ギリシャ語に対する信仰めいたものが背後にあるのかもしれないが、あらゆる意味で完全無欠な言語というものはない。文化が異なれば意味領域にそれなりの限界が生じてくるのは、見てきたとおりである。ヘブライ語、ギリシャ語も決して例外ではない。
ものみの塔協会の特異な感覚では、字義訳も読みやすく感じるようである。「霊感」の本は「新世界訳」を次のように宣伝している。
「『新世界訳』を読む人はその言葉使いによって霊的に覚せいさせられ、霊感を受けた元の聖書の力強い表現にすぐなじんで読むことができるようになります。あいまいの表現を理解しようとして何度も節を読み返す必要はもはやありません。(「霊感」P.330)
本当にこの通りであれば読者にとっては理想的な聖書ということになるだろうが、しかし、実際はまさに宣伝とは正反対である。ごく普通の感覚で新世界訳を読めば、これは誰でもすぐに分かることであると思う。全編に渡って不自然な表現に満ちており、その冗長の長さは類例のないものとなっている。どうやら「新世界訳翻訳委員会」のメンバーも内心では多少の懸念を持っていたようで、「参照資料付き聖書」の序文に次のように記している。
「聖句の意訳のための言い換えはなされていません。むしろ、今日の表現法が許すかぎり、また字義通りの訳出によるぎこちなさによって考えが覆われてしまわない範囲で、できるだけ字義通りの訳出を行うよう努力が払われています」
やはり彼らにも、ぎこちなく感じられるところはあったということであろう。読みやすいというのは組織の宣伝であって、字義訳とは本来読みにくいものであるという自覚は持っていたようである。たぶん新世界訳翻訳委員会も読みやすくしようと大いに努力したのかもしれないが、それにしてはあまりにも不自然な表現が多すぎる。今の新世界訳をぎこちないと考えなかったことは、たいへん残念なことであるが、もしかしたら普通の人とは感覚の次元が違うのかもしれない。
ただ日本語になっていると思うか思わないか、不自然な表現かそうでないかは、各人の感覚のよって判断はかなり異なってくる。不自然な表現も裏を返せばユニークで斬新な表現ということになるかもしれない。その差はほんの紙一重であろう。所詮は感性の問題であると思うので、私たちも自分たちの基準の方が絶対に正しいというつもりはない。以下はあくまで普通の感性ではこうなるだろうというわたしたちの判断である。それでは、新世界訳の不自然な表現のほんの一部を紹介することにしたいと思う。
預言者エレミヤは神の裁きによって崩壊したエルサレムを眺め悲嘆に暮れていた。嘆き悲しむエレミヤの目は、噴水が流れ出る彫刻のようになってしまったようである。
「わたしの民の娘の崩壊ゆえに、わたしの目からは水の流れが下って行く」
「With stream of water my eye keeps running down on account of the breakdown of the daughter of my people」
確かにヘブライ語「マイ」は「water」という意味なので、字義訳すると新世界訳のような文章になる。「私の目からは水の流れが下って行く」・・・白髪三千丈式の誇張表現と言えなくもないが、やはり日本人にとっては馴染みにくい表現であろう。現代訳、新改定では、「私の目からは涙が川のように流れ」となっている。やはりこの方が自然である。
「わたしの目は注ぎ出されて、とどまるところがない」
「My very eye has been poured forth and will not keep still」
「My eyes will flow unceasiningly, without relief」(NIV)
「注ぎ出される」と訳されているヘブライ語「ナガル」の字義は確かに「注ぎ出す」であるが、「旧約聖書神学用語辞典(ハリス、アーチャー、ウォルトケ)」によると「嘆いたり、悲しんだりしている様子を表すのにも使用される」と説明されている。それで、そういう意味を取って、「とめどなく涙が流れる」(現代訳、NIV)のように訳すこともできるが、これも結局は、「目」「注ぎ出す」という字義をそのまま訳出するか、それとも「目から涙があふれるように流れ出す」というふうに意味を取って訳すかの問題であろう。それぞれの言語には特有の慣用表現がある。例えば「I'm all ears(耳を澄まして聞いている)」は、字義通りに訳せば「私はすべての耳である」ということになるが、普通はそうは訳さない。「目を注ぎ出す」をどのレベルで考えるかということであろう。
ナホム2章にはアッシリア帝国の首都ニネベの滅びとイスラエルの復興が預言されている。「誇りを集める」とはその中に出てくる一節であるが、一読しただけでは何を言わんとしているのかよく分からない。
「エホバは必ず、イスラエルの誇りのように、ヤコブの誇りを集めるのである。奪い去る者たちが彼らから奪い去ったからである。そして、彼らの岩枝を損なった」
「For Jehovah will certainly gather the pride of Jacob, like the pride of Israel, because those emptying out have emptide them out ; and the shoots of them they have ruined」
埃を集めることはできても、「誇り」を集めることはできない。強いて解釈すれば「誇りを取り戻す、プライドを回復する」ということになるかもしれないが、文脈にはあまり合わない。「pride 」には「(集団、社会、階層における)最良、最上のもの、精華」という意味もあるので、「イスラエルの精鋭を集める」の意の解釈できないこともない。しかしここは誇りだけではなく、動詞「gather」の方にも問題があろう。新世界訳が「gather」と訳している原文のヘブライ語「シャヴ(シュヴの変化形)」は「restore, renew,元へ戻す、回復させる」という意味の動詞である。したがって全体としては、口語訳の次のような訳が妥当であろうと思われる。
「主はヤコブの栄えを回復して、イスラエルの栄えのようにされる。かすめる者が彼らをかすめ、そのぶどうづるをそこなったからである」
「restore」が用いられていれば、日本語のような珍役は生じなかったであろうが、英語版がなぜ「gather」を選んだのか、機会があれば是非聞いてみたい。
アダムとエバが住んだパラダイス、エデンは美しく肥沃な地であり、そこから四つの川が流れ出ていた。新世界訳によるとその川は四つの頭になったという。
「さて、川がエデンから発していて園を潤し、そこから分れ出て、いわば四つの頭となった」
「Now there was a river issuing out of E'den to water the garden, and from there it began to parted and it became, as it were, four heads」
普通「川が頭になる」といえば、まず擬人表現以外には考えられない。しかしここは事実をそのまま記述しているところであって、擬人表現を用いるような箇所ではない。新世界訳は「頭」と訳すことによっていったい何を伝えようとしたのだろうか。意味としてはエデンの地が四つの川の水源になっていたということなので、新改訳のように「四つの源となっていた」と訳すのが妥当であろう。英語の「head」には「頭」以外にも、「源、水源」という意味があるので、英語版は問題がないのかもしれないが、「head」ではなく、「headstream,beginnings ofstreams」を用いていたなら、このような場違いな訳は防ぐことができたはずである。
これはソロモンの知恵や繁栄に驚嘆したシェバ女王の言葉である。あまりの素晴らしさに気が動転してしまったのであろうか、「?」と思うようなことを口走っている。
「あなたは知恵と繁栄の点で、私のお聴きした、聞かされたことをしのいでおられます」
「お聴きした、聞かされたこと」・・・?誰でも一度は読み返すに違いない。日本語の訳の不自然さもさることながら、ここは英語版にも問題がありそうだ。幾つかの訳を並べてみよう。
新世界訳の他は、report, fame(報告、名声、評判)を使っている。元のヘブライ語「シェムア」、ギリシャ語「アコエ」にはhearing, news, report, rumor,messageという意味がある。したがってここは「あなたの知恵や繁栄は、私が聞いていたことをはるかにしのぐものです」ぐらいになるだろうか。新世界訳は正確な表現と自負しているのかもしれないが、「お聴きした、聞かされたこと」というのは、日本人には何とも奇異に感じられる表現である。こういう珍訳の原因は関係代名詞を直訳したことにあるが、次に関係副詞を訳してしまった例を紹介しよう。
息子アブロサムの反逆に遇い、逃走するダビデが自分に従ってきたギト人イッタイの安否を気遣って、戻るように勧めている場面である。
「あなたは昨日来たばかりで、今日わたしはどこか行こうとしているところへ行くところなのに、あなたを行かせて我々と共にさまよわせるというのか。戻って行きあなたの兄弟たちを共に連れて戻りなさい」
「Yesterday was when you came and today shall I make you wander with us , to go when I am going wherever I am going ? Go back and take your brothers back with you 」
突然の反逆に驚き、惑ったダビデ王は、思わず舌がもつれてしまったのであろうか。「to go when I am going wherever I am going ?」を上記のように訳したのであるが、中学生でもこういう訳文は作らないと思う。新改訳の「私はこれから、あてどもなく旅を続けるのだから」や、口語訳の、「わたしは自分の行くところを知らずに行くのに」ぐらいが自然な表現であろう。
預言者イザヤは堕落したイスラエルに愚行を止めるように勧め、それに応じる人々には神からのいやしが与えられるということを次のように描写している。
「あなたは必ず、よく潤っている園のようになり、その水が うそをつくことのない水の源のように[なる]」
「you must become like a wellwatered garden, and like the source of water, the waters of which do not lie 」
ウソをつかない水の源とはどういうことであろうか?「正直な水」といってもよく分からない。おそらく「そこへ行けば必ず水を飲むことができる、期待を裏切られることがない」ということであろうが、それにしても難解な表現である。ヘブライ語の「カーザブ」には、「be found a liar 」「be in vain 」「fail」などの意味があり、「うそをつく」にしなければならない必要性はない。ゆえにこの場合は、「水のかれない源のようになる」(新改訳)「水の絶えない泉のようになる」(口語訳)
と訳した方が分かりやすい。
これは背信したイスラエルに対する神の裁きの宣告であり、神を捨て、強国エジプトに助けを求めたイスラエルについての預言である。
「ノフとタフバネスの子らもあなたの頭の頂きを食らいつづけた」
「Even the sons of Noph and Tah'pan・es themselves kept feeling on you at the crown of the head 」
エジプトの都市、ノフとタフパネスの住民が人食いだというわけではないだろうが、これでは意味不明。「食らいつづけた」と訳されているヘブライ語「ラア」は、基本的には「(羊、山羊を)飼う、牧する、(牛、羊などが)草をはむ」という意味を持っており、ゲセニウスはエレミヤ2:16のラアを「devour むさぼり食う」と訳している。ものみの塔協会は、当時の状況を「エジプト」に援助を仰ぐことはユダの王族、支配者たちに高い代価を求めることであったろう。」と説明している。それで以上の点から「crown 」を「王座、王位」、「head 」を「指導者、支配者」と考えれば「王座を食い物にする」といった訳も可能と思われる。それにしても「頭の頂きを食らい続ける」とは何とも珍妙な表現である。幾つかの英訳や日本語は「頭を剃る」とか「頭を打ち砕く」というふうに訳している。
婉曲表現を字義訳すると滑稽な訳語ができあがる。
「またあなたは、肉の大きなあなたの隣人、エジプトの子らと売春を行ない、あなたの売春をあふれさせてわたしを怒らせた」
「And you went prostituting yourself to the sons of Egypt, your neighbors great of flesh, and you continued making your prostitution abound in order to offend me 」
この聖句は、堕落したイスラエルがエジプトと文字通り、あるいは宗教的な意味で売春をして神を怒らせたことを説明しているところであるが、「肉の大きな隣人」とはどういうことであろうか。日本語のままで考えるなら「肉の大きな隣人」とは「太った人」ということになり、イスラエルは肥えた人を淫行の対象にしていた、またはそのころのエジプト人は皆太っていたという意味になってしまう。「肉」に当たる英語の「flesh」ヘブライ語の「バシャル」は、これ以外にも「身体、肉欲」という訳語があるので、「肉」にこだわる必要はない。また「F・ブラウンによる旧約聖書のヘブライ・英語辞典」によると、「バシャル」は性交の婉曲表現としても用いられたようである。このような点から考えると、「肉の大きな人」は二つの見方ができる。
「良いからだをした(繁栄をあらわす)」(新改訳)
「肉欲的な隣り人」(口語訳)
参照資料付き聖書の説明を見ると、新世界訳は後者の解釈をとっているようだが、「greatflesh −肉の大きな人」では正確な意味を伝えることはできない。婉曲表現でもかまわず字義訳するのは、読者にとって非常に迷惑なことである。
初めて婚約者イサクに会ったリベカは当時の習慣にしたがって布で身を覆った。さてその布は何だったのだろう。
「そして僕にこう言った。『野を歩いてわたしたちを迎えに来るあの方はどなたですか』。すると僕は言った、『あの方がわたしの主人です』。それで彼女は頭きんを取って身を覆った」
「Then she said to the servant:“Who is that man there walking in the field to meet us?” and the servant said:“It is my master.” And she proceeded to take a headcloth and to cover herself」
「headcloth」は、ターバンなどのような頭巾を表わし、頭を覆うぐらいの分量しかない。日本では頭巾といえば、やはり頭や顔を覆うくらいのものを指し、体を包むほどのものを頭巾とは言わない。元のヘブライ語「ツァイーフ」は、「ベール、ショール、長くゆったりした外衣」などを指している。バイイングトンは「muffler」、NIV、七十人訳、アメリカ標準訳、欽定役は「vail」を使っている。「続目で見る聖書の世界」p.75 には、当時の服装について記されているが、その中に次のような一文がある。「婦人特有の衣料には薄い白布の被衣があり、愛人に紹介されるとき(創24:65)、身分を 隠すとき(創38:14、19)に用いた」したがって、ベールくらいが適当と思われるが、新世界訳がなぜ「headcloth」にしたのかはよくわからない。
落胆しているエレミヤに対し、神が、「もっと厳しい状況に直面したら、どう対処するのか」と諌めているところである。
「あなたは平和の地で自信があるのか。では、ヨルダン沿いの誇り高い[やぶ]の中ではどうするのか」
「And in the land of peace are you confident? So how will you act among the proud [thickets] along the Jordan 」
「平和の地で自信があるのか」というのもよく分からないが、「誇り高いやぶ」となると、完全にお手上げである。高慢なやぶがエレミヤにつらくあたるというのだろうか・・・。「誇り高いやぶ(the proud 「thikets」)」と訳されているヘブライ語は「ガオン」である。「ガオン」には、「pride 誇り高い、高慢な」という意味もあるが、ゲセニウスやF・ブラウンのヘブライ・英語辞典、旧約聖書神学用語辞典(ハリス)によると、「雄大な、見事な、荘厳な」などという意味もあることが指摘されている。三者ともエレミヤ12:5のガオンの意味として後者の方を取っており、ヨルダンの密林を表わすものと解説している。やぶの形容詞としてのproudの訳を辞典で探すのは少し手間がかかる。ウェブスターの第3版3(C)(2)「of a plant,Brit:LUXURIANT(植物などが)繁茂した、うっそうと茂った」ぐらいまで探さないとぴったりする表現がない。「新世界訳英語版」の委員会は「proud」をそういう意味で使ったのかもしれないが、普通「proud」ときたら「誇り高い」となるはず。原文忠実な日本語訳は確信をもって「誇り高いやぶ」と訳したのであろう。なんとも罪作りな英文である。ちなみに幾つかの英訳を比較してみると、
となっており、日本語訳は新改訳、現代訳、口語訳、リビングバイブルが、「ヨルダンの密林」、バルバロ訳は「ヨルダンの森」と訳している。「やぶ」を擬人化する必要はまったくないところである。
字義はしばしば矛盾した表現を生み出す。ダビデは息子アブロサムの陰謀にあい、やむを得ず逃げることになった。家に残された10人のそばめは哀れにもアブロサムに辱められてしまったのである。やがてダビデは戦いに勝って戻って来たのであるが・・・
「彼女たちは生きた[夫]のいるやもめの状態で、自分たちの死ぬ日まで、しっかりと閉じ込められていた」
「they continued shut up closely until the day of their dying, in a windowhood with a living[husband]」
普通、夫が生きている場合「やもめ」とは言わない。「やもめ」とは、「夫と死に別れた婦人、未亡人」のことなので字義通り考えると?となる。これは、アブロサムが戦いに破れて死んでしまったため、彼に辱められた10人のそばめをダビデは「やもめ」のように扱ったことを示している聖句である。彼女たちにとってダビデは「生きた夫」であるので、「生きた夫のいるやもめの状態」という訳も理解できないことはないが、それにしても矛盾した表現である。ここは、「未亡人同然の生活」(現代訳)の方が適切であろう。
人々は金や銀を求めて地底深く潜っていく。宝を得るためにはあらゆる困難をものともせず一生懸命に働く。そのようにして多くの金銀、宝石は掘り出されてきた。しかし、貴金属よりはるかに価値のある真の知恵はいったいどこに見い出すことができるのであろうか。はたして人はそれを探り出すことができるだろうか。金や銀などの目に見える宝とは異なり、真の知恵は人知によっては探り出すことのできないものである。神だけがその本当のありかを知っている。こうしたことを詩内に表現した箇所の一部が、次の一節である。
「人は[人々が]外国人としてとどまっている所から遠く離れて立て杭を掘り下げた。足から遠く忘れられた所で。死すべき人間のある者たちは、ぶら下がり、ぶらぶらしていた」
「He has sunk a shaft far from where[people] reside as aliens,Places forgotten far from the foot; Some of mortal men have swung down, they have dangled」
何とも理解し難い訳である。前半の方は、金、銀を求める人々が人里離れた所で穴を掘っている様子であることは分かるが、後半は思わず吹き出してしまいそうな訳になっている。これでは処刑される人かあるいは死のうとしている人がどこかに引っ掛かって、ブラブラしているような印象を与えてしまう。一つ一つ考えて見よう。「足から遠く忘れられた所」というのは、人があまり行かない所のことであろう。ヘブライ語の言い回しらしい。「死すべき人間」というのは3章でも紹介した、新世界訳ご自慢のエノシュである。ここも「死すべき」を付ける必要はないところである。「ぶらさがり、ぶらぶらしていた」とは、「dangle」を直訳したものであろう。「dangle」にあたるヘブライ語の「ダウ」には、この他にも「hang, pendulous; 吊す、下がる、垂れ下がっている」などの意味があるので、ここは人や物が吊り下がっている様子を表わしていると考えた方がよい。ゲセニウスなどのヘブライ語辞典はこの聖句について、「ロープで体を縛った炭坑労働者が穴を昇り降りするときに、揺られる状態」と述べている。上記の訳のように笑いがこみ上げられてくるようなものではなく、もっと危険な状況を表わしていたのである。それにしても、意味を考えず一字一句の字義訳を並べただけの訳はまさしく宙ぶらりんである。こういう具合に、文を読んでみてもそれがどういう状況なのか、何を言わんとしているのかよく分からないという場合、たいていは単なる翻訳の技術よりも訳者の頭の質の方に問題があるようだ。別宮貞徳氏は「誤訳迷訳欠陥翻訳」の中でそのような訳文を「ハクチ的文章」と述べ、次のように述べている。
「もちろん、文章がハクチ的だといっても、訳者がハクチというわけではありません。およそ翻訳には相当な頭が必要で、訳者はどなたもそれだけの頭を持っていらっしゃるはずです。しかし、その頭がこちこちに硬直していることが、往々にしてある。・・・・そして、頭が硬直していると、ばかばかしいまちがいをやたらしでかすのも、当然かもしれません。」(P.139,140)
ハクチ的文章に当たるような箇所は他にもまだまだあるので、他の聖書と比較しながらその幾つかを紹介しよう。
「心配のない者は、考えにおいて、消滅に対して侮べつを抱く」
「In thought,the carefree one has contempt for exetinction itself 」
「安らかだと思っているものは衰えている者をさげすみ、足のよろめく者をおしたおす」(新改訳)
「それらはわたしの食物の中の変質のようだ」「They are like disease in my food 」
「それは私には腐った食物のようだ」(新改訳)
「それはわたしのきらう食物のようだ」(口語訳)
「そして、離れ落ちてゆく者たちはほふりの業に深く下り、わたしは彼らすべてに対して訓戒であった」
「And in slaughter work those falling away have gone deep down,and I was an exhortain to all of them」
「曲がった者たちは、人々を死へ導いた。わたしは彼らをことごとく懲らしめる」(現代訳)
「曲がった者たちは落とし穴を深くした。わたしは彼らをことごとく懲らしめる」(新改訳)
すべてまったく意味不明なものばかりである。
エルサレムはおびただしい違反ゆえに、神の裁きによってついに崩壊した。次の聖句はそのことに対する深い悲しみを表明したものである。
「[神]はわたしの違反に対して油断なく気を配られた。そのみ手の中でそれらは互いに絡み合う。それらはわたしの首に上った。わたしの力はつまずいた」
「He has kept himself alert against my transgressions, in his hand they intertwine one another, they have come up upon my neck. My power has stumbled 」
全体的に変な文章であるが、「力がつまずく」という表現は特に奇妙な感じを与える。「つまずく」とは、「歩くとき、足が物にあたってよろける、途中で障害にあって失敗する」という意味なので、そのまま続けると「力がよろける、力が失敗する」というふうになる。これはどう考えても妙である。「stumble」には、「つまずく、失策する、口ごもる、出くわす」ぐらいの意味しかないので、英語版に忠実であろうとすれば、「つまずく」以外に訳しようがない。「力がつまずく」とは、一体どういう意味であろうか。ここで用いられているヘブライ語「カーシャル」には「stumble」の他に、「fail 衰える、弱る」の意味もあるので、NIVでは「sap 弱る」、七十人訳では「fail」にしている。他の日本語訳は、「力をくじき」(新改訳、現代訳)、「力を衰えさせられた」(口語訳)となっている。ここは単に「力がなくなった」ということを示しているにすぎないので、新世界訳が、なぜわざわざ「stumble」を用いるのかよく分からない。これでは人々に聖書の真意を伝えるどころか、混乱を生じさせるだけであろう。
エホバは堕落したエルサレムとユダ王国をついに見捨てられ、バビロンに引き渡された。しかしその70年後、彼らに哀れみを示し、エルサレムに戻すことを約束したのである。この聖句は、それまで彼らを捕らえていた諸国民に対する憤りを表明したものである。
「安楽にしている諸国民に対しては大いなる憤りをもって憤っている。わたしは少しだけ憤ったのだが、彼らは災いを助けたからである」
「With great indignation I am feeling indignant against the nations that are at ease;because I, for my part,felt indignant to only a little extent, but they,for their part,helped toward calamity 」
「憤りをもって憤っている」というのも妙だが、「災いを助けた」というのはもっと奇妙である。もし諸国の民が「災いを助けた」のであれば、神の糾弾を手伝ったということになるので、神が諸国の人々に憤る必要はなくなる。しかしそれだと前の部分と矛盾してしまう。それとも、これは神の皮肉だろうか?この聖句は、「神が下した災いに加えてイスラエルを必要以上に苦しめた。またはそれ以上にむごいことを行なった」ということを示しているので、「助ける」は適切ではない。「help」は「助ける」だけでなく、「助長する」という意味もあるので、ここは「災いを増し加えた」(現代訳)、意訳ではあるが、「ほしいままに悪事を行なった」(新改訳)の方が文脈に合う。
エゼキエルは幻を見た。その中で彼はみ使いによって神殿の食堂に連れて来られたのだが、どこに何があったのかよく分からなくなったようである。
「1そして、やがて彼は北に向いている道から、外の中庭へわたしを連れて出た。次いで彼は、隔てられた場所の前、北の方の建物の前にある食堂[群]に連れて来た。2長さ百キュビトの前に北の入り口があり、幅は五十キュビトであった」
「Before the length of a hundred cubits there was the north entrance, and the width was fifty cubits 」
1節では、「北方の建物の前にある食堂[群]に連れて来られた」ことが記されているのだが、上記の訳では何の百キュビト前か、何の幅が五十キュビトなのかよく分からない。幅、五十キュビトの入り口が建物の百キュビト前にあるか、あるいは食堂と建物の間の距離が百キュビトだったと考えられないことはないが、きわめてあいまいな文章である。文脈をみても意味はさっぱりわからない。NIVの訳と比べてみると、
「The building whose door faced north was a hundred cubits long and fifty cubits wide」
「北向きにドアのある建物は高さ百キュビト、幅五十キュビトであった」
となっている。実に分かりやすい。ここで問題になるのは、新世界訳で用いている「before 〜の前に」とNIVの「faced 〜に面した」である。ヘブライ語の前置詞「エルーペネ」には多くの用い方があるが、ゲセニウスによると、前置詞「ペネ」は「エル」を伴うと「toward 〜に向かって、〜に面して」の意味を持つようになると述べられている。したがって、ここは「百キュビトの前」ではなく、「その長さは百キュビト、その端に北の入り口があり幅は五十キュビトであった」(新改訳)と訳す方がよい。
次の聖句は、背教したエルサレムに臨む荒廃を預言したものである。
「そして、雄の子羊は自分の牧場にいるかのように実際に草を食い、肥え太った動物の荒廃した場所を外人居留者が食べるであろう」
「And the male lambs will actually graze as in their pasture; and the desolate places of well-fed animals residents will eat 」
ここは英語を直訳すると、確かに「場所を食べる」ことになってしまうのだが、「場所を食べる」とは・・・まったく意味不明。「肥え太った動物の荒廃した場所」というのもどういう場所なのかよく分からない。これもやはり意味不明。預言の内容自体は、やがてエルサレムには人が住まなくなり、羊が草をはんだリ、外国人の羊飼いが訪れるくらいさびれた所になるだろうというものである。かつては外人居留者などとても近寄れなかった富んだ人々の牧草地(肥えた羊や山羊が草を食んでいた)に、彼らも自由に出入りできるようになるということである。せめて「野獣は廃虚の中で食を得る」(現代訳)「肥えた獣は廃虚にとどまって食をとる」(新改定訳)「肥えた家畜および小やぎは荒れ跡の中で食を得る」(口語訳)くらいの訳にはすべきであろう。こういう表現をそのまま載せるという、この文章感覚には正直いって素直に驚くしかない。参考までに次のような意見を紹介しておこう。
「ところで、最初にオンチとブンチとの関連なんてヘンなことを申しましたが、ブンチっていうのは文章オンチ。方向感覚がにぶい人のことを方向オンチと言いますね。それと同じ伝で、文章オンチ、略してブンチ。つまり文章感覚のにぶい人のことです。文章を書くのは音楽の演奏に似ている。そして、オンチは音楽づくりに手を出すな、と同じ言い方をすると、ブンチは文章づくりに手をだすな、ということになりますか」(誤訳迷訳欠陥翻訳 P.133 別宮負徳 著)
次の預言は背信したイスラエルに対する裁きの宣告である。
「[神]も賢い方であり、災いとなるものをもたらされる。[神]はご自分の言葉を呼び戻されなかった。[神]は悪を行なう者たちの家に敵して、有害なことを習わしにする者たちの援助に適して必ず立ち上がられる」
「And he is also wise and will bring in what is calatious, and he has not called back his own words; and he will certainly rise up against the assistance of those practicing what is hurtful」
「言葉を呼び戻す」とは物理的には成り立たない表現である。残るは比喩的な表現ということになるが、ここはそういう箇所ではない。つまり、「言葉を呼び戻す」という表現ではおかしいのである。辞書によると、「call back」には、(1)呼び戻す(2)〈発言・告訴などを〉取り消す、撤回する(3)回収するの意味がある。文脈や意味を考えれば、「み言葉を取り消さない」(新改訳)、「その言葉を取り消すことなく」(口語訳)とするはずである。どうやら、「call back」の最初に上げられている意味にしか目が行かず、(2)(3)は目に入らなかったらしい。
不自然な表現は全編に満ちているので、上げて行けば切りがないが、以下その中でも代表的なものをまとめて紹介することにしよう。
「わたしは必ず、わたしの民イスラエルのために一つの場所を定め、彼らを植えるであろう」
「I shall certainly appoint a place for my people Israel and plant them, and they will indeed reside where they are, 」
イスラエルを定住させるという意味である。
「耳を植える方は、聞くことができないだろうか」
「The One planting the ear, can he not hear?」
「目や耳をお造りになった方が、どうして見たり、聞いたりできないだろうか」(現代訳)ということである。
「神からの恐怖がわたしに向かって整列する」
「The terrors from God range themselves up against me」
ヨブは神からの恐怖を戦闘隊形を組んだ軍隊に例えたようである。
「わたしは必ずその敵の地で彼らの心の中におじ気を入れる」
「I shall certainly bring timidity into their hearts in the lands of their enemies」
彼らをおじけさせる、弱めるという意味。
「2ああ、わたしの悩みがことごとく量られ、同時にわたしに逆境を人々がはかりにかけたなら!3今やそれは海の砂よりも重たいからである。だから、わたしの言葉は乱暴な話しだったのだ」
「3For now it is heavier even than the sands of the seas. That is why my own words have been wild talk」
「3It would surely outweigh the sand of the seas no wonder my words have been impetuous」(NIV)
ヨブの言葉の乱暴な話というのは、どうやら「わたしの言葉が軽率であったのだ」(口語訳)ということらしい。
「そして彼はその者たちに打ちかかり、股の上に脚を積み重ねて大々的な殺りくを行なった」
「And he went smiting them,piling legs upon thighs with a great slaugter」
下線の部分は、「大々的な殺りくを行なった」ということを表わす慣用表現である。
「肥え太ってくると、エルシュン(イスラエルの詩的な呼び名)はけり足を挙げた」
「When Jesh' u run began to grow fat, then he kicked」
国力が豊かになり、高慢になったイスラエルが神に背を向けるようになったことを詩的に表現しているのだが・・・「けり足」とは・・・・。「エルシュンは肥え太り、後ろ足で蹴り上げた」(バルバロ訳)ぐらいが適当であろう。
「王は裁きの座につき、自分の目ですべての悪を散らしている」
「The king is sitting upon the throne of judgment, scattering all badness with his own eyes」
バルバロ訳では、「裁判の席に座する王は、すべての悪を一目で見分ける」となっており、「賢い王は裁判の時、善と悪を一目で見分ける」という説明がなされている。
新世界訳の冗長さは実に見事なものである。おそらくこの冗長さを廃するだけで、少なくとも100ページは短くなるのではないかと思われる。本来ヘブライ語は接続詞が多く用いられる言語である。それを可能な限り訳してゆくと、膨大な接続詞の量になってしまう。新世界訳では例えば、創世記は「and」のオンパレードになっている。英語の感覚はよくわからないが、日本語では「and」をことごとく訳してしまうと、どうにも煩わしくてしょうがない文章ができあがる。さらに、新世界訳は接続詞の他にも、まわりくどい表現、慣用表現などをそっくりそのまま訳しているだけでなく、[・・・]を用いて言葉を挿入するなど、冗長さに輪をかけるようなことをしている。こういう冗長さの要素をことごとく取り除いたとすれば、短縮できるページ数は百をはるかに超えるものになるだろう。以下にその事例を上げていくが、最初に紹介するエズラ記ではおびただしい代名詞をことごとく訳出しており、その数の多さに、文章の流れはもとより、読む意欲も途中で消え去っていくほどの悪文になっている。別宮氏は「誤訳迷訳欠陥翻訳」の中で
「代名詞の数で翻訳のじょうずへたがわかる―っていうのは僕の持論だけど、わずか十九行の中に、彼女、あなた、わたくしが二十二個はいっていた。これはちょっとした記録だろうな」(P.98)
と述べているが、どうやら新世界訳はそれを凌ぐ新記録を達成しそうである。
ここには「わたし」「わたくしたち」がなんと27回も出てくる。たった4節の中に27回である。時間のある人は数えてみて欲しい。
「5.そして、夕方の穀物の捧げ物[の時]に、わたしは引き裂かれた衣とそでなしの上着をまとったまま、屈辱から立ち上がり、それから両ひざでひざまずき、わたしの神エホバにたなごころを伸べた。6.次いでわたしは言った、「私の神よ、私は実際恥ずかしくて、私の神よ、あなたに向かって顔を上げることにもまごついております。私たちのとがは、私たちの頭の上に増し加わり、私たちの罪科は増大して天にまで達したからです。7.私たちの祖父の時代から今日に至るまで、 私たちは大いなる罪科の中にありました。私たちのとがのために、私たちは、すなわち私たち自身や、私たちの王たち、祭司たちは各地の王たちの手に渡され、剣にかけられ、補囚の身とされ、強奪に遭い、顔に恥をかかされて、今日ある通りです。8.ところが今、しばらくの間、私たちの神エホバからの恵みが臨みましたが、これは逃れる者たちを私たちのために残し、その聖なる場所に私たちに賭けくぎを与えてくださることによるのです。それは、私たちの神よ、私たちの目を明るくし、奴隷状態の私たちをしばらく生き返らせてくださるためでした。9.私たちは僕だからです。けれども、この奴隷状態にありながら、私たちの神は私たちを捨ててはおかれず、かえってペルシャに王たちの前で愛ある親切を施してくださいますが、これは私たちを生き返らせて、私たちの神の家を立てさせ、その荒れ果てた所を元通りにさせ、ユダとエルサレムで石の城壁を私たちに与えさせて下さるためです」
「それは、わたしがあなた方を追い散らし、あなた方が、あなた方もあなた方に預言している預言者たちもが、必ず滅びうせるためなのである。」
その他の冗長な表現
「また、これは地に群がる群がる生き物のうち・・」
「地の上を動くあらゆる動く生き物」「あらゆる肉なるあらゆる生き物」
「・・・大いなるしっとをもってしっとする」
「・・・油をもって油注がれた者」
新世界訳は字義役によって辞書にはない様々な語を作り出している。以下にその一部を上げよう。
「また、その頭が上の正面のところではげてくるなら、それは額はげである」(レビ13:14)
単なるはげのこと、てっぺんがはげていれば「てっぺんはげ」とでもいうのだろうか。
「ヨナタンとその武具持ちが彼らを討ち倒したその最初の殺りく[で殺したの]は、一エーカーの畑のすき道のおよそ半分以内のところで、およそ二十人であった」( I サムエル14:14)
畑を耕して作った畆のことである。
「しかしヨアブは彼に言った、『あなたはこの日の知らせの人ではない』」( II サムエル18:20)
メッセンジャー、使者、伝令のことである。
「エホバよ、怒りのうちに立ち上がってください。わたしに敵意を示す者たちの憤怒の激発に対して身を起こしてください」(詩編7:6)
激しい怒りのことである。
「見よ!わたしたちはそれをエフラタで開き、森林の野にそれを見いだした」(詩編132:6)
これは森のことである。
「あなたはこれをいなごのように飛びはねさせることができるか。その鼻あらしの威厳は怖ろしい」(ヨブ39:20)
馬の鼻息のことである。
「そのとき、せん越の水がわたしたちの魂を越えて行ったことだろう」(詩編124:5)
イスラエルに敵対する者たちを表わしている。溢れる水、逆巻く水のほうが日本語らしい。これらの言葉が日本語として辞書に載るには、ものみの塔協会の時代にでもならなければまず無理であろう。
以上、字義訳聖書「新世界訳」ならではの珍表現、不自然さ、意味不明な文章を紹介してきたが、これらはほんの一部にすぎない。日本語になっていない表現がそれこそ全編に満ちているため、読者にとって非常に理解し難い聖書になっている。外山滋比古著、「日本の文章」の中に、聖書が近代散文に与えた影響について述べるくだりがある。英語散文の範とされる「天路歴程」を書いたジョン・バニアンを紹介し、正規の教育を受けなかったバニアンが聖書を繰り返し、繰り返し読むことによって文章能力を身に着けたことを記している。その聖書とは「欽定英訳聖書」のことであり、近代英語散文の基本とみなされていると述べ、次のように結んでいる。
「バニアンのように徹底して聖書の影響を受けた例はさすがにすくないが、ほとんどすべての近代散文に大なり小なり聖書の影が認められる。聖書は信仰の大黒柱であるにとどまらず、文章の指針でもあった。」(P.216、217)
昨今洋の東西を問わず、国語の乱れが憂慮すべき問題として取り上げられることが多くなってきている。日本では欧米ほど一般に聖書が普及しているというわけではないが、聖書にもそれなりの役割を期待してもよいのではないかと思う。人類に啓発を与えるために記された聖書であれば、国語教育に貢献するのも一つの使命であろう。少なくとも決して逆の貢献だけではすべきでない。宗教改革者ルターが新、旧約聖書ドイツ語訳を通じて作り出した標準的ドイツ語は、近代ドイツ語への道を開いたとされる。翻訳に際して、ルターは分かりやすい聖書を作るため大衆の中に入って、彼らが日常使う言葉を徹底的に調べたと伝えられている。残念なことに新世界訳翻訳委員会には、このルターのような基本姿勢はなかったようである。日本語としてどれが適切な表現であり、読者にとって意味が分かりやすいのはどういう表現か、もう少し検討してほしかったと思う。聖書とはそもそも、神が人類にご自分の意志や目的を伝えるために作られた本である。基本的には聖書は理解しやすいものでなければならない。確かにそのすべてが易しく、分かりやすいように書かれているわけではない。日常の言語では表現できないような深淵な真理もあれば、非常に深い意味が込められているところもある。しかしそうした難しさとは、複雑でわけの分からないような表現や漠然とした用語を使うことによる難しさとは、まったく異質なはずである。また聖書には当時の人々が通常使っていた言葉やシンプルで平易な表現が多く用いられている。神も基本的には、人々が理解しやすい、分かりやすい聖書を望んでいるということであろう。したがって、聖書のもつ使命から言っても訳者はもっと次の点に考慮を払うべきである。
「まず、翻訳は日本語で訳してほしい。・・・原文忠実ということをよく言う。でたらめな訳がいいわけがない。原著の言わんとしているところをなるべく正確に伝えるのは訳者の務めである。いわゆる誤訳は極力避けなければならない。ただ、誤訳を恐れるあまり、原文忠実で、わけのわからない訳文になっても平気だというのでは読者は迷惑する。原文忠実がしばしば欠陥日本語の言い訳になっている。原文忠実か、日本語らしい文章か、という二者択一をせまられたら、訳者はためらうことなく、日本語をとってもらいたい。ところが、いまの翻訳者の多くが語学の教師である。教師は日本語がなっていないと言われてもまったく痛痒を感じないが、誤訳がひどい、語学力が怪しいといわれるのは職業的にも影響が小さくない」(「日本の文章」P.202外山滋比古著)
日本語でなければ何も伝えることができないわけだから、これは当然のことである。いかに神の言葉とはいえ、意味が通じなければ霊的に築き上げるものとはならない。本来の使命を達成するためにも、訳者はもっと分かりやすい日本語にすることを心がけてほしいと思う。
教義とは、ある特定の宗派や教団によって真理として公認された教えのことであり、教理またはドグマともいう。通常のキリスト教(主としてプロテスタント諸教会)の場合は原則として、教義を作るときには聖書以外のものは用いないということになっている。(モルモン経を有するモルモン教会や統一原理を教える統一教会は例外である。)
約1900年前、「救い主はイエス・キリストです。悔い改めてバプテスマを受けなさい」という非常にシンプルな音信から始まったキリスト教は、その後、次々と教理を増し加え、今日では膨大な教義体系を有するようになった。その中には聖書外典やまったく別の経典から作られたものもあるので、そのすべてに聖書的根拠があると唱えられているわけではない。しかし、ほとんどの教義には、それなりの聖書的な根拠があると主張されている。
聖書的根拠があると主張されている教義を聖書翻訳との関連から分類してみると、大体次のように大別することができる。
どの聖書を使っても良いということは、言い換えれば、翻訳にそれほど違いがないということであるが、また好きなように解釈できるということでもある。したがって、これは純粋に解釈の仕方の問題になる。聖句に対する視点を変えると、それなりの論理を組むことができるもので、復活、神の王国、三位一体、終わりの日、キリストの再臨など主要教理と言われるもののほとんどはこの項目に入る。
例えば、次のような聖句があったとする。
「わたしと父とは一つです」(ヨハネ10:30)
これは、「一つである」というところに注目すると、キリストと父とは一つなのだから三位一体を教える聖句だということになるし、「わたしと父」に注目すれば、二人しか出てこないのだから二位であって三位ではないという具合になる。
もう一つ「魂」に関する聖句を。
「からだを殺しても、たましいを殺せない人たちなどを恐れてはなりません。そんなものより、たましいもからだも、ともにゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい」(マタイ10:28新改訳)
この聖句からは、まったく相反する二つの異なった結論を導き出すことができる。「キリストは、人は体を殺しても魂を殺すことはできないと述べている、ゆえに、人間は人が殺すことのできない魂を持つという意味で、不滅の魂を有する」というのが一つ。そしてもう一つは、「神は魂も体も共に滅ぼすことができると言っているのだから、そもそも不滅の魂などというものはありうるはずがない」である。要するに解釈の視点の問題であるが、その視点は解釈する本人が正当化したいと考えている教義によって決定されることになる。
さて、次は特定の聖書でないとダメな教理であるが、それはなぜかと言えば、ある特定の用語がその教義を論証するカギになるからである。もし別の聖書を使えば、先に教理を設定しなければならなくなる。
「神の名はエホバである」という教えは、エホバを使っている聖書であれば、「ここにこのように出ています」と簡単にその根拠を示すことができる。しかし、エホバを使わず、すべて「主」や「神」になっていたり、別の呼び方ヤーウェやヤーヴェを用いていれば、先に神の名はエホバであるという教理を確立しなければならなくなる。
「キリストは十字架ではなく一本の杭の上で死んだ」とか「聖書に地獄の教えはない」というような教理もこの項目に入る。
以上二つの分類について考えてきたが、これはもちろん、ものみの塔協会以外の教理にもそのまま当てはまる。ものみの塔協会の教理だけが例外で、絶対的な聖書的根拠を有するなどということはない。すべての教義は、解釈の視点に依存しているか、新世界訳に依存しているかのどちらかである。
新世界訳は字義訳なので、ものみの塔協会の教理には、字義訳ならではの教理、字義訳主義でなければ作れないような教理がある。その背景を検討してみると、いかにも字義訳主義らしい教理の作り方が浮かび上がってくる。
以下そうした事例を幾つか取り上げ、最後に聖書翻訳の根底に潜む問題を考慮したいと思う。新世界訳の場合、教義との関連は字義訳の問題に集約して考えることができるし、さらに聖書の翻訳と教義の関係は極めて本質的な問題をはらんでいるからである。
創世記5章24節はエノクの最後について次のように記している。
「こうしてエノクは〔まことの〕神と共に歩み続け、そののちいなくなった。神が彼を取られたからである」
ヘブライ人の手紙はこの出来事について、
「信仰によって、エノクは死を見ないように移され、神が彼を移されたので、彼はどこにも見いだされなくなりました。彼は、移される前に、神を十分に喜ばせたと証されたのです。」(11:5)
と説明している。
また、コリント人への第二の手紙12章には使徒パウロの特異な体験が記されている。
「2 わたしはキリストと結ばれたひとりの人を知っています。その人は十四年前に−それが体においてであったかどうかわたしは知りません。体を出てであったかどうかも知りません。神が知っておられます−そのような者として第三の天に連れ去られました。
4 その人はパラダイスに連れ去られ、人が話すことを許されず、口に出すことのできない言葉を聞いたのです」
このエノクとパウロの経験したことについて1987年1月15日号は次のようなコメントを載せている。
「『信仰によって、エノクは死を見ないように移され(た)』のです。同様に、パウロもクリスチャン会衆の将来の霊的パラダイスの幻を与えられたためと思われますが、移されました。つまり『パラダイスに連れ去られ』ました。(コリント第二12:14)そうすると、エホバが敵の手が届かないようにエノクを死の眠りにつかせたとき、エノクも、来るべき地上のパラダイスの幻を見ていたのかもしれません。」(p.12、8節)
パウロはパラダイスを見た。同じように、エノクもパラダイスを見ていたに違いない。このように述べる根拠はたった一つしかない。「移された、連れ去られた」という動詞一語である。エノクは「移された(transferred)」同様に使徒パウロも「移された(transferred)あるいは、連れ去られた(caught away)」ので、パウロ同様エノクもパラダイスを見ていたに違いないという論議の組み立て方である。
70人訳が創世記5:24で用いているギリシャ語動詞はヘブライ11:5に対応しているが、ギリシャ語本文の方は、コリント第二12:2,4とヘブライ11:5で全く同じ動詞を使っているわけではない。同意語、同義語が用いられているにすぎない。
実際のところ日本語で考えてみても、「連れ去られた、移された、運ばれていった、取り去られた」といったところで、多少のニュアンスの違いこそあれ、意味はそんなに大きく変わるわけではない。だいたい同じような内容を指している。しかし、たとえそうではあっても、「同じような動詞が使われているから同じようなことを経験していたに違いない」と考えるかというと、まず普通はそう単純には考えないと思う。字義訳に対する信仰のようなものがなければ、これは無理な論理であろう。
動詞一語で論理を組み立てる、いかにも字義訳らしい、字義訳主義的だと感じさせられる。ここまでくると、もうほとんど字義病ではないかと思う。
聖書の中で名前の上げられている天使は二人だけである。一人はマリアにイエスの受胎を告げに来たガブリエル、そしてもう一人は天使長ミカエルである。このミカエルが誰であるかについては意見が分かれている。
聖書外典のトビト書12章15節には、
「わたしは、主の栄光のみ前にはべり、奉仕する、7人の天使のひとり、ラファエルです」
と記されている。それで、ミカエルとはこのラファエルやガブリエル同様、神の前で特別な奉仕をする7天使の一人ではないかというわけである。バビロン補囚後のユダヤ人が天使論を展開したときにはこのように考えたという。
モルモン教会は、ミカエルとは後代の啓示によって霊界に戻ったアダムであることが明らかになったと述べているが、ものみの塔協会は、ミカエルとロゴス、イエス・キリストは同一人物であると説明している。
神の救いを待ち望む人々にとって、ミカエルは非常に重要な存在である。世界の裁きとなる大艱難のとき、神の民を救うのはほかならぬミカエルであるとダニエル書12章1節は預言しているからである。
「そして、その時に、あなたの民の子らのために立つ大いなる君ミカエルが立ち上がる。そして、国民が生じて以来その時まで臨んだことのない苦難の時が必ず臨む。しかしその時、あなたの民、すなわち書に記されているものはみな逃れ出る」
読むと明らかなように、ミカエルが立ち上がるのと苦難の時が臨むのは同じ時になる。苦難の時とはマタイ24章21節の「大艱難」に相当すると考えられているので、ミカエルが立ち上がる時は同時に大艱難の時でもある。そこで問題はこれが「いつ」になるかということであるが、「御心が地になるように」という本はその点について、
「『その時ミカエルが立ち上がります』。この意味は何ですか。ミカエルが天で王になる、という意味です。ダニエル書11章の中では、『立ち上がる』という言葉は、しばしば力を取り、王として支配し始めることを意味しています。『ペルシャになお三人の王が立ち上がるでしょう…力のあるひとりの王が立ち上がって支配するでしょう。…しかし彼女の根の芽のひとつは、彼の代わりに立ち上がるでしょう…彼に代わって立ち上がる者は、租税を取り立てるものを栄光の国につかわすでしょう…彼の代わりに卑しむべき者が立ち上がるでしょう。彼には国の尊厳が与えられなかった」。(ダニエル11:2,3,7,20,21また8:22,23ユダヤ人出版教会(ママ)訳)ミカエルは、北の王の最終的な年月中、つまり『その時に』天で王として支配し始めます。その時は西暦1914年であると、神は指定しました。」(p.309、310)
と述べている。
ミカエルが立ち上がったのは1914年であると説明しているわけだが、そうすると、大艱難が始まったのも1914年ということになってしまう。現在だとこれは完全に矛盾することになるが、この「御心」の本が出された当時はまったく問題がなかった。というのは、この頃は1914年からすでに大艱難は始まっていると考えていたからである。
ところがやがて大艱難に関する教義が変更されることになる。1914年に始まったのは一世代の長さを持つ「終わりの日」であって大艱難ではない。大艱難とは終わりの日の最終部分を指す。それは大いなるバビロン(偽りの宗教−ものみの塔協会によれば自分たち以外は皆偽りの宗教)の滅びによって始まり、ハルマゲドンの戦いで終わるごく限られた期間の出来事をいう。大艱難が全世界を襲うのはまだ将来のことである。
このように大艱難に関する教義を変えてしまうと、困った問題が一つ生じてくる。ミカエルはすでに何十年も前に立ち上がったのに、大艱難は一向に始まらないということである。ミカエルが立ち上がったとされる1914年からもう70年以上が過ぎ去ってしまった。
この「時」のズレをどうするかという問題に、ものみの塔協会が初めて答えたのは1986年の地域大会であった。北海道で開かれた大会のテープを聞いてみると、「封印を解かれた神聖な奥義は、平和の確かな希望を与える」というプログラムの中で、「ミカエルが立ち上がったのは『1914年』ではありません」と講演者は確かにはっきり宣言しているようなのだが…
教理が調整されるこうしたプログラムは、必ずものみの塔誌に載せられるのが慣例になっている。なかなか出てこないな、どうしたんだろうと思っていると、ついに、1987年7月1日号に登場した。遅れたわけが分かった。「御心」の本と大会の宣言の調整を図っていたのである。
今まで述べてきた見解を変えるのは、やはりまずいと考え直したようである。7/1号はものみの塔協会の苦労が忍ばれるような記事である。「ミカエルが立ち上がったのは1914年です」という見解と、「ミカエルが立ち上がったのは1914年ではありません」という宣言の両方の顔を立てようというのである。
それにしてもこういう調整の仕方は本当にものみの塔協会らしいと思う。調整したなどとは一言も述べてない。いかにも新しい啓示がありましたとうようなスタイルを取っている。しかも多くの人の記憶が薄れてくるような時期にさりげなく変えているのである。
以下は少々長いが7月1日号からの引用である。
…み使いは『立つ』という語を二度用い、「そして、その時に、あなたの民の子らのために立つ大いなる君ミカエルが立ち上がる」と述べています。(ダニエル12:1)イエスが「立ち上がる」という言葉にはどのような意味があるのでしょうか。また、イエスがすでに「〔ダニエルの〕民の子らのために立(って)」いるとすれば、どのようにして「立ち上がる」ことができるのでしょうか。
…その時は、「定めの時」である1914年に到来しました(ダニエル11:29)イエスはその年に、神の王国の統治する王として即位され、み使いの頭ミカエルとして、直ちにサタンを天から投げ落としました。(啓示11:15;12:5-9)そのようなわけで、イエスは1914年以来、王として『立って』おられます。
…では、すでに『立って』いるイエスがその時に「立ち上がる」とはどのような意味ですか(ダニエル12:1)それは、イエスの支配権が言わば新しい局面を迎えるということです。その時イエスは、『ダニエルの民』が人間の政府の手によって絶滅させられないよう、際立った方法で彼らを救うための行動を起こされます。(エゼキエル38:18,19)ここで言及されている「時」とは、北の王が神の民の霊的地所を脅かす、北の王と南の王の「終わりの時」のことでしょう。(ダニエル11:40-45)その時まで、イエスの支配権を真剣に受け止めてきたのは地上の忠実な臣民だけです。(詩編2:2、3)しかし、今度は「主イエスが…表し示される」時となり、すべての人がイエスの王権を認めざるを得なくなるでしょう。(テサロニケ第二1:7、8)その時には、反対する勢力全体が滅ぼされ、その後にイエスとその共同支配者による千年統治が続きます。千年統治の期間中は、王国が人類を治める唯一の政府となります。(p.18、19)
ダニエル12章1節には「立つ」という語が二回使われているので、ミカエルは二度立ち上がる。一回目は1914年、二回目は大艱難のとき。しかも、北の王と南の王の最後の抗争、及び北の王の滅びの時を受けている「その時に」という言葉は1914年の「立つ」ではなく、大艱難の時の「立つ」にのみかかると考えるわけである。このように教義を組み立てると、今までの矛盾はすべてなくなる。
しかしながら、これもいかにも字義訳新世界訳らしい教義の立て方ではある。
まず問題となるのは、この聖句の二か所で使われている「立つ」という語が、どうしても両方とも「立つ」でなければならないのかという点である。新世界訳と同じように訳している聖書もあるが、他の幾つかの翻訳では
「その時、あなたの国の人々を守る大いなる君、ミカエルが立ち上がる」(新改訳)
「そのとき、ミカエルが、立ち上がる。彼は、主の民の子らを守る偉大な君主である」(バルバロ訳)
「At that time Michael, the great prince who protects your people, will arise」(NIV)
となっており「立つ」は一カ所、あとは「守る」である。
ここで「立つ」と訳されている原語のヘブライ語「アーマド」には、「立つ」だけでなく「守る」「奉仕する」「踏み止まって防戦する」などの意味があるので、どう訳すかは所詮解釈の問題になる。
さらに、「立つ」が二回あったとしても、果たして両方とも「厳密に預言的な意味を有する」と考えねばならないのかという疑問が生じてくる。
新世界訳が「民の子らのために立つ」と訳しているところは、「民の子らの上に立つ」と訳すこともできる。そういうふうに解釈すると、ミカエルはみ使いがこの預言をダニエルに伝えたその時点で、すでに「ダニエルの民の上には立っていた」と考えることができる。つまり、初めの方の「立つ」は預言的な意味を持っているとはみなさないということである。
また、前置詞は「上に」でも「ために」でもどちらでもよいが、「立つ」の時制を未来形に限定しなければ、必ずしも1914年までミカエルに待ってもらう必要もなくなる。「民の上に立つ」を「監督する、治める」…何のために…「民を守るために」と考えれば、先に引用したような訳になる。
この解釈にはかなりの有力な根拠がある。ダニエルに神の言葉を悟らせるためにやってきた亜麻布を着た人は、彼に次のように語っている。
「しかし、ペルシャの王土の君が二十一日間わたしに逆らって立ちつづけた。すると、見よ、主だった君のひとりミカエルがわたしを助けに来た。それでわたしはそこにいて、ペルシャの王たちの傍らにとどまった。
しかしわたしは、真実の書の中に書きとめられた事柄をあなたに告げる。これらの事に関してわたしを強く支えてくれる者は、あなた方の君ミカエルのほかにいない」(ダニエル10:13、21)
このみ使いの説明から、ミカエルはダニエルの民の上に立つ君であり、またイスラエルの民の救いのためにはすでに立っていたことが分かる。当然のことながら、立たなければ助けに出て行くことはできないからである。
では、一体いつからミカエルは「立って」いたのであろうか。この預言が語られるはるか以前からである。君として、さらに民の救いのためであれば、少なくともモーセの時代にはすでに立っていたことになる。ユダは次のように記しているからである。
「しかし、み使いの頭ミカエルは、悪魔と意見を異にし、モーセの体について論じ合った時、彼に対しあえてあしざまな言い方で裁きをもたらそうとはせず、ただ、『エホバがあなたを叱責されるように』と言いました」(ユダ9)
約束の地を目前にして、モーセがネボ山で死んだときのことである。悪魔と対峙して神の民のために戦うミカエルの姿が浮かび上がってくる。
したがって、ものみの塔協会の「ミカエルは立って立ち上がる、すなわち、二度立ち上がる、一回目は1914年、二回目は大艱難」というこの教義は、二個所の動詞を両方とも「立つ」と訳し、どちらも将来に適用されるという条件付きでなければ成り立たないものである。
エホバの証人の大会で、恒例の行事になっているものに集団バプテスマがある。
バプテスマを希望している人はまずステージ中央の最前列に設けられた特別の席に座り、バプテスマの話に耳を傾ける。話の終り近くになると、講演者は希望者全員に起立することを促し、次のような二つの質問に大きな声で「ハイ」と返事することを求める。
講演者の求めに応じて、「はい」と答えた人は出席者の拍手や賛美の歌に送られ、バプテスマ会場へと向かうことになる。
このような公の宣言を行なうという儀式は一体何を根拠に取り決められたのであろうか。よりどころとされている聖句はローマ人の手紙10章10節であるが、この教理にも一つの字義にこだわるという字義訳的な考え方が色濃く反映されている。新世界訳の訳文は次のようになっている。
「人は、義のために心で信仰を働かせ、救いのために口で公の宣言をするからです。」
キーワードは「公の宣言」という言葉であるが、この語からどのようにバプテスマの誓いの儀式が出てくるかについて1973年2月15日号は、
人が「口で救いのために公の宣言をする」のはいつでしょうか。それは、献身した信者が『父と子と聖霊との名によって』バプテスマを受ける前であり、またそうでなければなりません。(マタイ28:19、20;使徒16:31-33;17:33;19:1-7)王国行間逐語訳や他の聖書翻訳が示しているように、ここで言う公の宣言とは、ある意味での告白です。(改訂標準訳;モファット訳;エルサレム;アメリカ標準訳)バイイングトンの翻訳とアメリカ訳はこれを「承認」と訳しています。この告白もしくは承認とは、今や献身した信者としてのわたしたちが、水のバプテスマをつかさどるクリスチャン奉仕者に対して、またはその前で口頭で行なう事柄なのです。(P.120)
と述べている。
しかし結論から先に言えば、これはあくまでも、ものみの塔協会なりの解釈であって、聖書そのものから必然的に導き出されてくるという教理ではない。この儀式の取り決めが聖書的に成り立つためには少なくとも次の二つの仮定が必要になってくる。
この仮定は任意でしか成り立たない。というのは、「公の宣言」と訳されているギリシャ語「ホモロゲイタイ」には公の宣言の他にも多くの意味があるからである。
「承諾する」という訳でも良いことは、ものみの塔誌でも述べられているが、さらにこの語には「告白する、約束する、同意する、賛美する」などの意味があり、「人に対してなされる公の宣言」というのはごく限られた意味にすぎない。
救いをもたらすのは人間ではなく、神とイエス・キリストである。ローマ人の手紙はそのことを再三にわたって強調している。したがって、その観点から宣言の意義を考えると、真に価値があるのは神に対してなされる心の宣言であって、決して人や組織に対してなされるものではないということになる。儀式的な宣言より実際の生活を通しての宣言の方がはるかに重要であると言える。
ものみの塔教会が行なっているバプテスマの司会「者」や組織に対してなされる宣言に、いったいどのような真の意義があるのか、また神の目から見て本当にそのような儀式が必要かは大いに疑問である。霊的な意義から言えば全く不用の取り決めであろう。
統治体とはエホバの証人の最高指導機関の名称である。定員は18名になっているが、現在は13名で構成されている。全世界のエホバの証人の頂点に立ち、いわゆる権力のトロイカ、つまり、決定権、人事権、予算権を一手に握っているのはこの統治体である。
本来、キリスト教の精神とは相反する言葉を持ち出してきて、その組織にとって根幹となるような教理を組み立てるというのは、なかなか大変なことである。そういう教理を維持しようとすれば当然のことながら、かなり無理をしなければならなくなるし、組織には時と共に歪みが生じてゆく。現在の統治体にかかわる様々な問題は、統治体という教理自体が抱える矛盾の必然的な結果であろう。
さて、統治体に関してしばしば問題になるのは、まず、ものみの塔教会も認めているように、聖書の中にこの統治体なる言葉が出てこないということである。さらに、統治体という名称がキリスト教にとって果たして適切かどうかという点もある。「教えと行動の基準はすべて聖書に基づいて定める」と銘打っているものみの塔協会にとって、もし聖書的根拠がないなどということにでもなれば大変な問題であろうと思うが、本人たちがそのように考えることはないだろうからこれは余計なことかもしれない。
以下、この教理がどのように組み立てられているか、また、なぜ統治体の教理に聖書的な根拠はないといえるかを論じることにする。
ものみの塔協会刊行の聖書には、新世界訳の他に新約の部分だけを逐語訳した「王国行間逐語訳聖書」というのがある。統治体(The Governing Body)そのものズバリではないが、統治(govern)という語はその逐語訳の中に出てくる。この「統治」という語から「統治体」という名称が取られている。
17
Πειθεσθε τοισ ηγουμενοισ (Be you obeying) (to the (ones)) (governing) υμων και υπεικ ετε, αυτοι (of you) (and) (be you yielding under) (very (ones))
その語が出てくるヘブライ13章17節を下に引用する。
「あなた方の間で指導の任に当たっている人たちに従い、また従順でありなさい」
「Be obedient to those who are taking the lead among you and be submissive,」
日本語版で「指導の任に当たっている」英語版で「are taking the lead」に相当するところが、行間逐語訳では「governing」になっている。聖書に出てこないという問題は、このように「王国行間逐語訳」に登場させることによって解決したのである。
ここで用いられているギリシャ語は「ヘゴウメノーン」であるが、その訳語を「govern」にしたところが味噌である。逐語訳で「govern」を選んだということは「ヘゴウメノーン」のより字義に忠実な翻訳が、「統治する」であると主張していることを意味する。つまり、「統治体」という名称はより聖書本来の字義にかなった名称だというわけである。
さらに、ものみの塔誌1973年2月15日号P.126,127には、簡単に要約すると、以下のような点が統治体の教理の根拠としてあげられている。
要するに、「初期キリスト教には諸会衆を統治する人々がいた、だから、統治体という名称およびその取り決めは聖書的なものである」というのがこの論理の骨子である。
本当にこの主張通りかどうか、この論理が正しいかどうかを確かめるには、次の質問を考慮すればはっきりする。
この質問の答えのカギとなるのも、やはり「統治」という言葉の意味である。「統治」の意味しだいでは「いた、調和する」とも言えるし、あるいは「いなかった、調和しない」ということにもなる。
まず、日本語の統治を調べてみると、
「スベヲサムルコト」(大言海)
「主権者が国土・人民を支配すること」(学研国語大辞典)
となっている。「統治」という言葉には「水先案内をする、導く」といった意味はない。
では、英語の「govern」はどうだろうか。
「rule or control with authority, conduct policy and affairs of, be in charge or command of, etc.」
(THE POCKET OXFORD DICTIONARY)
(研究社英和大辞典第五版)
- 治める、支配する、統治する
- (人、行動を)支配する、左右する
- (原則、政策などを)決定する、律する
- 政治を行なう、執務を取る
- その他
日本語の統治と同じように、英語の「govern」にも「水先案内をする、導く」という意味はない。「水先案内をする、導く」という意味をもっていたのは、語源の「グベルナーレ」や「クベルナオ」であって、「govern」や「統治」ではない。
「リデルとスコットの希英辞典」によれば、新世界翻訳委員会が「govern」と逐語訳したギリシャ語「ヘゲオマイ」は、
となっており新約ギリシャ語辞典(岩隈直著)によれば
となっている。他の辞書もほとんど同様で、この語を「govern」と訳さねばならぬ必然性はまったくない。
このギリシャ語の名詞形「ヘグーメノス」には確かに支配者、君主、統治者の意味もあるが、クリスチャン会衆内の人々を指す場合は、そういう用語は使わないのが普通である。神の会衆、キリストの会衆なのだから、当然その程度の謙虚な姿勢は持つべきであろう。逐語訳であればむしろ、「統治」よりも「導く、案内する」にしなければならないはずである。神の会衆について述べたヘブライ13章17節で「govern」を選んだのは、ものみの塔協会の好み、完全に恣意的な判断である。
繰り返すが「govern」はあくまでも「支配する」であって、決して「導く」ではない。したがって、初期クリスチャン会衆の中に「導く、水先案内をする」人々はいても、「統治する」人々はいなかったとはっきり断言することができる。神の会衆を「統治しようとする」のは、神の羊を支配しようとする邪な企てであり、そうしようとする人は真のキリスト教から背教した人だけであった。
さらに、この「統治体」という称号は真のキリスト教の精神とも、キリストの指示とも真っ向から対立するものである。なぜならキリストは次のように述べているからである。
「8 しかしあなた方は、ラビと呼ばれてはなりません。あなた方の教師はただ一人であり、あなた方はみな兄弟だからです。
9 また、地上のだれをも父と呼んではなりません。あなた方の父はただ一人、天におられる方だからです。
10 また、『指導者』と呼ばれてもなりません。あなた方の指導者はキリスト一人だからです。
(マタイ23:8,9,10)
「復活したイエス・キリストは地上の霊的なイスラエル人で成るご自身の会衆の天的統治者です。このかたこそ、ミカ書5章2節から引用された次のことばがあてはまるかたなのです。『そして、ユダの地のベツレヘムよ、あなたは決して、ユダの統治者たちの間でもっとも取るに足りない〔都市〕ではない。治める者〔ギリシャ語、ヘゴウメノス〕があなたから出て、わたしの民イスラエルを牧するのである』」。(マタイ、2:6、新)書き記された神のことば、聖書によれば、イエス・キリストは今日の地上のエホバの証人の世界的な集団を、聖霊によって、また、「統治する」もしくは『指導の任に当たる』(ギリシャ語、ヘゴウメノーン)』長老たちで構成されている見える統治体を用いて統治しておられます。一へブル、13:17、行間逐語訳;クリスチャン・ギリシャ語聖書新世界訳、1950年版」
「キリストは見える統治体を用いて統治します」と言っても、キリストは目に見えないのだから見える者が支配することになるのは必然的な結果であろう。キリストの支配と、「統治体」の支配をすり替えるところに、この教理の欺き、ごまかしのからくりがある。
こうした統治の実態は最新号のものみの塔誌にもよく反映されている。1987年8/1号、第一研究記事の出だしには
「エホバの証人は自分たちの指導者として、どんな人間をも受け入れていません。彼らの組織的な機構には、ローマ・カトリック教会の法王、東方正教会の総主教、キリスト教世界の他の諸教会や分派の指導者に相当する人は存在しません。」(p.10)
と記されているが、その後の方ではしっかりと
「…集まり合っていた統治体はその話を聞いてからパウロに明白な指示を与え、『わたしたちが告げることをしてください』と述べました。統治体は、パウロが神殿に行き、…という事実はないことを公に実証するよう命じました。」(p.14、15節)
「すべての長老は当然ながら、キリストが霊と、霊によって生み出された統治体の成員を用いて働かせている、その管理、指導、指図の『右の手』に従うべきです。」(p.19、14節)
と述べている。
記事の本音が後者の方にあることは言うまでもない。簡単にいえば「余計なことを言わずに黙って命令を聞け、たとえ分からなくとも統治体の指示に従え、パウロだって統治体の命令に従ったのだ」ということであろう。
「エホバの証人は自分たちの指導者として、どんな人間をも受け入れていません」と書きながら、そのすぐ後で堂々とそれを否定するような文章をさりげなく書く…自己矛盾を感じないのだろうかと思うが…もっとも「統治体は人間ではない」か「エホバの証人は統治体が人間であれば絶対に従わない」とすれば、この記事には何の問題もないということにはなるが。果たして実際はどうであろうか。
結局この教理は、昔の意味の一つを持ってきて今の意味をカモフラージュするという、典型的なすりかえ論理によって成り立っている教理である。現在そういう意味は全くないにもかかわらず、昔は「導く、案内する」という意味があったから正しいというのである。それでも実態が宣伝の通りであればまだいいのであるが、実質は「統治体」という名称と見事に一致しているわけだから、これは実に悪質な教理である。まさに紛れもなく「統治する、支配する人々」というのが統治体の真実の姿である以上、二重の欺きと言えよう。
先に上げた「パウロとエノク」「ミカエル」などの教理は意味合いを変えれば幾つかの考え方が成り立つと言うものであった。それらの教理は様々な余地を認めたとしても、それほど大きな弊害があるというわけではない。しかし、この統治体の教理だけは別である。この教理は「組織支配、組織バアル」の元凶になっているので、あえて、統治体の正当な聖書的根拠は全くないと断定しておく。
今まで見てきた事例からも明らかなように、訳語の選択にはある程度幅のあることが分かる。好むと好まざるとにかかわらず、訳語が定められているような箇所もあるが、訳者の信条によっては好きな訳語を選べるというところもある。そういう場合は、まず組織ないしは個人の主張したい教理が先に合って、それに都合のよい訳語を選んでくるというのが普通のやり方になる。おそらく「統治体」の教理などは、このスタイルの代表的なものであろうと思う。
また、あるモードで聖書を訳したら、「こういう教理も作れるのではないかと改めて気がついた」というような場合も考えられる。たぶん字義訳モードによる教理、「ミカエルは二度立ち上がる、パウロとエノク」のようなケースがそうであろう。
これは次のことを意味している。つまり、まったく白紙の状態で、何ら特定の教義、信条を入れずに聖書を翻訳することは不可能だということである。言い換えれば、誰もが納得できるような仕方で訳語を統一することは無理だということになる。それは逆に、教義を統一することもまた不可能であるということにつながってゆく。
使徒パウロは、
「体は一つ、霊は一つです。それは、あなた方が自分たちの召されたその一つの希望のうちに召されたのと同じです。主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つです。」(エフェソス4:4:5)
と語り、また、
「あなた方すべての語るところは一致しているべきです。あなた方の間に分裂があってはなりません。かえって、同じ思い、また同じ考え方でしっかりと結ばれていなさい。」(コリント第一1:10)
と勧めているが、特定の教団の自己満足を除けば、今のところこれは理想にすぎない。
現在のキリスト教世界の実状は、一致がいかに困難な課題であるかを物語っている。そういう主旨の話し合いが歴史上何度かなされ、現在も試みは続けられているようであるが、成功した例はほとんど聞いたことがない。おそらく既存のキリスト教のスタイルやモードのままでは、何度やってみても不可能なことではないかと思う。
教義上重要な訳語を統一できない原因としては、様々な理由が考えられるが、根本的な問題としては主に次の三つの点を上げることができる。これは世界中で様々な委員会訳や個人訳が出版されている本質的な理由にもなる。
2については前の章でも詳しく取り上げたので、ここでは省略することにする。
世界各国で出版される各種翻訳の原本になっているのはヘブライ語本文やギリシャ語本文(新世界訳の場合ヘブライ語の方はキッテルの「ビブリア・ヘブライカ7版、8版、及び9版に載せられたレニングラード写本B19A」ギリシャ語の方はウェストコットとホートの本文)であるが、これはまだ全面的に統一されるには至ってない。程度の違いこそあれ、実状は聖書の出版状況とたいして変わらない。
ヨブ記の研究者として知られるロバート・ゴルディスによれば、ヨブ記の本文はまだ最終的な確定ができないという。70人訳とマソラ本文にはかなりの相違があるので、ヘブライ語本文には二つの系統があるのではないかと推測されている。何千というギリシャ語写本も完全に同じものはないといわれるほど、多くの相違点を抱えている。写本家はしばしば「証拠がなくて当惑するのではなく、証拠がありすぎて当惑しているのである」と語る。
ものみの塔協会は
「古代の文献で、聖書ほど勤勉に写本され、再写本されてきたものはありません。そのように写本は繰り返し行なわれましたが、常に最新の(ママ)注意が払われました。写字生の誤りはごくわずかで、それもささいなものでした。ですからそれらの写本を比較することにより、神の霊感のもとに書かれた原文が確立されました。聖書写本の指導的権威であったフレデリック・ケニヨン卿は、『聖書は実質的に、書かれた通りにわれわれにまで伝えられたということを疑う根拠は、いまや取り除かれた』と述べました。今日でも、聖書の全巻またはその一部の手書き写本が、1万6000ほど、存在します。その中にはキリスト前2世紀の写本で今なお残っているものもあります。そればかりではありません。聖書は最初ヘブライ語、アラム語、ギリシャ語で書かれましたが、それらの言語から、世界にあるほとんどすべての言語に正確に翻訳されてきました。」(「見よ」p.7、10節)
と述べているが、この引用の仕方、コメントは宣伝一流のやり方であって決して真実ではない。外ならぬフレデリック・ケニヨン卿自身が「聖書の生い立ち」という本の結びの中で次のように記しているからである。
「到達したと思われる全般的な結論をいえば、新約の原初の本文を発見しうる王道はない、ということである。70年ほど前、ウェストコットとホートはそういう道を発見したように見え、そこで、明らかな写本家の誤りを別にすれば、自らの責任においてヴァティカン写本から出発すべきだと思われた。だが、発見と批評的研究の両過程において、ヴァティカン写本とその一族が、原初のみなもとから何の汚れもなく伝えられてきた伝統的な流れを示すと信ずることは、しだいに困難を増していった。シナイ写本とヴァティカン写本に現れたあらゆる特徴がよく一致することは、これらが、明確な原則に基づく選別された諸典拠を巧みに編纂した結果であることを、明白に物語っている。それゆえ、校訂の年代とその文体よりみて一応権威は尊重するが、西方・シリア・カイザリア等に一家族を見出した初代の諸本文には、ウェストコットやホートが考えた以上の、考慮を払わねばならないであろう。だがそれでもなおアレクサンドリア本文が、全体として、聖なる書物の原初の形に最も近いものを示している、と信じ得ると思う。とはいって、これには個人的に先入観が大きな役割を演ずる余地があるから、人によって、さまざまな見解がとられよう。」(p.159、160)
ウェストコットとホートが拠りどころとしたのは、主としてシナイ写本とヴァチカン写本である。このウェストコットとホートの本文を新世界訳は定本にしているわけだが、ブルース・M・メツガーは「新約聖書の本文研究」という本の中でこの本文について、
「ウェストコットとホートの作品に関するこのかなり長い記述を終るに当たり、学会の意見は彼らの批評版が真に画期的であったことを、ほとんど一致して認めていることを述べておこう。彼らはその当時に入手できた情報によって得られる最も古い最も純粋な本文を提供したのであった。その後の写本の発見は、あるグループの証言について再調整を必要とするに至ったが、しかし彼らの批評原理と手続きが一般的に妥当することは、今日も、本文批評家に広く認められている。」(p.154)
と述べて、ウェストコットとホートの業績を高く評価しているものの、次のようなコメントを付け加えている。
「ウェストコットとホートの批評ですら主観的である。というのは、まず彼らは彼らが従うべき方法を選択、決定し、そののち、いわゆる中性型本文は一般に他の型の本文に優先すべきであると判断しているのである。」(p.155)(中性型本文とはシナイ写本とヴァチカン写本を指す。)
まだ、神が書かせたと言えるほどの決定的な本文はない。聖書の最終的な原文は確立されておらず、今なおより正確な本文を求めて多くの人々が努力を続けている。ただ、現存する写本間の違いは主要教理に影響を与えるほどのものではなく、重大な意味上の相違をもたらすようなものもほとんどないということは多くの写本かが認めていることである。現在の本文が神の言葉として信頼に値するかどうかについては、おおむね、肯定的な見解で意見の一致がみられるようである。
聖書翻訳については、ものみの塔協会自体他の翻訳を不正確であると批判しているし、加えて2〜4章で例証した通り、いかに聖書翻訳が不正確になり得るかは、何よりも新世界訳そのものが如実に物語っている。
結局どの聖書、どの本文を取ってみても、決定的なものは見当たらないわけだが、しかし、これは決して消極的に評価すべきことではないと思う。むしろ現状では歓迎すべきことであろう。様々なスタイルの聖書翻訳が出版されているということは、特定の誤りや一方的な見解が押しつけられるのを防ぐ上で大いに役立っているからである。
「多くの翻訳があっても聖書は一つです。神が伝えようとしていることは、結局は同じことです。」これもよく言われることであるが、それでは本当に、誰の目から見ても聖書の伝えていることは一つである、神が人類に伝えようとしているメッセージは一つしかないと言いきれるのかといえば、残念ながら現実はそうではない。数多くの教義とそれを唱導する何百と言う宗派に分裂しているのが、今日のキリスト教の実状である。
要するに述べていることが一義的でハッキリしていれば、解釈などいらないわけであるが、聖書はそのような形態の本にはなっていない。一見すると、混沌としているのではないかと思えるくらいの多様性を内包している。聖書が解釈を待つ本であるとよく言われるのはこうした理由による。これは言いかえれば、聖書の解釈に絶対的な基準を設定することが、いかに難しいかと言うことである。それぞれの宗派が自分たちの教えこそ絶対的な真理であると主張しているにすぎない。極端な言い方をすれば、解釈しだいで大抵の教理は作れるということである。
自分たち以外はみな間違っているので考慮する必要はないという狭量で独善的な態度を捨てて、現実を直視し事実を事実として受け入れるなら極めて本質的な問題に行き当たる。つまり、
「聖書解釈の絶対的な基準はない」
という問題である。
この事実を受け入れることは絶対的な真理の否定にもつながるので、「真理は一つである」と考えている人にとっては深刻な事態を招くことになるかもしれない。しかし、事実は事実、現時点で絶対的な基準系を設定するのは無理である。もっとも不可知論者からすれば、何をいまさらということになるかもしれないが。
まだ知識が足りないから、研究が不充分なので、そのような基準系を見出すことができないのであって、今後さらに聖書の調査と探求が進めば、それも明らかになるのではないかと考える人もいると思う。しかし、別に可能性を100パーセント否定するわけではないが、おそらく無理であろう。というのは、この問題は単なる知識や理解のレベルではなく、宗教上の真理そのものが持つ性質に起因しているからである。
物理学や電子工学、医学などの真理は、誰でもその真偽を何度でも実験して確かめることができる。観測の限界が問題にされるような領域を除けば、普遍的で客観的な答えを出すことのできるものである。ところが、宗教上の真理はそうではない。道徳や戒律、規則であれば、守ってみて、本当に人を幸福にするものなのか、人間にとって必要なものなのかどうか、確かめることができないわけではないが、それでもかなりの個人差がある。根本的な教義になると実験不可能なものばかりである。
神の名はエホバか、エホバこそ生きて活動する唯一の存在か、それとも三位一体か、キリストは将来目に見える仕方で再臨するのか、それともすでに1914年から再臨しているのか、死者は復活するのか、天国や地獄はあるのか、これらの問いに対する客観的な答えはまだない。絶対的な基準系がない以上、絶対的な答えは出せないのである。
ただそうは言っても、すべての可能性が否定されてしまったというわけではない。たった一つだけ、絶対的な基準系が確立される、あるいは明らかになる道が残っている。
実はキリスト教の場合、教義上だけならばこの問題についての結論はすでに出ている。最終的には神自身がその基準になるとされている。つまり神が自分で答えを出すということである。ものみの塔協会でいえば、それはエホバになる。
原則的には、本文や翻訳そして聖書解釈の重大な問題が生じたとき、直接神が答えを出してくれれば論争は生じないということになるのだが、キリスト教の歴史が示すように、そういうことは起きたことがない。誰もが聞けるような天からの声はなかったのである。預言の時節ではなかったのか、あるいは自らの目的と会わなかったのか、残念ながらエホバもキリストも現れてはくれなかった。ただ今までなかったということは、必ずしも、今後も絶対にないということを意味しているわけではないので、可能性としては残っていると言える。
今のところ、神とキリストは単なる教義上の存在にすぎないので、現実には別のものがそのポジションに就いている。つまり、その組織の中で最終的な権威、実質的な権威を有する者が、同時に解釈の決定権をも合わせ持っているのである。多くの組織の通常の形態、運営はそうなっている。もちろん、あくまでも名目上は神やキリストにあるということになってはいるが。キリスト教の多くの宗派、教団を見ていると、誰が解釈の権限を有するかは大体三つのタイプに分類できるようである。たぶんこれは宗教全般にも当てはまるのではないかと思う。
絶対的な解釈や狭義はないので、神とキリストを信じていれば細かい教理のレベルは個人の信仰に委ねるという考え方である。これを極限まで押し進めると一人の教会、教会不要論になる。ただ、弱い人はそこまで言われると、かえって不安になるかもしれないが。
非常にリベラルで自由であり、組織の束縛をほとんど感じさせないくらい居心地は良いが、インパクトに欠けるきらいがなくもない。組織としての差し迫った具体的なビジョンがないので信仰のエネルギーはそれほど強くない。「こ れは絶対に真理だ」というものがない以上仕方のないことであろう。確かなものを得たいという人にとっては、おそらく物足りない感じが残るのではないかと思う。
カリスマ的な存在が自らをメシア、預言者と称して最終的な権威となるが、人物崇拝の問題が生じやすい。
新しい教団が組織される初期においてはほとんどがこの形態を取る。組織としては非常にエネルギッシュであるが、裏を返せば狂信的になりやすい体質を持つ。個人の体験が基準とされるので論理的一貫性はあまり期待できない。
現在のエホバの証人の統治体のように、特定の人物ではなく組織が権威の象徴となる。こういう機構はどうしても官僚的になりやすい。極端になれば、取り決め至上主義、パリサイ的体質ができあがる。
ものみの塔協会も、創始者のC・T・ラッセルの時代は個人依存型であったが、組織が拡大するにつれて組織主導型へと移行した。カリスマ的なシンボルを立てている場合はあっても、ほとんどの組織宗教が最後に落ち着くのはこの型である。
実際のところ、2や3の教団の幹部にとっては神やキリストが現れないということは、非常に都合の良いことではないかと思う。いつまでも現れなければ、いつまでも神とキリストの名を借りて組織支配を続けることができるからである。
1987年8/1号のものみの塔誌(p.20)は、
このように、キリストが「体である会衆の頭」であられることを聖書から読むとき、わたしたちはキリストが名目だけの頭ではないという確信を抱けます(コロサイ1:18)。わたしたちは自分の経験から、キリストが実在する積極的な頭であることを理解しています。
と述べてはいるが、今本当にキリストが頭として現れたら一番困るのはむしろ彼ら自身の方であろう。心から喜んで統治権という特権を手放すとはとても思えない。
ものみの塔協会に限らず、実質的な意味で地上に絶対的な権威を設定している組織(教義上は別)はどうしても無理が来る。本来は、天にいる神とキリスト以外、真に絶対的な基準になることはできないはずである。それなのに不完全な人間が絶対権の肩代わりをしようとする、そもそもそれが間違っているのである。
そういう無理をすると、必ず歪みが生じ、論理的な矛盾が露呈してくる。これはある特定の宗教組織の欠陥と言うよりは、特定の宗教モードに内在する構造的な欠陥といえる。ものみの塔協会と似たようなモードを持つ組織は、間違いなく似たような体質になる。
2や3の宗教モードの弊害を痛切に感じた人々は、どうしても1のモードにならざるをえないと思う。現在の組織に、そうしたモードの構造的な欠陥を克服した組織は、残念ながら見当たらないからである。
ただ、キリスト教というのはどうしても世界観がないと成り立ちにくい宗教である。しかも単なる漠然とした世界観ではなくハッキリしたものがないと、全体としてのエネルギーはなかなか出てこない。これは1のモードが持つ本質的な弱点の一つであろう。
一村一品運動式に特定の必要にだけ答え応じるという宗教形態は、キリスト教には不向きである。明確な世界観が真の動機にならなければ、ほかの手段、つまり、情報を遮断して洗脳するとか、特権指向をくすぐるとか、別種の欲望を転化させるなどの方法を取る以外にはなくなる。不節操にも多くの組織はこういう方法を取っているが、いずれも真のキリスト教とは正反対の道である。組織化によるこうした弊害は、基準系をある程度失うことよりもはるかに大きい。しかしながら、それを止めると今度は逆に、慢性的なエネルギー不足に陥るというジレンマがある。教義上だけでなく本当に実質的な意味を持つ具体的な世界観、ヴィジョンの確立が望まれるところである。
地上における絶対的な基準系を否定すると、すぐに生じてくるのは正しい教理、正しい解釈をどうするかという問題である。結局、決定することはできないのではないかと考えるのは、聖書の述べることと調和しない。聖書の解釈に間違った解釈と正しい解釈があること、これはまず絶対に確かなことである。それは使徒ペテロの次の言葉に示されている。
「しかし、〔彼の手紙〕の中には理解しにくいところもあって、教えを受けていない不安定な者たちは、聖書の残りの部分についても〔している〕ように、これを曲解して自らの滅びを招いています。」(ペテロ第二3:16)
使徒パウロが書いた手紙の中の難解な部分を曲解していた、つまり、間違った解釈をしていた人々がいたということは、逆に言えば、正しい解釈があったことを意味している。正しい基準がなければ間違っているとか、反れた、迷い出た、背教したというような表現は成り立たないからである。誤った解釈をすると滅びを招くことになると述べられているので、(ゆえにハッキリ解釈しないほうが安全ではないかというのは少々ひねくれた見方である)クリスチャンにとって、聖書を正しく解釈するということは真剣に受け止めるべき重要な課題である。
キリストが生きていた間は、弟子たちの中でこのような問題は生じなかった。というのは、キリストが「わたしは真理です」と断言して、最終的な権威となったからである。しかし、キリストの死後そのような絶対的な権威を持つ者は存在しなくなった。
ではその後は誰が正しい解釈、誤った解釈の判定を下していたのかといえば、証拠は使徒たちにそういう権威が与えられたことを示している。加えて当時は奇跡的な聖霊の証しもあった。ただ使徒たちに与えられた権限が組織上の絶対権でなかったことは、エルサレム会議で一度決着のついた割礼論争が再燃し、パウロがそれを正すために苦闘していることなどからも明らかである。使徒たちは、「統治体」のように組織上の権限に訴えるのではなく、聖霊の証しと聖書的な論理を証拠として提出している。
現代ではもはや1世紀当時のような使徒職はない。誰が是認されているのかを示す奇跡的な聖霊の証しもない。(霊的な仕方での聖霊の証し、ないしは聖霊による霊的な裁きは今日でもあるが、それを見分けるには信仰の目が必要である。この聖霊の証しはあくまでも個別の義認であって、組織体として義認されるという意味ではない。それゆえ組織を判別すると言う点では、決定的な基準とはならない。)
キリスト教の宗派数もそれこそ一人では調べきれないくらいに増えてしまった。正しい教理、正しい解釈を見出すのはなかなか大変な状況である。「求めよ、されば与えられん」と述べられているので、神とキリストが実在するのであれば決して不可能ではないだろうが、ただし、今の宗教モードのままでやったのでは、遅かれ早かれ不可知論に陥ってしまうと思う。もっとも途中で変質してしまえば話は別であるが。
この面では論理もそれほど当てになるわけではない。絶対的な論理というものはないので、論理だけで正しい解釈を規定することは無理だからである。正しい解釈を見出すためには、総合的な真理の新しいモードが必要ではないかと思う。
真理のモードとは−この答えは1900年以上も昔にすでにキリストによって出されている。そういう意味では別にことさら新しいというわけではないが、より具体的なレベルにおいては、新しいものではないかと思う。
名もないサマリア人の女に語ったキリストの言葉は、非常に簡単なものであった。
「真の崇拝者が霊と真理を持って父を崇拝する時が来ようとしています。それは今なのです。実際、父は、ご自分をそのように崇拝する者たちを求めておられるのです。神は霊であられるので、〔神〕を崇拝する者も霊と真理をもって崇拝しなけ ればなりません。」(ヨハネ4:23、24)
必要な点として上げられているのは、「霊(聖霊及び精神)」と「真理」だけである。律法時代と比べると、実に簡潔なスタイルである。
真のキリスト教の基本的なモードとしてはこの原則だけでもう十分であろうと思う。組織が妙に出しゃばって、余計なものをゴチャゴチャと入れるから複雑になったり、変なものが紛れ込んだりするのであって、何といっても、「Simple is the best」である。この「霊と真理」による崇拝のモードをもう少し具体的に記述すると、以下のようになる。
神とキリストの権威が単なる概念上の、あるいは便宜上のものであってはならない。特定の人間や組織が主人になることが決してないように、明確に神とキリストの領域を設定する必要がある。
少し違う意見を言えば、すぐに背教だ、異端だと騒ぐような組織は論外である。まず、天の判断、聖霊の判断を見るだけのゆとりが必要であろう。
能力や業績、組織の取り決めと健全な動機を比較して、どちらを高く評価するかということが、最大のポイントになる。「神は心を見る方である」(サムエル第一16:7)と述べられているし、「心の純粋な人は神を見る」(マタイ5:8)とイエスは教えたので、どちらが重要かは言うまでもない。
「取り決めではどうなっていますか、誰がそういう指示を出しましたか、あなたは割り当てられたことをすればそれで良いのです。」こういうたぐいの言葉が頻繁に発せられるような組織は、もう終っていると考えて良い。
拡大が至上命令のようになった組織も動機の点では、すでに腐敗している。そうなると、いわゆる健全な動機−神の栄光を求め、隣人愛に基づき−も単に人を集めるための手段、宣伝文句に過ぎなくなってしまう。
宗教指導者の偽善はキリストが最も厳しく糾弾したことの一つである。このレベルの偽善になると完全に意識的なもので、それゆえ、彼らは巧みなスマイルや誉めことばで偽善を覆い隠そうとするのである。この種の能力にたけた人々が、幹部になっていくような組織は最悪である。
偽善的な指導者を持つ組織は、さらに構造的な偽善をも抱えることになる。やれもしない、できもしない、ありもしないことを宣伝するので、組織全体の構造が偽善的になってしまうということである。
まず宣伝の良すぎる組織は避けた方がよい。ほとんどがまゆつばものである。
消費者の利益確保を目的とした法律に独占禁止法というのがあるが、教義の世界にもこれは必要ではないかと思う。
神との関係で言えば、ある個人の信仰に関して最終的な責任と権利を有するのはその人自身である。サマリア人の女に偉大な真理を明らかにしたイエスのように、教義はすべての人に開放するべきであろう。
一部の人が教義を独占するのは、組織支配には便利かもしれないが、成員一人一人の真の成長には役立たないし、また本当の益にもならない。それに、自分たちの教義に確信があるのであれば、すべての人に発言する機会を与えても、少しも困らないはずである。
最初は何でも聞いてくださいというのであるが、そのうちだんだん本音が現れてくる。教え手の自尊心をくすぐる程度の質問ではだめで、ズバリ矛盾をついてみれば一番はっきりする。真理のモードを持っていない組織は、それは信仰の問題ですと言って逃げるか、あの人はふさわしくないとか危険だからといって退けるかのいずれかになる。
教義に関してはものみの塔協会の場合、初代会長C・T・ラッセルの遺言に基づいた取り決めが設けられている。その点について、1987年3月1日号のものみの塔誌は次のように述べている。
「その遺書には次のように記されています。『シオンのものみの塔』の編集上の全責任は5人の兄弟から成る委員会の手にゆだねるように命じる。それらの兄弟たちには、真理に対して最新の(ママ)注意と忠実さを保つよう強く勧めたい。『シオンのものみの塔』誌上に掲載される記事は、すべからく5人の委員のうち少なくとも3人の無条件の賛同を得ているべきである。さらに、どんな記事であろうとも、3人の賛同を得たものが委員会の一人あるいは二人の成員の見解に反することが知られている、もしくはそう思われる場合、そのような記事は、思考と祈りと討議のため発表まで3ヶ月保留するよう強く勧める。それは、この雑誌の編集作業において、可能な限り信仰の一致と平和の絆を保てるようにするためである。」(p.14)
こうして作られた教義は、統治体の権威、ものみの塔協会の権威のもとに、神の教えとして信者に押し付けられることになる。密室で教義が作られ、あとの人は守るだけというのでは、きわめて排他的かつ閉鎖的な教義体系ができあがるのも不思議ではない。
独自の教典や啓示しか受け入れないとか、聖書だけあれば良いというようなモードは失格である。また、現実を直視しないモードも不適格である。もっと積極的にあらゆる分野の真理を取り入れる必要がある。独善的な真理や自己満足の真理であってはならない。
神が備えて下さったのは、決して聖書だけではない。ほかならぬ聖書そのものが詩編19:1、2節で次のように述べている。
「天は神の栄光を告げ知らせ、
大空はみ手の業を語り告げている。
日は日に継いで言語をほとばしらせ、
夜は夜に継いで知識を表し示す」
天地自然の創造者が神である以上、自然界の真理と聖書の真理は調和するはずである。どちらか一方だけに偏るのはいずれも真の理解から遠ざかる。
中世と近代の歴史から学んだように、もし科学が聖書の真理と調和しないのであれば、それは聖書の解釈が間違っている、という判断で十分であろう。ジョルダーノ・ブルーノの火刑やばかげたガリレイ裁判の過ちをいまさら繰り返す必要はない。
いずれにしても、自説を証明することにのみやっきになるような組織はダメであって、真理の多元的な構造、階層構造を総合的に理解しようとするモードが必要であろう。
残念なことではあるが、私たちは今まで上げたモードにかなうような組織を見出すことはできなかった。もし誰か知っている人がいたら、是非教えてほしい。
少なくとも現時点では、キリスト教の中に総合的な真理を有する組織はないと判断せざるを得ない。「神に是認された唯一の組織だけが聖書の正しい解釈を行うことができる」というものみの塔流の考え方は、完全に否定されたと言える。
それでは、このモードでやってみれば、絶対的な基準系が確立されるのかと言えば、実験したわけではないからまだはっきりしたことは言えないが、たぶんすべての面でそうなることはまずないだろう。というのは、真理そのものの構造がそのようになっていると考えられるからである。ただ、ある真理が成り立つ限界や、適応できる領域はより明確になってくるものと思う。
原則的には真理のモードに従っている方が重要であると言える。そうであれば、「神が絶対的な基準が必要だと考えればそうなるし、要らないと思えばそうならない。無理に設定して人に迷惑をかける必要は少しもない。絶対的な基準というのは神の領域なのだから、神に任せておけばよい」と判断することができるからである。
教義が定まらないと訳語を決定することが難しいものに、十字架、杭、地獄の問題などがあったが、その中でも代表的なものは神の名をどうするかという問題である。神に名前があることは確かなのだが、発音がはっきり分からないので、神や主と置き換えたり、エホバ、ヤハウェ、ヤーヴェと読んだりしている。
しかし、この問題に関しては、早い機会に答えを出す見通しがある。すべての状況が整ってきているからである。
現在世界的な規模を有するキリスト教の組織で、エホバを崇拝していると唱えているのはものみの塔協会以外にない。ところが今回、広島会衆で生じた事件で明らかになったように、統治体とものみの塔協会は神の律法を退け、かつ無視しながら、偽善的にも「組織に従え」と完全に開き直っている。
したがって、エホバが本当に生ける神であり、天地の主権者であれば、ものみの塔協会に次の聖句が成就するはずである。
「〔今〕は、裁きが神の家から始まる定めの時だからです。さて、それがまず私たちから始まるのであれば、神の良いたよりに従順でない人たちの終りはどうなるのでしょうか」(Iペテロ4:17)
「自分の肉のためにまいているものは自分の肉から腐敗を刈り取り、霊のためにまいているものは霊から永遠の命を刈り取ることになるからです」(ガラテヤ6:8)
エホバが神性を表明し、ものみの塔協会を裁くのであれば、神の名はエホバで良いということになる。しかし統治体とものみの塔協会の組織支配をいつまでも野放しにしておくなら、その偽善をどうすることもできないのであれば、間違いなくエホバとは「ものみの塔協会の作り出した神」ということになる。キリスト教世界の多くの宗教家が批判してきたことは正しかったということになろう。
果たして神の名はエホバで良いのか、これは、ものみの塔協会がどうなるかで決着がつく。エホバが基準系の最終権威となるかそれともならないのか、この結論は近いうちに出るであろう。
現在のものみの塔協会の体質の中で最も顕著なものは、何といっても、組織賛歌、組織主義、組織支配、組織崇拝、組織バアルである。まさに組織の氾濫、組織一色といえるような状態であるが、最初からこういう体質だったというわけではない。
ものみの塔協会の初代会長であったC・T・ラッセルは、むしろ組織化の動きを警戒していたと言われている。当初は「組織」ということばを使うこと自体抵抗があって、クリスチャン会衆を組織とはみなしていなかったようである。認められていたのはエホバやみ使いたちからなる天的組織だけであった。1985年3月15日号のものみの塔誌はその当時の状況について、次のように述べている。
「そのような集め出された者たちから成る、目に見える組織を形成することが、神のご計画の精神と調和しないことは明らかである。そして、そのように組織を形成するとしたら、教会の側に、組織とか連盟とかいう今流行の概念に迎合する気持ちがあることを示すことになるように思われる。(イザヤ8:12)今の業は、組織することではなく、ユダヤ人の本来の収穫の場合と同じように、分けることなのである。(マタイ10:34〜36)」
(この部分は1894年12月1日号からの引用)
神の会衆を組織化することは世の精神に迎合することであり、神の意志に反するとまで明言されている。現在の組織化の巨大な潮流を考えると、とても信じられないような話であるが、かつてはそういう時代もあったということであろう。
しかし、やがて変化の時が訪れる。ラッセルの死後間もなく、神の組織という考え方が登場する。そのいきさつについて、同じ1985年3月15日号のものみの塔誌は次のように述べている。
「神の組織」この表現は今から60年余り前、べテルの食卓で日々の聖句の討議を行っていた時に、ものみの塔協会の編集委員の一人によって用いられました。この言葉は、ニューヨークのブルックリンにある本部の家族に深い感銘を与えました。「神の組織」というその独特な言葉は、これらの聖書研究者たちのその後の考え、話、執筆活動を導くものとなりました。(p.10)
「ものみの塔」誌の1922年12月1日号は、「サタンの目的」という副見出しに続いて、明確にこう述べました。「我々は今、邪悪な日に生きている。戦いはサタンの組織と神の組織との間で行なわれている。」〈p.17)
「この世には神の組織とサタンの組織しかない。神の組織はものみの塔協会だけ、あとはみなサタンの組織」という現在の極めて一義的な教義の概念は、1920年代の初期に導入されたものであることがわかる。組織としては、大きな方向転換をしたわけであるが、しかし、これは宗教組織の成長から言えばごく自然なことであろう。
C・T・ラッセルの頃は彼個人に対する組織の依存率が極めて高く、いわゆるカリスマ的なモードともいえるような形態であった。彼は支配的な投票権を持ち、協会内の様々な役員を任命したと言われている。当時まだエホバの証人という名称はなく、外部の人々からはラッセル派とかラッセル信奉者と呼ばれていた時代のことである。
通常組織がそういう状態のままであれば、指導者の死とともに組織自体も解体してしまう危険性がある。ものみの塔協会もラッセル死去のとき、そのような危機を経験した。ある人々は「これでもう終りだ」とまで考えたらしい。協会の会長のポストを巡る後継者争いが起き、理事会も分裂してしまった。本部ではデモ行進まで行なわれ、ものみの塔協会は分裂の危機に直面した。おそらく「神の組織」という概念が導入されることになった背景には、このような事情があったものと考えられる。
一代目の影響が大きければ大きいほど、二代目はその影に悩まされるものであるが、この非常に難しい時期を乗り越えて、ものみの塔協会を発展させたのが二代目の会長、J・F・ラザフォードであった。彼は個人依存型の体制を廃し、組織主体のモードを確立することに成功した。「神の組織」という概念のレールが敷かれ、進むべき道とその方向が提示されたのが1920・1930年代であったといえる。
そのレールの上をものすごい勢いで走り始めたのが、1924年から三代目の会長に就任した、N・H・ノアである。「合理的な管理者、組織者」と言われた彼は、その才能を十分に発揮し、次々と新しい取り決めを設ける。現在のものみの塔協会の組織体制のほとんどは、彼が作り上げたものである。組織の拡大に対するその貢献には計り知れないものがある。マタイ24章14節の「王国のこの良いたよりは、あらゆる国民に対する証しのために、人の住む全地で述べ伝えられるでしょう」という預言は、彼の組織化なくしては成就しなかったのではないかと思う。
第二次世界大戦後、組織は記録的な増加を達成して行く。わずか10万足らずから300万をはるかに越える人数への拡大である。この数字は会員数ではなく伝道者数なので、もし一般の宗教団体のように会員数でしかも多少水増しして数えたら、たぶん現在では全世界で1000万を越えることになるのではないかと思う。
現在の会長F・W・フランズは1984年10月6日の年次総会で「65年ほど前にJ・F・ラザフォードと共に、『神の組織』という言葉を初めて聞いた時ほど興奮を覚えたことはかつてなかった」と述べている。神の組織の概念なくしてものみの塔協会は成り立たないということであろう。
組織の拡大はものみの塔協会の最大のよりどころになっている。拡大はエホバの祝福のしるし、拡大が続く限りは神の是認を得ているという論理である。もっとも拡大が止まったら止まったで、それはサタンのせいだということになってしまうとは思うが。
組織は確かに必要なもの、また有用なものである。組織がなければ世界的な業は何一つ行なうことができない。組織が信仰の支えになっているような人も大勢いる。しかし、いかに組織が重要なもの、大切なものであるとはいっても、限度を越えた暴走は問題になる。神の組織と銘打ったからといって、神の領域まで犯してよいということにはならないし、第一これは増加や拡大で正当化できるような性質のものではない。
ただ、そういう体制を敷かなければ世界的な拡大を達成することはできなかったであろうから、必要悪みたいな面もあるとは思うが、いつまでもそのままでは成員も困るし、疲労もたまる。もうそろそろ終りにすべき時であろう。組織の大合唱や暴走などはもってのほかである。いずれにしても、「神の組織」という概念に明確なワク組みを設定しなかったことが、組織の暴走を許してしまた最大の原因であろうと思う。
福音の理想主義に勝利を収めた組織主義が台頭してきた時期に、新世界訳聖書の翻訳もまた始まっている。組織が教義を作り、教義が翻訳を作る(この逆も成り立つ)といった具合に、組織、教義、翻訳は密接な相関関係にあるが、ものみの塔協会の組織主義的な体質は新世界訳にも反映されている。
問題となる聖句は、出エジプト記14章31節、19章9節、フィレモン5節である。
「民はエホバに対して恐れを抱き、エホバとその僕モーセに信仰を置くようになった」(出エジプト14:31)
「するとエホバはモーセにこう言われた。『見よ、わたしは暗い雲のうちにあってあなたに臨む。わたしがあなたと話す時に民が聞くため、そして彼らがあなたに対しても定めのない時まで信仰を置くためである』。」(出エジプト19:9)
「わたしは、祈りのなかであなたのことを述べるさい常にわたしの神に感謝しています。あなたが主イエスとすべての聖なる者たちに対して抱く愛と信仰についてつねに聞いているからです」(フィレモン4、5)
このように訳すと、非常に重要な教義上の問題が生じてくる。つまり、信仰の点で、神と人間が同レベルになってもよいのか、人間が人間に信仰を持つことは正しいのかという問題である。
どうやら新世界訳委員会は、人間に信仰を持っても良いと判断したようで、エホバとモーセが同列に扱われているし、エホバ自らモーセに信仰を置くようイスラエルの民に勧めている。フィレモンの手紙の方は、パウロを含む聖なる者全員にフィレモンが信仰を持っており、パウロ自身もそれを誉めているということになっている。
それでは他の聖書もみなこのように訳しているのかというと、決してそうではない。例えば共同訳は、
「主イエススに対するあなたの信仰と、聖なる人一同に対するあなたの愛とについて聞いているからです」
というふうに「信仰」と「愛」を分けて訳している。新改訳、現代訳の翻訳もこれと同様である。新世界訳と同じように訳している聖書には、口語訳、詳訳聖書などがある。出エジプト記の方はほとんどの聖書が「モーセを信じたとか信頼した」という表現になっており、新世界訳のように「信仰、faith」を用いている聖書は、私たちの調べた範囲では他になかった。訳者によっては見解が分かれているようなので、まず新世界訳翻訳委員会に「信仰」を選んだ理由を尋ねてみた。しかし残念ながら返事はなかった。それで今度は、異なった翻訳をしている共同訳委員会に、どのような根拠に基づいてフィレモンの手紙の方を「主イエスに対するあなたの信仰と、聖なる人一同に対するあなたの愛」というふうに分けて訳したのかを質問してみた。すると次のような親切な返事が送られてきた。
「ご質問の箇所についてお答えしましょう。この箇所はテキスト上ではあまり問題はありません。つまり写本によってギリシャ語が違っているわけではなく、どの写本も、前置詞に若干の違いがある程度で、ほとんど同じギリシャ語です。
ではなぜこのような訳文の違いが出てきたのかということになりますが、そ れはこの箇所のギリシャ語の構造によります。
以下はそのギリシャ語とポイントになる言葉の日本語です。
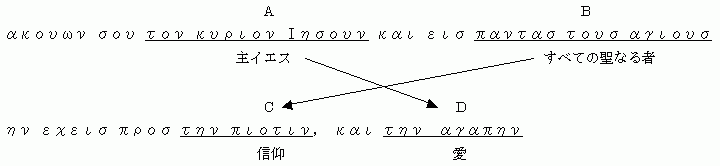
このような形になっていて、このまま訳せば、文語訳などのように『主イエスとすべての聖なる者たちに対して抱く、愛と信仰』ということになります。しかし、この形は『キアスモス』というギリシャ語の特殊な表現方法であると考えるのが普通で、口語訳や共同訳の訳し方『主イエスに対する信仰』『すべての聖なるものに対する愛』は、この考え方によったものです。
『キアスモス』(ギリシャ語のXに由来する言葉です)とは、ABCDと語や句があったときに、AはDにかかり、BはCにかかるという形の表現で、ギリシャ語やヘブライ語などによく使われる方法です。
ですから、どちらの考え方も間違いとは言い切れません。しかし、前後の文脈、聖書全体の教えるところ(コロサイ1章4節)などから考えて、共同訳聖書や口語訳聖書では『主イエスに対する信仰』『すべての聖なるものに対する愛』と分けて訳してあります」
この説明から明らかなように、文法上の絶対的な見解というものはない。結局は解釈の問題といえる。したがって、どちらの翻訳を選ぶかは、人間に対して信仰を持つことが聖書の教えにかなっているのか、それともそうではないのかという教義上の判断によることになる。
共同訳委員会も述べているように、聖書全体の教えや精神を考慮すると、どうしても聖書が人間に信仰を持つように勧めているとは考えにくい。証拠は圧倒的に新世界訳に不利である。
例えば、コリント人への第二の手紙5章7節は、
「わたしたちは信仰によって歩んでいるのであり、見えるところによって〔歩んでいるの〕ではありません」
と述べて、クリスチャンの真の信仰は、見える者に依存しているのではないということを教えている。このように諭したパウロが、フィレモンには自らその逆のことを書き送るとは、まず考えられない。
さらに、詩編146編3節は
「高貴な者にも、地の人の子にも
信頼を置いてはならない。彼らに救いはない」
と明確に記しているし、加えてモーセが約束の地に入れなかった理由を述べている次のエホバの言葉
「後にエホバはモーセとアロンにこう言われた。『あなた方がわたしに信仰を示さず、イスラエルの子らの目の前でわたしを神聖なものとすることを怠ったゆえ、それゆえに、わたしが必ず彼らに与えるその土地に、あなた方がこの会衆を携え入れることはないであろう』」(民数記20:12)
とも合わない。要するに、文法的にも聖書的にも「モーセに信を置く、聖徒に信仰を置く」と訳さねばならぬ必然性はまったくないのである。そうである以上、新世界訳の訳文はものみの塔協会の純粋な解釈または方針ということになろう。
これは組織支配、組織崇拝には非常に都合の良い翻訳である。なぜなら日本語の「信仰」の感覚では
「神・仏などを固く信じ、その教えを守り、それに従う・こと(心)。また、ある物事を絶対視して、信じる・こと(心)」(学研国語大辞典)
ということになってしまうからである。(英語の「faith」も辞書を見る限りではあまり大差はない。)
ここで注目すべきは「信仰」のレベルになると、「絶対視」する傾向が出てくるということである。ものみの塔協会の場合、「現代の聖なる者」すなわち「残りの者」、その代表が「統治体」という教義になっているので、これは「統治体絶対紙組織盲従」の体質を生み出す翻訳であるといえる。
新世界訳委員会、ものみの塔協会、統治体は確かに意識して「信仰」という訳語を選んでいる。というのは、ものみの塔誌には次のように書かれているからである。
「エホバへの信仰、エホバが代弁者として用いておられる人々に対する信仰、そうですエホバの組織に対する信仰です!わたしたちが今日エホバへの奉仕に『出て行く』とき、そのような信仰を働かせるのは本当に重要なことです。これこそ確かな成功への道であり、エホバとその取り決めに信仰を働かせる、献身してバプテスマを受けた証人たち全員がそうした成功を収めるべきです」(ものみの塔19847/1、p.15、15節)
組織の代表者に対する信仰、組織そのものに対する信仰を持つべきであると断言している。
「今年の大会は、三日間全日の大会になります。…プログラムのどの面も、それが提供される目的は,エホバが現在用いておられる目に見える組織に対する信頼を強めるだけでなく、エホバへの信頼を強めることにあります」(ものみの塔19872/1、p.30)
何とすでに神よりも組織の方が優先されている。組織は当たり前、その次に神である。
「高い塔の上の部署に就き、前かがみの姿勢を取りながら、昼間は地平線のあたりをじっと眺め、夜は目を凝らして闇を見据える、常に警戒を怠らない見張りの者の姿を思いに描いてください。それが、イザヤ21章8節で用いられている『物見の塔』に相当するヘブライ語(ミツぺ)にこめられている主要な考えなのです。見張りの者はしっかり目覚めているので、正常な人ならこの者が報告を声高く告げることに疑いを差しはさまないでしょう」(ものみの塔19873/1、p.12、12節)
見張りの者に疑いを持つ人は、正常な人ではないと述べられている。全くこの感性には驚くほかはない。疑われるようなことをしてはいないだろうかと謙虚に顧みてみるという姿勢ではなく、疑う方が異常だという感覚である。本当に正常であれば誰に疑われてもそれほど困ることはないと思うのであるが。
ものみの塔協会は非常に「組織」が好きである。新しく聖書を学んだ人には「組織の話」というプログラムを組んで、聖書研究のたびごとに組織について説明するよう取り決めている。こういう組織好きの体質は翻訳にも反映されてくるようで、日本語版はわずか一箇所だけであるが、まったくその必要がないにもかかわらず「組織」という言葉を聖書に登場させている。(英語版はorganised が二箇所 organising が一箇所)
その聖句は出エジプト記38章8節で次のようになっている。
「彼は銅の水盤と銅の台とを作ったが、それは会見の天幕の入り口で組織的奉仕に携わっていた婦人たちの鏡を用いて造られた」
「Then he made the basin of copper and its stand of copper, by the use of the mirrors of the women servants who did organised service at the entrance of the tent of meeting」
「organized service」「組織的奉仕」が他の翻訳ではどのようになっているかというと、例えば新改訳では、
「彼は…また青銅でその台を作った。会見の天幕の入り口で務めをした女たちの鏡でそれを作った」
単なる「務め」になっている。口語訳も同じで、ことさら「組織」という言葉を入れる必要はないところである。
確かに会見の天幕の入り口で働く婦人たちは大勢いたに違いないので、彼女たちが組織的に務めを果たしていたことは間違いのないことであろう。ただ、組織的という言葉を付け加えなければ、それではばらばらになって働いていたことになるかというと、それは考え過ぎであって普通はそのような心配はいらない。文脈を見れば十分わかることである。「組織」という用語をわざわざ入れたのは、やはりものみの塔協会の好みとしか言いようがない。
ここで使われているヘブライ語「ツァーヴァー」の基本的な字義は「service」であって、新世界訳が付け加えているような「organize」「組織する」という意味はツァーヴァーには含まれていない。字義訳を誇る新世界訳が何故「service」だけにとどまらなかったかは、翻訳委員会に聞いてみないと分からないが、おそらく「ツァーヴァー」の中の「army or hosts」の意味を取ったものと考えられる。確かに軍隊は厳しく組織され統制が取られている。その様子を働く婦人たちにあてはめたようだ。
「聖書から論じる」によると「組織」の定義は、「ある特定の仕事もしくは目的のために各人の努力が調和的に作用するようにまとめられた人々の集合体または社会集団。組織の成員は、管理のための種々の取り決め、また一定の基準や要求によって結び合わされます。」(p.293)となっている。したがって、組織の強化といえば通常は管理体制の強化、取り決めの強化ということになる。
これは別にものみの塔協会に限ったことではなく、すべての組織体にも当てはまることである。組織中心の体質になって行けば、必ず組織の肥大化と共に官僚化が始まり、取り決め重点主義、取り決め偏重の体質が生まれて行く。「取り決めではどうなっていますか、ぜひ取り決めに従ってください、取り決め通りにやりましょう」という組織の声が、全体を押し潰してゆくことになる。
ものみの塔協会がこういう体質を正当化するために用いている聖句は数多くあるが、ここでは翻訳との関連からその中の一つだけを取り上げることにする。
問題のその聖句とはコリント第一14章40節であるが、それに従うと、物事はすべて「取り決め」のもとに行なわねばならないということになってしまう。
「しかし、すべてのことを適正に、また取り決めのもとに行ないなさい」
「let all things take place decently and by arrangement」
新世界訳の「取り決め」が他の翻訳では、
「秩序を正しく」−共同訳、「秩序を正して」−口語訳、
「秩序があり」−現代訳、「秩序をもって」−新改訳、
「in order」−アメリカ訳、欽定訳
圧倒的に「秩序」になっている。
もとのギリシャ語には両方の意味があるので、訳語としてはどちらでも良いわけであるが、字義的には「秩序」の意味のほうが強いようである。ものみの塔協会の「王国行間逐語訳」も「order」にしている。逐語訳の「order」を止めて「arrangement」にしたのはなぜか。これは新世界訳翻訳委員会に聞いてみないとわからないが、そのほうがよりものみの塔協会の方針に合っていたということであろう。「取り決め」と「秩序」たいして違いはないように思えるかもしれないが、組織上の権限を持つ者が「秩序正しくやりましょう」と言うのと、「取り決めに従ってください」と言うのでは雲泥の差がある。組織の成員が受けるイメージはまるで違うのである。「取り決め」と訳してあれば組織の幹部はいつでも、「聖書のここに書かれているように、取り決めに従いましょう。神が勧めておられるのは皆さんが取り決めに従うことです」と皮肉タップリに言うことができるのである。
会衆の運営や集会が秩序正しく行なわれねばならないのは当然のことである。パウロが指摘しているように、神は無秩序の神ではなく平和の神だからである。会衆が混乱状態にあれば聖霊は喜ばず、その働きも低下する。当時コリント会衆はこの面で深刻な問題を抱えていた。
しかし、問題があるからといってすぐに「取り決めに従ってください」とやってしまうのでは、聖霊の働く余地を大いに狭めてしまう。もしかしたら、聖霊が心に働きかけて、自発的に問題を正すよう人々を動かすかもしれない。あるいは、予想も付かないような方法で問題を解決する可能性も残っている。また人々に健全な精神があれば、その必要に気づかせるだけで問題はなくなるかもしれない。始めから取り決めとやるとこうした可能性をみな奪ってしまう。もしコリント会衆がその段階をすでに過ぎていたというのであれば、この聖句の適用をそういう範囲に限定すべきであろう。
加えて、新世界訳の翻訳では「取り決め」を造る権限を組織が独占するのにも、非常に都合が良いものである。
取り決め偏重の体質が進行して行くと、次のような傾向も出てくる。つまり、聖書の教えが先ではなく、組織の取り決めが先になるという現象である。組織の方針が咲きに決まっていて、まず必要な取り決めを造る。そして、その取り決めを正当化できるような聖句を、聖書の中から捜してくるというやり方である。これは直接翻訳とは関係のない問題であるが、ものみの塔協会の体質を示す例として一つだけ上げることにする。
エホバの証人が毎月提出しなければならないものに、奉仕報告というのがある。正規開拓者以上は特別の用紙を使うが(もしかしたら現在は変わっているかもしれない)、一般の伝道者は次のような用紙に記入して提出する。これを会衆で集計して支部事務所に送る。

通称「組織の本」には、奉仕報告の必要性やその根拠について多くのことが述べられているが、簡単にまとめると次のようになる。
この考え方でゆくと、おそらく数字の上がっているところはみな、聖書的な根拠ということになると思う。中でもおもしろいのはヨハネ21:11の「シモン・ペテロは〔船に〕乗り、大きな魚がいっぱい、百五十三匹というふうに端の数まできちんと数えてあるので、奉仕報告の数字は正確に数えるべきであるという具合になる。初期クリスチャンが毎月組織に対して奉仕報告をしていたなどという記録は、聖書のどこにも記されていない。キリストへの報告にしたところで、弟子たちが果たして「取り決め」で報告したのか、それともその必要性を感じて自発的に報告したのかは、明示されていない以上分からないことである。また、全員が奉仕報告をするということと、誰かが統計や集計をまとめるということは決して同じことではない。それをなぜ、奉仕報告の聖書的根拠一色でみることになるかといえば、つまりは組織がそのようにしたいからに 他ならない。
こういう取り決め中心の体制では、組織が大きくなると共に必ず取り決めの数も増えてゆく。生じてくる問題やあいまいな部分を取り決めで解決しようとするのであるから、増えるのは当然である。やがてはいかに多くの規定が必要になるかはタルムード、ミシュナ、ゲマラや現代の法律を見れば良いであろう。2年ほど前になるが、すでに長老の数の少ない会衆では、ものみの塔協会から送られてくる書類をこなすだけでも大変だという状況になっていた。
加えて、取り決めが多くなればなるほど、それを管理するための官僚も大勢必要になってくる。取り決めの適用を巡って、骨の折れるような様々な問題が生じてくるからである。組織化が進むにつれ専門の管理職が存在するようになり、階級制度が発達して行く。やがて落ち着く先は、パリサイ的体質ということになる。
「ピーターのピラミッド法則」という本は、組織の成長を3段階に分けて説明しているが、この過程と特徴は宗教組織にもそっくりそのまま当てはまる。
- サービス中心の段階
成員のすべてがまだ組織本来の主旨や目的を認識しており、組織は顧客を中心に機能する。まだ組織が組織外の人々に奉仕する段階である。- 組織中心の段階
業務の拡大とともに組織化が進み、取り決めが増大する。- 管理者中心の段階
成員の関心は主に組織内の管理者に向けられるようになり、フレキシビリティー(柔軟性)は消えてゆく。組織が顧客にサービスするのではなくて、顧客の方がかえって組織の取り決めや書式に従い組織に仕えるという本来の主旨とは全く逆の状態が出現する。
ものみの塔協会は、この段階のどこまできているであろうか。おそらく3段階の末期ではないかと思う。特に宗教組織という性質上、ものみの塔協会の場合、組織支配による弊害には著しいものがある。この組織病に対する有効な処方箋はまだない。
エホバの証人の社会で非常によく耳にする言葉に「特権」という用語がある。一般にはあまり使われない言葉なので、最初はその頻度の多さに驚く。おそらく組織用語の中では、最もよく使われているのではないかと思う。
試しにどのくらい出てくるのか数えてみた。次に上げた数字は、ものみの塔誌に載った経験の中で用いられている「特権」という語の使用回数である。
カール・クライン(12回)ケアリー・バーバー(3回)ダニエル・シドリック(4回)ジョン・バー(4回)F・W・フランズ(6回)故グラント・スーター(10回)
エーリッヒ・カットナー(3回)スタン・ウッドバーンとジム・ウッドバーン(3回)ベルナルド・デ・サンタナ(1回)エバ・キャロル・アボット(0回)工藤百合子(1回)ポール・スミット(1回)アーサー・グスタブソン(0回)ワイカト・グレー(0回)フェルナンド・マリン(0回)マグダレーナ・クセロウ・ロイター(1回)エリック・ブリッテン(1回)サムエル・B・フレンド(3回)ハロルド・E・ギル(1回)P・J・ウェンツェル(2回)タリサ・ゴット(2回)
他の兄弟たちに比べて統治体の方が、はるかに多く特権という言葉を使っている。統治体の経験は他の人より紙面が多いので、そのせいもあるとは思うが、しかし、傾向ははっきりしている。全般的に組織のピラミッドを上がって行くほど、特権の使用回数は多くなってくる。やはりそれだけ、特権だと心から感じることが多いのであろう。また特権志向の強い人が特権を捕らえやすいという背景も関係しているのではないかと思う。普通のエホバの証人よりは、ものみの塔協会の代表者ほど頻度は高い。
この「特権」という言葉の使い方は、意味合いから分類するとだいたい二通りになる。たぶん多くの人は、はっきり意識することもなく使っているのではないかと思うが、深層心理からいうと二つに分けることができる。ひとつは快感神経を刺激するような使い方で、これが最も多い。特権という言葉の性質上当然そうなるとは思うが。もう一つは少々屈折した使い方で、大会会場や集会などでよく耳にするものである。
次に挙げるのは、最初の方の使用例であるが、中にはこういう言い方が口癖のようになっている人もいる。
「ものみの塔協会の当時の会長だったJ・F・ラザフォードを親しく知るというまれな特権にも恵まれました」
「ノア兄弟は私を戒め、より大きな奉仕の特権を提供されたら、それを熱心な態度で受け入れなければならないと言いました」(1984年10/15号p.28カール・クライン)
「ラザフォード判事はそのような人の一人で、私はカリフォルニア州サンディエゴにあった同兄弟の家に伺う特権を得ました」(1985年6/1号p.27D・シドリック)
「私が1920年代にあずかった大変貴重な特権の一つは、1926年に英国のロンドンで開催された国際大会でラザフォード兄弟と一緒に奉仕したことです」
「ネイサン・H・ノアと共に交われたことは、非常に大きな特権でした」(1987年5/1号p.28、29F・W・フランズ)
「そのプログラムのためにラザフォード兄弟のアナウンサーを務めさせていただいたのは特権でした」
「1941年10月1日に、ラザフォード兄弟が欠席したためにペンシルバニア州のものみの塔聖書冊子協会の年次総会を司会する特権を私がいただきました」
「数々の歴史的な退会の際に話し手の一人として奉仕するのも特別な特権でした」(1983年12/1号p.12、13グラント・スーター)
「1977年9月には、米国ニューヨーク市ブルックリンにあるエホバの証人の統治体の成員になるようにという比類のない特権が差し伸べられました。」(1987年7/1号p.29ジョン・バー)
「1961年9月から1963年9月まで、ニューヨーク市ブルックリンにある協会の本部で、特別な翻訳関係の仕事をする特権をいただきました」(1987年4月1日号p.25エーリッヒ・カットナー)
「大勢の子供たちが、当時のものみの塔協会の会長ラザフォード兄弟から『子供たち』という本を無料でいただいたのもその大会のときで、私の子供も3人全部その特権にあずかりました」(1987年6月1日号p.23ある姉妹)
アメリカの年鑑から
「わたしは1916年10月29日にロサンゼルスで行われた、ラッセル兄弟の最後の講演会に出席する特権を得ました」(P.79ドワイト・T・ケニヨン)
「1906年に、J・F・ラザフォードはエホバへの献身を象徴しました。マクミラン兄弟は次のように書いています。『わたしはミネソタ州セント・ポールで彼に浸礼を施す特権にあずかりました。…』」(P.83)
「わたしは兄弟たちが監禁されていた1918年の夏の終わりごろにブルックリン・べテルを訪問する特権にあずかりました」「兄弟たちからの報告を聞く特権を得ました」(P.109,110T・J・サリバン)
1959年の1月から…姉妹たちにも神権宣教学校に入学する特権が与えられました。(P.198)
これは一見すると謙遜ふう、中には本当にそういう気持ちで使っている人もいるかもしれないが、しかし、実際はほとんどが経歴の自慢、奥底に晴れがましいという感情が見え隠れしているものばかりである。「…は特権です」というとき、本人はさぞかし気持ちが良いかもしれないが、記事を読む人の霊的高揚には少しも役立たない。
ある特定の人物と特権意識が結びつくとすれば、それは人物崇拝になりかねない。「教祖様の御顔を拝する光栄に浴しました」というのと、「ものみの塔協会の会長ノア兄弟と交わる特権に与りました」というのは、それほど大きな違いはないからである。あるいは、そういう言い方をすることによって自分の立場や組織を誇示しているのであれば、真のキリスト教とはまったく無縁の世界である。
次はもう一つの特権の使い方。
「兄弟たちの物質的な必要物をわずかながら融通して援助する特権に与れたことは喜びでした」 (アメリカの年鑑P.209)
「神のみことばと王国を宣明するというすばらしい特権をエホバに感謝しています」(P.255)
「エホバの民は、……神の目的や救いのための数々の備えを知らせるというなんとすばらしい特権を享受しているのでしょう!」(P.256)
「アメリカ全土の兄弟のために雑誌用かばんを縫う特権にあずかりました」(P.163)
「地上で永遠に住むすばらしい見込みをもつすべての人々に、その王国政府がもたらす数々の優れた祝福を語りつづけており、その特権に感謝しております」(1986年9月1日号P.13)
大会会場や集会では、
等々、
このような使い方がよくなされている。
これはどちらかといえば、そう思うように努力しているという建前的な特権の使い方で、組織上はそういうふうに言わないと、締りが付かないという一面もある。この種の特権には、ときに非常に鬱積した暗い感情が伴う場合がある。本当はもっと良いポジションに付きたいのであるが、そのようにはならなかったので、せめて「特権です」といって自分を慰める。欲しい特権を手に入れた人は満足しているので、「ゴミ拾いだって特権でしょう。同じようにエホバに仕えているわけですから。」といかにも励ますように余裕を持って言う。心の中では少しもそうは思っていないのに。不自然さを通り越して、何か奇異な感じすらする使い方である。
この特権と言う言葉は何度聞いても、ついに最後までなじむことができなかった。
新世界訳聖書に「特権」を登場させたのは、もちろん新世界訳翻訳委員会である。それでは、エホバの証人の中に「特権」を定着させたのは一体誰であろうか。この語の背景については説明している記事がないので、私たちにもよくわからない。今は不可能であるが、機会があれば是非ものみの塔協会に尋ねてみたい。ただ出版物を読むと、この語はかなり前から使われていたことがわかる。ラザフォード兄弟の時代にも出てきているところを見ると、特権の歴史は相当に古いと言えるようだ。
新世界訳聖書には、「特権」は全部で7回出てくるが、いかにその聖句のすべてを引用することにする。ただし、[特権]は新世界訳翻訳委員会が挿入したものである。
「いつの日もみ前で忠節と義とをもって恐れなく神聖な奉仕をささげる特権をわたしたちに得させるためなのです」(ルカ1:75)
「あなたがたには、キリストのために、彼に信仰を置く特権だけでなく、彼のために苦しむ[特権]をも与えられたからです」(フィリピ1:29)
「ペテロから、わたしたちの神と救い主イエス・キリストの義により、わたしたちと同じ特権としての信仰を得ている人々へ」(IIペテロ1:1)
「彼(ダビデ)は、神のみ前に恵みを得、ヤコブの神のために住まいを備える[特権]を請い求めました」(使徒7:46)
「そして、わたしの主の母に来ていただくこの[特権]がわたしのものになるのはどうしてなのでしょうか」(ルカ1:43)
「それでも彼は自ら進んで、親切に与える[特権]と、聖なる者たちへの奉仕にあずかることとをわたしたちに請い求め、しきりに懇願したのです」(コリントII8:4)
この聖句の中で「特権」と訳すべきところは全くない。もちろん挿入しなければならないようなところは一箇所もない。もとのギリシャ語本文で字義的に特権に相当する言葉は、どこにも使われていないからである。ただし、特権という意味がそのギリシャ語の中に無いということではない。そのように訳したいと思えば、そういう訳語を選んでくることはできる。しかし、その必然性は全くない。これは完全に好みの問題である。
完全逐語訳であるものみの塔協会の王国行間逐語訳聖書にさえ「特権」は出てこない。それではなぜ、新世界訳には特権があるのか、これはやはり、新世界訳翻訳委員会の解釈、好みとしか言いようがない。挿入してまで登場させようというのだから、よほど「特権」が好きなのであろう。新世界訳が出版されるかなり前から、ものみの塔協会には根深い特権体質があったと考えてよいと思う。 特権を使っている聖句をもう一度よく読んでみていただきたい。そこには、ものみの塔協会が何を特権と考えているか、あるいは、何を特権と考えさせたいかが反映されている。 「神に奉仕すること、信仰を持つこと、キリストのために苦しむこと、仲間の一員でいること、神殿を建てること(現在で言えばべテルや王国会館を建てることと考えてよい)、マリアのような著名な人の訪問を受けること、組織の代表者をもてなすこと」などである。
好きな人は愛着すら感じるであろうが、普通の人ならば、特権と言う言葉に良いイメージを持っている人はほとんどいないと思う。どちらかといえば、これは非常にイメージの悪い言葉である。
なぜなら「特権」とは、「特定の人、身分、階級、国家などに与えられる特別の権利」(学研国語大辞典)「特定の(身分や階級に属する)人に特別に与えられる優越的な権利」(広辞苑)という意味で、すぐに「特権階級」という言葉を連想させるからである。一部の人にとって特権とは、階級差別、階級制度の代名詞のような言葉になっている。英語のprivilegeも意味にたいした違いはない。
したがって、「特権」を連発すると、組織のイメージは悪くなると考えるのが普通の感覚である。しかし、ものみの塔協会は幹部ほど特権を使っているわけだから、感覚がよほど特異なのか、特権体質の人を集めて養成したいかのいずれかであろう。
特権欲を動機とする人々のエネルギーはすさまじいものである。組織にとっては、こういう人々こそ大変ありがたい存在であろう。拡大には欠かせない貴重な人材であろう。せめて特権をもって報いるということになるのかもしれない。
しかし反面、動機が汚染され、霊的な荒廃は進行してゆく。特権のポストは限られているので、満たされない人々のねたみ、嫉妬、そねみが渦巻くことになる。特権競争が激しくなり、霊的パラダイスは名ばかりの存在になってしまう。なんとも難しいものである。
結局のところ、特権欲とは自己顕示欲である。エネルギーはすごいが、利他的な誠心にはならない。本人が利他的だと思っていても、それは表層的な意識に過ぎず、よく分かっている人は偽善的になる。これは神の名を付したミーイズムとも言える。
子どもが親のために苦しみにあっているときそれを特権とみなしなさいという親はいったいどういう性格をしているか考えてみたらすぐにわかるだろう。厳しい迫害にあっているとき、それを特権と自発的に考えるのと、神がそのように勧めるのとは、全然話が違う。
また、イエスが「私はメシアになれて特権でした、人類のために死ぬことができたのは比類のない特権でした、神の王国の王になれたのは類い稀な特権でした」と言って自己満足にひたっている姿を果たして想像できるであろうか?
崇拝の構造はこうである。
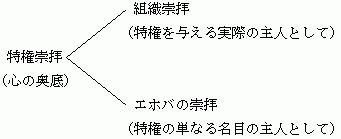
もう充分の特権を得たと思えば、何とかしてそれを失うまいと腐心する。もっと特権が欲しいと思う人は、さらに上を狙う。いずれにしても、エホバの証人としての節操をかなぐり捨て、ひたすら上部の機嫌取りに精を出すことになる。特権なくして生活ができるだろうかと言う人が出てきたり、特権のためならば、平気でウソをつき、聖書を脇に追いやっても何ともないという監督たちが増えてくる。このレベルになると、もはや完全に特権崇拝であろう。
この特権体質、特権欲の世界は、自己顕示欲が絶え間なくうずいている世界でもある。ものみの塔協会の体質の中でも、これは最も醜い一面であろう。
仮にキリストがごく普通の兄弟の姿になって、神からのメッセージを伝えるため、ものみの塔協会の本部を尋ねたとしたらどうなるであろうか。受け入れられる可能性はほとんどゼロに近いと思う。「私はイエス・キリストです」と言おうものなら、気違いと思われるのがせいぜいではなかろうか。
ものみの塔協会の教義では、神の組織に対する指示はキリストを通して、真っ先に統治体に来ることになっている。それからものみの塔協会を経由して組織の末端まで送られることになる。このルートは神権的秩序と呼ばれ、神がこのルートを否定することはありえないとされているので、誰がキリストだと言っても、エホバの証人は信用しないのである。
それでは今度は逆に、サタンが立派な背広を着て、組織上の権威を持って尋ねたらどうなるだろうか。おそらく受け入れられる可能性は、限りなく100%に近いと思う。よほど変なことをしなければ、見破られるには相当の期間がかかるであろう。
これはあくまで単なる仮想実験、思考実験に過ぎない。それでもこういうことが言えるというのは、ものみの塔協会の体質が問題だからである。この章で指摘してきたように、現在のものみの塔協会は、真理そのものによって判定するのではなく、組織の権威によって判断するシステムになっている。真理とはすなわち組織なのである。組織の代表者、組織のスタンプ、組織上の特権には非常に弱い体質である。もしサタンがこのシステムを利用するなら、組織内に容易に潜り込むことができるであろう。
この種の絵は心理学のテストなどでよく使われるものであるが、まず最初に次の絵をご覧になっていただきたい。
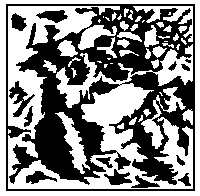
おそらくほとんどの人は一見しただけでは何の絵か分からないと思う。こういう絵を見ると、人間にはそこに何らかの意味を読み取ろうとする傾向があるので、しばらくすると、人の顔とか動物の姿とか何かの形が見えてくるかみそれない。しかし、それが正しいかどうかの確信はまだないはずである。
今度は、このページの絵を見て、もう一度前のページの絵をご覧になっていただきたい。カエルの顔の部分はちょっと分かりにくいかもしれないが、両方ともはっきり見えてくるはずである。
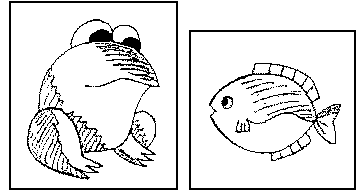
これは情報の意味を解釈できるだけの認識パターンが形成されたことによる。このパターンができあがると、もはや識別するのに困難を覚えることはなくなる。加えて、他の人にも確信をもって、これは魚です、これはカエルですと言えるようになる。
宗教の場合この認識パターンのアウトラインを決定してゆくのは教義であるが、実際もっとも強力なのはその組織の体質である。教義は建前、体質は本音の世界だからである。特定の体質の中で長い間育まれてゆくと、細胞のレベルまでそのパターンがしみついてしまう。変えようとすると、生理的な拒否反応が起きてくるようになる。これは実に強力なものである。
また意識するにせよそうでないにせよ、一度形作られたパターンは、その後の判断を支配してゆくことになる。最初の絵はもう魚かカエル以外には見えないはずである。
このように体質の持つ本当の恐ろしさは、体質が判断や認識の支配的な基準になってしまうという点にある。そのモードに染まった人には、そのパターンでしかものが見えなくなってしまう。
再度繰り返すがこれは非常に恐ろしいものである。体験者がいうのだから絶対に間違いはない。組織がカエルといえばカエルになり、魚といえば魚になるのである。それ以外の見方はみな組織に対する反逆、神に対する不忠節にされてしまう。組織が一つの見方に神の名を付してそれを絶対化すると、他の見方はすべて排撃されてしまう。このようにして極端に一義的、一律的な体質が出来上がる。
輸血や武道その他不評を買っている教義のほとんどは、本来の精神そのものは悪くないにしても、適用の仕方に問題のあるものばかりである。なぜそうなるかといえば、ものみの塔協会の体質があまりにも一義的だからである。組織の適用が本来の精神を越えてしまったところに、この教義の真の問題がある。(詳しくは現在広島会衆で検討中である。)
この宗教的パターン認識の図式を考えてみると、キリストの述べた次の言葉の心理的なからくりが、よく分かるのではなかろうか。
「人々はあなた方を会衆から追放するでしょう。事実、あなた方を殺す者がみな、自分は神に神聖な奉仕をささげたのだと思うときが来ようとしています」(ヨハネ16:2)
パターン認識が殺人と判定しなければ、殺人も殺人ではなくなる。
ものみの塔協会の代表的な体質として、組織主義、組織崇拝、取り決め偏重、特権崇拝を上げたが、もう一つ、偽善的な体質を付け加える必要がある。今回の広島会衆が直面した事件で明らかになった最大のものは、この偽善的な体質であったからである。
これらの体質はどれを取ってみても、キリスト教の価値観から言えば、致命的な病ばかりである。癒しは非常に難しい。第一本人たちに直す気が全くないのだから、エホバも癒しようがないのではなかろうか。
特権こそ命のような人々にとって、そのよりどころとする体質を変えられたら非常に困るであろうし、一度吸った甘い汁はそう簡単には忘れられないと思う。おそらく、体質を変えようとする者がエホバとキリストであっても、彼らは今の体質を維持するために必死に戦おうとするのではないだろうか。ものみの塔協会の反応を見ていると、そのように思えて仕方がない。
今回私たちは、政治と宗教が分離されている国に住んでいて、本当に良かったと思った。もし、ものみの塔協会が政治上の実権を握っていたなら、おそらく広島会衆のかなりの成員が処刑されてしまったのではないかと思う。まさに雰囲気は中世の異端審問、宗教裁判をほうふつとさせるものがあった。半分冗談交じりではあったが、山にでも籠ろうかと話していたくらいである。
ものみの塔協会の幹部が実際に政権を握ったら、間違いなく恐怖政治、神権ファシズムの体制になる。霊的には今でもそういう体質なのだから。彼らが天に行って神の王国の成員になったら、それこそ一番迷惑するのは地上の住民ではないだろうか。もっともエホバとキリストがいれば大丈夫かもしれないが。それにしても、自覚症状のない人が多いので、危険な存在ではある。
古代ユダヤ教の体制は神に捨てられ、一世紀のユダヤ教の体制もまた神に退けられた。癒すことができなかったからである。果たして、ものみの塔協会はどうなるであろうか。
字義訳新世界訳には、やはり逐語訳の欠陥のすべてが含まれていた。新世界訳の正確さとは単語のコンピューター的な処理による字句の正確さに過ぎず、文章全体の意味や音信の主旨の正確さではなかった。部分の正確さを追及した結果が、かえって全体の不調和や不明瞭さの原因となっていることは、例証してきた通りである。新世界訳はおびただしい数の不自然な表現や極端な冗長さにより、非常に分かりにくく、読みにくい聖書になっている。
加えて新世界訳には、ものみの塔協会の体質上の欠陥も反映されている。1940年代の強力な組織化と共に生み出され、改訂されたときにはさらに組織化が進んでいたという背景がある。新世界訳の母体はものみの塔協会、その精神はものみの塔協会の精神である。
このような聖書に長く親しんでいると、どのような弊害が出てくるだろうか。「日本の文章」の49頁には、その点を示す非常によい例えが載っている。これは新世界訳の欠陥の霊的な側面を表しており、翻訳上の問題よりはもっと重要なより本質的な部分を示しているといえる。
「たかが文章くらいと言うけれど、度の合わないメガネをかけていると目が悪くなるというのは常識だ。焦点のはっきりしない訳文を通して対象を見定めようとすることを長くつづけていれば頭も悪くなる道理である」
目の方は悪くなると物がはっきり見えなくなるので比較的気が付きやすいが、霊的頭、心脳の方はなかなかそうはいかない。特に自分たちは世界で最も啓発された唯一の真理の民であると自負しているものみの塔協会の幹部の場合は、自覚のある人は皆無に近いであろう。末端のエホバの証人の方は、翻訳に問題があるなどとは夢にも思わず、ひたすら自分たちの頭が悪いせいであると思い込んでいるはずである。もっとも自分はよくわかっていないと思っている謙虚な人に限られてはくるが。
考えてみると、こういう聖書に慣れてしまうことには、非常に恐ろしい一面がある。字句が分かったというだけで全体が分かったかのような錯覚を起こしやすいのである。もちろんこれは少々極端な言い方ではあるが。組織は分かりやすい、分かりやすいと宣伝するので、そう思わないと不忠節になるのではないかというような意識も働くし、何度も聞いているうちにしまいには本人もだんだん分かっているような気になってくる。組織の幹部の方は分かっているつもりなのでよけいに始末が悪い。
組織の体制全体がこうなってしまうと、実際には何が分からないかもよく分からなくなってしまう。目で追う聖書の言葉は単なる反射言語にすぎず、心脳言語にはならないのである。「聖書読みの聖書知らず」が大量生産されてゆく背景にはこうした側面がある。ものみの塔協会の「度」の基準が絶対的に正しいと思い込み、自分たちの心脳の働きが悪くたっているとは考えてもみないのである。
また字義優先の思想はヘブライ語、ギリシャ語信仰にもつながってゆきかねない。ヘブライ語、ギリシャ語が重要でないというわけでは決してないが、度が過ぎると聖書解釈がヘブライ語、ギリシャ語の字義に依存しすぎるという問題が生じてくる。この面での権威者とされるキッテルの研究について「新約聖書諸論」(エヴェレット・F・ハリソン著)という本はその九十九頁で、
「神学的意義を持つギリシャ語の用法を、古典の背景から70人訳聖書を経て、新約聖書に至るまで、(ヘレニズム時代の世俗の出典を無視することなく)たどるというのが、キッテル(Gerhard Kittel)とフリードリッヒ(Gerhard Friedrich)によって、順次編集されたあの何巻にも及ぶ新約聖書神学用語辞典(Theologisches Worterbuch zum Neuen Testaent)でとられた方法である。この辞典の価値は、ほとんど世界中で、好意を持って受け入れられている。」
と評価しているが、同時に次のような批判があることも指摘している。
「もちろん、批判者もないわけではなく、中でも特に、ジェームズ・バー(James Barr)は以下の点を鋭く指摘する。すなわち、語源学にあまりにも依存しすぎていること、言語学的判断と哲学−神学的判断との根拠のない混同、文脈の要求を十分考慮することなく、孤立した単語を強調しすぎること、言葉から概念にあまりにも簡単に移行しすぎること、ヘブル的概念とギリシャ的概念を安易に対照させすぎることなどである。これらの批判は、他の反対論と共に、釈義や聖書神学の土台として聖書の言語を取り上げる人々が、陥りやすい危険を指摘している。」
特別優れた言語とか、とりわけ劣った言語というものがあろうはずはない。ヘブライ語、ギリシャ語といってみても所詮はニュアンスの相違に過ぎない。字義による深い研究とは、多くの場合単たる言葉の置き換えである。ものみの塔誌にもたいして意味のないトートロジー(類語反復)がよく載せられている。そういうのを有難がる人は別として、意味から言えばそれほど決定的な相違があるというわけではない。字義にこだわり過ぎると、むしろ、重箱の隅をほじくるような、「ブヨこし取り、ラクダ飲み込む」式の聖書研究に陥りやすい。
こういう弊害はキリスト教にとっては致命的な欠陥になりかねない。まさにキリスト教の実質的な力、存在意義に関わってくるレベルの欠陥である。意味の理解にヴェールをかけるということは、非常に重要な問題である。というのは、マタイ13章14,15節でイエス・キリストは次のように述べているからである。
「イザヤの預言は彼らに成就しています。それはこう述べています。『あなた方は聞くには聞くが、決してその意味を悟らず、見るには見るが、決して見えないであろう。この民の心は受け入れる力がなくなり、彼らは耳で聞いたが反応がなく、その目を閉じてしまったからである。これは、彼らが自分の目で見、自分の耳で聞き、自分の心でその意味を悟って立ち返り、わたしが彼らをいやす、ということが決してないためである』」
この言葉から分かるように、意味が悟れない人には神からのいやしがない。つまり、魂の救いはないのである。心の目、心脳の働きが悪くなるということは、クリスチャンにとっては致命的な問題となる。意味の理解はもっともっと強調されてしかるべきである。
「読書百編意おのずから通ず」ということわざもあるが、これは聖書通読には別の意味で当てはまることが多いようである。意味の分からないものでも百回読めば分かった気分くらいにはなれると。その間に心脳の麻簿は秘かに進行してゆく。繰り返すばかりが能ではない。もっと心の理解に目を向けるべきである。
現在のものみの塔協会内の霊的荒廃と新世界訳は決して無関係ではない。もちろん非とされるべきはものみの塔協会の体質の方であるが、新世界訳がそれに貢献していることは否定しようがない。新世界訳は「霊的いやし」には極めて不向きな聖書だからである。できるだけ早い機会に改訳すべきであろう。
新世界訳聖書の前書きには「神と人に対して責任を感じる」と記されているわけだから、新世界訳翻訳委員会は是非ともその公約を果たしてほしいものである。神と人に対する良心が少しでも残っているなら、組織の権威でごまかそうとするのではなく早急に問題を正すべきであろう。
もし改訳するのであれば、この機会に是非二つの聖書を検討してみてほしいと思う。中途半端な字義訳はやめて、徹底的な字義訳、完全な逐語訳を一つ作り、それは研究用にしてしまう。そして通読用には分かりにくい、読みにくい、長すぎるという字義訳ではなく、意味のすっきり分かる聖書を作るのである。通読用の聖書には外部からの提案や要求も可能な限り含めてほしい。自分たち以外はみなサタンの世の人、バビロンの人、意見など聞く必要がないなどと決め付けないで、有用な提案には積極的に耳を傾けるよう努力すべきであろう。
聖書をもっと読みやすくするために提案されている点をまとめるとだいたい次のようになる。
「だいぶ前に亡くなったが、佐々木邦というユーモア作家がいた。だれにもたいへんよくわかる文章で小説を書くというので、多くの愛読者をもっていた作家である。
縁があって、佐々木さんのところへときどき伺った。
あるとき、
『どうしたらわかりやすい文章が書けるのでしょうか』とたずねてみた。すると、佐々木さんは
『同じことばをくりかえさないことですね。同じことばがすぐ近くに出てくる文章は読む人に難しいという感じを与えるようですよ。』
と言われた」(「文章を書く心」P.49外山滋比古著)
(1) 空の鳥を見よ、播かず、刈らず、倉に収めず、然るに天の父は、これを養ひたまふ。汝らは之より一も遥かに優るる者たらずや。汝らの中たれか思い煩ひて身の長一尺を加え得んや。又なにゆえ衣のことを思ひ煩ふや。野の百合は如何にして育つかを思へ、労せず、紡がざるなり。されど我汝らに告ぐ、栄華を極めたるソロモンだに、その服装いこの花の一つにも如かざりき。今日ありて明日、炉の投げ入れらるる野の草をも、神はかく装ひ給へば、まして汝らをや、ああ信仰うすき者よ。さらば何を食らひ、何を飲み、なにを着んとて思ひ煩ふな。
(2) 空の鳥を見るがよい。まくことも、刈ることもせず、倉に取り入れることもしない。それだのに、あなたがたの天の父は彼らを養っていて下さる。あなたがたは彼らよりも、はるかにすぐれた者ではないか。あなたがたのうち、だれが思いわずらったからとて、自分の寿命をわずかでも延ばすことができようか。また、なぜ、着物のことで思いわずらうのか。野の花がどうして育っているか、考えて見るがよい。働きもせず、紡ぎもしたい、しかし、あなたがたに言うが、栄華をきわめた時のソロモンでさえ、この花の一つほどにも着飾ってはいなかった。きょうは生えていて、あすは炉に投げ入れられる野の草でさえ、神はこのように装って下さるのなら、あなたがたに、それ以上よくしてくださらないはずがあろうか。ああ、信仰の薄い者たちよ。だから、何を食べようか、何を飲もうか、あるいは何を着ようかと言って思いわずらうな。
(2)は(1)にくらべて格段に冗長である。口語体が文語体ほどに簡潔であり得ないのは、いはば宿命的な欠陥だらうが、しかしそれにしても度が過ぎる。(2)の翻訳者たちはおそらく、口語体のそのやうな弱点を一度も意識したことのない呑気な人々なのであらう。なぜならここには、文章の凝縮度を高めようといふ努力の影さへも見られないからである。たとへば「あなたがたの天の父」の「あなたがたの」は除いていっこう差支えない。「養っていて下さる」は「養って下さる」ないし「養ってくれる」にするほうがよい。「自分の寿命」は「自分の」を取って単に「寿命」あるいは「命」としたほうがすっきりする。このやうな配慮の方法を知らず、また、配慮の必要を感じたかった人々が聖書翻訳の仕事にいそしむとき、イエスの言葉は、「きょうは生きえていて、あすは炉に投げ入れられる野の草でさえ、神はこのように装って下さるのなら、あなたがたに、それ以上よくしてくださらないはずがあろうか」といふやうな、イエスの口から断じて出るはずがない、平板で力点がなくて、たるみにたるんでいる駄文と化してしまふのである。(「日本語のために」P.58,59,61丸谷才一著)
この冗長さという問題はもっと真剣に考慮しても良いのではないかと思う。それでなくとも聖書は長いのに、何もわざわざ冗長にしてそれに貢献することはない。もう少し短時間で読めるように訳者は親切を示すべきであろう。次のような指摘も是非翻訳のレベルで検討してみてほしい。
今日一般的に受け入れられている標準本文のもととなった「レニングラード」写本は、1008年のものである。しかし「クムラン写本」の発見により、一気に1千年も前の『聖書』本文が明らかになったことになる。完全な形で残されたクムランの「イザヤ書写本」と現在のマソラ本文とを比較してみると、多くの相違が見出されるが、そのほとんどは些細なもので、全体としてはマソラ学者による本文伝承が、きわめて正確なものであったことが裏付けられた。
他方・相違について興味深い事実も明らかになった。たとえば、『旧約聖書』のギリシャ語訳である70人訳の「エレミヤ書」には、マソラ本文に見られる多くの語や文が欠け、全体として8分の1短い。それまでこのことは、訳者のずさんさや意図的省略によるものとしばしば考えられてきた。しかしクムランから発見された「エレミヤ書」の断片は、マソラ本文よりもギリシャ語訳の内容に近いヘブル語本文を示している。したがって、これにより70人訳が用いた「ヘブル語底本」が現在のマソラ本文とは異なる系統のものであったという事実と、ヘブル語本文にかなり遅い段階にまで拡張や付加がなされ続けたという可能性とが明らかになったのである。
(「死海文書の発見」山我哲雄著 歴史読本特別増刊/'87-1p.133,134)
「英語の作文の本に『センテンスを"そして"(and)とか"しかし"(but)で始めるのは悪文である。そういう書き方をしてはいけない』とあるのをみて、われわれは愕然とする。いけないといわれることをさかんにやっているからだ。英語の文章だけのことではない。日本語の文章でも、前後の文章を結びつげる論理的接続詞を乱用しないようにすると文章が良くなる。」
(「文章を書く心」P.53,54外山滋比古著)
一語が文を引き締めたり、緩めたり、ときには意味を通じなくさせたりもする。接続詞・副詞は、軽く見られるのか、あるいは逆に節目の意識があるのか、濫用の気味がある。「そして」「しかし」「だから」「すなわち」は、もっとも多く使われる。「すなわち」と置くことによって、書いている実感なり、手答えなりを味わっているのだろうか。
(「文章の書き方」p.105,尾川正二著)
「そんなことを言うが、"私"や"ぼく"を使わないでは文章が書けないではないかと反論される可能性はある。なにも絶対にいけないと言おうとしているのではない。ぎりぎりの必要なときだけにしてほしいと思うだけである。そのつもりにならば、第一人称単数は、ラテン語と同じように、動詞のなかへかくすことができる。それが日本語のおもしろさか」(「日本の文章」p.14)
「まず逐語訳の問題がある。ヨーロッパ語と日本語と言語の性格が違うのだから、逐語訳といっても語順の入れ替えをしないと訳文にならない。
ところが、構造の違いを考慮に入れるのはこのセンテンス内の語順の交換だけにとどまっている。これは翻訳の原理としてもたいへんおかしい。ただし、それをおかしいと思う人がほとんどいなかった。これはさらにおかしい。
センテンスの内部で原文の語の順序はそのままにしておく、というのはどうしたことか」(「日本の文章」P.190)
おそらく聖句の節番を変えることには心理的な抵抗を覚える人もいるだろうが、次の記述はこだわりを捨てるのに役立つかもしれない。
ステファヌスの第四版(1551年)は二つのラテン語訳(ウルガタとエラスムスの訳)をギリシャ語本文の両側に配置しているが、注目すべきことに、この版ではじめて本文が節に区切られた。ステファヌスは「馬にのって」旅行している時に節区分を施したとか、馬の背がゆれて彼のベンがまちがったところにあたったため節の区切りに不適当なところがあるとか、言われている。ステファヌスの息子は、父がパリからリオンヘの旅行中に(inter equitandum)節区分をほどこしたことを認めているが、しかし、実際は道々、旅館で休んだ時にこの仕事にあたったものであろう。
(「新約聖書の本文研究」P.119,B・M・メツガー著)
今の新世界訳は完全な欠陥聖書である。通読用としては改訳しないかぎり、もはや必要性のない聖書であろうと思う。それではもう新世界訳は不要かというと、またそうとは断言できない面も残っている。まったくの誤訳は別としても、字義訳の欠陥とは裏を返せば字義訳の個性にもつながる。字義訳には字義訳でなければ味わえないような表現がある。分かりやすさよりもそういう異質の文化との出会いをもっと貴重にすべきだという次のような意見もある。
・・・何ほどかでも新約書を知っている人が「ただ神により頼む人々は、幸いだ」という文に接したとして、これがマタイの山上の説教の冒頭の有名な句だと気がつくだろうか。どうして「心の貧しい者は幸いだ」と訳さないのか。いや「心」というのは厳密でないので「霊」とすべきだとか、そうには違いないが日本語で「霊」と言っては何だかはっきりしないから、「精神」とまでは言わぬまでも「魂」とでも訳そうか、というのなら、ありうる議論である。しかし、「霊」も「貧しさ」も消去して、その代わりに「ただ神により頼む」と訳してよい理由がどこにある。・・・。
それに対して「共同訳」を支持する者は理屈をこねる。目本語では「貧しい心」とはもっぱら金銭や自分の利益しか求めない「さもしい心」しか意味しない、というのだ(たとえば1978年12月2日大阪朝日夕刊に「共同訳」のたいこもち記事を書いている三好迪)。だから日本人の読者に対しては「心の貧しい者は幸い」と言ったとて通じはしないので、「ただ神により頼む者」と訳さないといけない、というのである。しかしこれほど読者を馬鹿にした話しはない。
今時の日本人で聖書の翻訳を読むくらいの人ならば、「心の貧しい者は幸い」という場合の「心の貧しさ」は決して「さもしい心」なんぞを意味するのではなく、もっと積極的な価値を意味している、という程度のことは知っていて読んでいる。日本近代にはすでにキリスト教と接触してきた百年の歴史があり、多くの人々が、たとえキリスト教徒でなくても、「心の貧しい者は幸い」という言葉に取り組みつづけてきた歴史がある。日本人の読者ならば、「心の貧しい者は幸い」という文に接した時に、「さもしいエゴイストが幸いである」などという意味に勘違いして受けとることはまずありえない。その程度には日本人の読者も聖書のことを知っているのである。
(「宗教とは何か」P.77〜79田川建三著)
マタイ5章3節の訳は「心の貧しいものは幸いである」にはなっていないが、異なった文化、異質の感性、特異な表現との出会いのおもしろさでいうなら、文句なしに新世界訳を推薦できる。こういうユニークな聖書は他に類例がないのではないだろうか。新世界訳のこの希少価値はもう少し高く評価してよいと思う。
さらに、神の名に関する問題がある。新世界訳の最大の特徴は何と言ってもエホバというみ名を全面的に用いている点である。これは新世界訳を不要だと言い切ってしまえない最も重大な理由になっている。
神の名については前にも触れたように見解が分かれているが、私たちは次の意見に賛成である。
「神の名YHWHは、マソラ本文でアドーナイと呼んでいる箇所は、特製の太字『主』と訳出した」とのことであり、そのようにされている。YHWH(yahweh)は神の名であるから、神の名は神の名として打ち出したほうがよいと思う。マソラ学者は、ただ読みを忘れてしまったこの神名の聖四文字に母音符号をつけてアドーナイと読ませたり、エロヒムと読ませたりしただけのことであるから、何もことさらユダヤ人のまねをしてアドーナイ(主)と読む必要はない。いや、それより神の名を意訳するなど、愚の骨頂である。どんなものでも、ものの名というものは意訳などするものではない。このありかたりは、日本ではかなりリベラルな聖書協会口語訳か先鞭をつけており、不評を買ったものである。硬骨ファンダメンタリストがどうして軟弱リベラリストのまねをしたものか、了解にくるしむ。ちなみに、元訳には「エホバ」、左近訳には「ヤーエ」、半月訳には「ヤウエ」、渋谷訳には「ヤハエ」、関根訳には「ヤウ」、荻原訳には「ヤヴ」、フランシスコ会訳には「ヤーウ」中沢訳には関根訳と同じように「ヤウ」、と発音されている。YHWHはハーヤー動詞の第三人称、単数、未完了形における神の名であって、「私は在るという者」「私は在って在る者」ないしは「私は在ろうとして在ろうとする者」(出エジプト3:13,14)を意味する語であるから、「主」というような語でおきかえて平気でいられるものではあるまい。
(「聖書の和訳と文体論」p.314,315藤原藤男著)
もっともであると思う。名前があるかぎりは使うべきであって、当事者に断りもなく消すべきではない。
聖書から神の名を省いてしまうことは、小説であれば主人公の名を消してしまうことに相当する。カフカの「城」のような小説もあるが、たいていの小説は主人公の名前を省いて人、人間、男、女、などとしたらまず成り立たなくなってしまうであろう。
引用文からも明らかなようにエホバを用いているのは文語訳くらいのものであって、口語訳では新世界訳の他はほとんどがヤーウェである。ヘプライ語の研究によれば、エホバは間違いであってヤーウェが正しいということになっているし、次のような証言もあるので
「タルムードにも聖四文字の持つ聖なる力についての記述があり、聖四文字の正確な発音をめぐってさまざまな魔術・呪術・悪魔払いなどの通俗的カバリスト(瞑想と思索を主としたカバリストとは区別するための呼称)の活動が展開されたのである。これがつまり"聖四文字の秘儀"なるものの中心課題であった。それでは、YHWHの正確な発音はどのようなものであったのか。現代の研究者によれば決して紀元前3世紀以来忘れられていたのではなく、キリスト教初期の記述のうちに"ヤウ"(Yaweb)として記録ざれていることが指摘されている。さらに、YHは母音が付加されてYAHとして『出エジプト記」の詩のうちにも記述されていることが判明した。
"主はわたしの力また歌、わたしの救いとなられた、彼こそわたしの神、わたしは彼をたたえる、彼はわたしの父の神、わたしは彼をあがめる"(出エジブト記15:2)−YAHU、−YAHは、ヘブライ語の名詞の語尾につくことが多い事実も判明した。また、YHWHは古代ヘブライ語における"ある"(to be)を意味するYHWHの動詞形であることが、多くの学者によって指摘されている。」
(「カバラ」P.99,100箱崎総一著)
もうヤーウェに決定してもよいと言えるかもしれないが、ものみの塔協会に関する決着がつかないうちはまだ早い。
それに名前を啓示したのは神自身であるという聖書の歴史的な背景を考えると、どの名前にするかは人間が勝手に決めるべきことではないと思う。神が自分で名前を定めるのが一番ふさわしいであろう。
繰り返すが現在の世界の宗教事情では、エホバ−ものみの塔協会−新世界訳聖書というつながりになっている。その新世界訳はエホバの神性をおかしくするような聖書であり、ものみの塔協会にいたっては完全に神の神性を否定してしまっている。
これを放置するようではもはやエホバではない。ものみの塔協会を裁いてこそ本物の神である。神聖な名前を汚されても何もできないようでは、エホバとは単なる名ばかりの存在、ものみの塔協会の教義上の存在に過ぎなくなってしまう。
もしエホバが何もしたいようであれば、そのときはエホバという名を捨て去ってもよいのではないかと思う。ヤーウェが正しいというのであればヤーウェにすればよい。
しかし、ものみの塔協会に天の裁きが下るならば、確かにエホバは自らの存在と神聖を証明したことになる。その時には、神の名をエホバに決定してもよいであろう。
そういう意味では、今はキリスト教の歴史上、神の名を定められるという点でまたとない絶好の機会といえる。