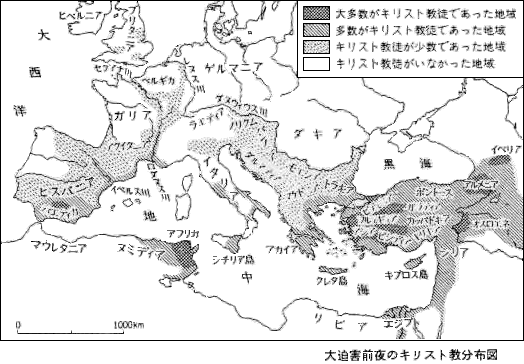
今回の広島会衆の事件によって明らかになった最大の点は、ものみの塔幹部のいやし難い『偽善』とその『組織崇拝』であった。彼らにはイエス・キリストの次の言葉がよく当てはまる。
「彼らのことは放っておきなさい。彼らは盲人を手引きする盲人です。もし、盲人が盲人を手引きするなら、ふたりとも穴に落ち込むのです。」(マタイ15:14 新改訳)
もはや偽善的な幹部はどうしようもないであろう。彼らのことは、キリストの指示通り放っておくより仕方がない。問題なのは自分たちの案内人が盲目の偽善者であるとは、夢にも思っていない誠実なエホバの証人たちである。純粋に真理を愛し、心から神に仕えているエホバの証人の数は決して少なくない。ものみの塔協会の誤導から解放する必要があるのは、こうしたエホバの証人たちである。
この小冊子の目的は、「誠実なエホバの証人たちにものみの塔協会の真実の姿を伝え、彼らが盲目の案内人の手引きを振り切ることができるよう助ける」ことにある。
ものみの塔協会は強力な情報統制を敷き、一般信者に真実が伝わらないようにしている。もちろんそれは、真の姿が明らかになることによって、組織を離れる人が増えることを懸念しているためである。
一般に出版されているものみの塔を批判する書籍や雑誌を読むことは、サタンの影響を受けることとして禁じられている。組織の中にはそうしたことを話題にするだけでも、背教者の疑いをかけられてしまうような雰囲気がある。信徒のなかには組織の実態に疑問を抱き、誠実に改善を提唱する者もいるが、そのような声をあげようものなら、すぐに背教者、異端者というレッテルをはられてしまう。
この面でのものみの塔協会の行動は非常に素早い。いったん組織から出してしまうと、今度は会衆の羊を守るという名目で、一切の交渉を禁じてしまう。実態を知った者の処分はじつに速やかにかつ徹底して行われるのである。そうなるともはや組織の指示に違反する人が出てこない限り、追放された人が内部の人と話し合うことはできなくなる。
そういうわけで残念ながら、組織の正体を知った人は(私たちもそうであるが)真実を伝えたくても、直接エホバの証人と会って話し合うことができない。ものみの塔協会から神の羊を救い出すには、エホバの証人や彼らと聖書を学ぶ人々を気遣う『善意の人』の協力が是非とも必要になる。この小冊子を読んだ方々が、そのような善意の人になって下されば誠に幸いである。
今まで何冊かエホバの証人救済のための本が発行されてきた。しかしその多くは、残念ながらあまり大きな効果を挙げていない。内部から見ていると、どうもインパクトが弱いというか、最も重要な点が欠けているような印象があった。
それでこの小冊子には、エホバの証人の信仰の最大の基盤となっている点を取り上げてみた。加えて「事件簿」「欠陥翻訳−新世界訳」出版以来、各地から寄せられた情報や意見、提案に基づいて最善と思われる方法を提示した。
効果的か否かはやってみないとわからないが、少なくとも今までよりは何らかの進展を期待できるものと思う。
この小冊子を用い、ごまかしを許さず、ものみの塔協会の実態を問うて行くなら、やがてエホバの証人は次の二つのタイプに分かれてゆくのではないかと考えられる。
(1) のタイプは建設的な批判と単なる悪口の区別の付かない、いわゆるミーハー的信仰の持ち主である。このタイプのエホバの証人には何を言っても無駄であろう。彼らは、若者がアイドル歌手に熱を上げ、みさかいがなくなった状態といっしょで、いかに真実の証拠をあげ論理的に問題点を指摘したところで素直には受け入れない。感情的な反応ないしは冷たい反応にあい、時間が奪われ疲れるだけで何の益も得られず、嫌な思いをすることになる確率が高い。そういうタイプだとわかったら早めに手を引くのが賢明であろう。
このタイプのエホバの証人の親族にはお気の毒としか言いようがない。組織熱が冷めるのをじっと待って出直すか、あるいは親権を利用して強烈な冷水を掛けるかしかないのではなかろうか。
(2) のタイプは単にものみの塔協会に誤導されているだけで、本当の真理、真実がはっきりすれば、人間の作る組織や取り決めを恐れることなく行動できるタイプである。話し合いも実のあるものになると思うので、是非時間をかけて援助していただきたい。
真理の擁護者と組織の奴隷を見分けるのは簡単である。
最後に一言
夢を見ている人は、途中で起こされると不機嫌になるかもしれない。しかし、完全に正気になれば起こしてくれた人に感謝するはずである。
エホバの証人とは「エホバを証しする人」という意味である。彼らは宣べ伝えることにより、また日常生活で聖書に従った生活をすることにより、神性を他の人々に証しする責務を負っている。
以前は「ラッセル信奉者、ラザフォード派、ものみの塔派、国際聖書研究者協会及び一般伝道者協会」等で呼ばれていたが、その名称はふさわしいものではないとして、J・F・ラザフォードの提唱により、1931年から「エホバの証人」という名称が採用された。
この名称の根拠はイザヤ書43章10,11節で、その聖句の中で神はご自分の民イスラエルを「私の証人」と呼ばれている。したがって、現代の神の民が「エホバの証人」と呼ばれるのは妥当なことであり、この名称は神ご自身が命名されたものであると、ものみの塔協会は主張している。
本来「エホバの証人」とは神を証しする人のことなのだか、最近では神のみ言葉を何よりも優先して神に仕えようとする真のエホバの証人と、み言葉より組織の取り決めを優先する自称エホバの証人(すなわち、ものみの塔の証人)がいるようである。
エホバの証人最高指導機関、定員は18名('87年現在13名)。
油注がれた14万4千人からなる忠実で思慮深い奴隷級(マタイ24:45〜47)の代表と称している。
統治体は6つの委員会を構成している。
| 執筆委員会 | … | 出版物の作成とその監督 |
| 教育委員会 | … | 各種学校(牧羊、伝道の面でエホバの証人を教育するため独自に設けた学校)、集会、大会などで用いられる資料を準備する |
| 奉仕委員会 | … | 伝道に関する一切を取り扱う、審理問題の最高責任機関 |
| 出版委員会 | … | 印刷作業及び業務関係をすべて扱う |
| 人事委員会 | … | ものみの塔協会の職員の人事を扱う |
| 司会者の委員会 | … | 議事の討議の司会を交代で務める |
ものみの塔協会は国の許可を受けて宗教活動を行うため、C・T・ラッセルにより1881年に設置された非営利団体である(法人化は1884年)。理事7名、会員500名('82.10.2の時点では464名)からなる。エホバの証人のほとんどは、法的にはものみの塔協会の会員ではない。
組織支配の仕組みのカギは、忠実で思慮深い奴隷級、統治体、ものみの塔協会の関係にある。
忠実で思慮深い奴隷級とは、キリストが再臨するときすべての財産をゆだねられる人々のことである。エホバの証人の教義ではその代表が統治体ということになっている。したがってエホバの証人にとっては、統治体こそがキリストの是認を得た唯一の管理機関になる。その統治体の用いる法人団体がものみの塔協会ということになっている。
通称「組織の本」の28ページには、この組織上の流れについて次のように記されている。
「組織内のすべての人は神の神権的な管理の仕方を認めます。諸会衆は、すべての人の益のために組織上の取り決めを定める統治体の導きを受け入れ、それに従います。彼らは、支部、地域区、巡回区、会衆などを監督するために年長者たちに対してなされる任命を受け入れます。」(支部、地域区、巡回区、会衆はものみの塔協会の管轄下におかれている)
神権的な管理の頂点に位置するのが統治体、統治体はものみの塔協会を通して全地のエホバの証人を導く、ということになっているが、歴史的な背景からすると実際は逆である。忠実で思慮深い奴隷級、統治体、ものみの塔協会という流れではなくて、その反対、つまり、ものみの塔協会、統治体、忠実で思慮深い奴隷級なのである。
最初にものみの塔協会を設立した、そして組織の拡大に伴って、協会の幹部たちが自らの聖書的根拠を確立しようとして考え出したのが、統治体、思慮深い奴隷級の教理なのである。
事実ものみの塔協会の初代会長、C・T・ラッセルの時代は彼が忠実で思慮深い奴隷であると考えられていた。奴隷は一人ではなく奴隷級、その数は14万4千人、その代表が統治体というのは、C・T・ラッセルの死後かなりの年月を経て作られた教理である。
この点はものみの塔協会の定款にもよく表れている。1972年3月15日号のものみの塔誌、「法人団体と異なる統治体」という記事の欄外には、ものみの塔協会の定款が載せられているので、その一部を以下に挙げることにする。
「当協会の目的は次のとおりである。すなわち、エホバの証人として知られるクリスチャン団体のしもべおよびその世界的な合法的管理機関として働くこと、キリスト・イエスの治める神の王国の福音を全能の神エホバの名前とことばと至上権に対する証として諸国民すべてに宣べ伝えること。聖書を印刷、頒布し、キリスト・イエスの治めるエホバの王国の樹立に関する聖書の真理と預言を説明する情報および注解を収めた文書を作成、出版することにより各種の言語で聖書の真理を流布すること、世界のあらゆる場所に出かけて行き、喜んで耳を傾ける人々に前述の文書を配布し、それら文書に基づいて聖書研究を司会し、公に、また家から家に聖書の真理を宣べ伝え、かつ教える代理行為者・しもべ・要員・教師・教官・福音伝道者・宣教者・奉仕者を認可し、任命すること」(下線は発行者)
この定款にある通り、実際は最初からものみの塔協会がすべてを管理し、組織内の役職の設定、任命権のすべてを牛耳っていたのである。権力の頂点に位置するのは、ものみの塔協会の幹部たちである。
| 組織の発展 | 年代 | 預言 |
|---|---|---|
| C・T・ラッセルを含む6人はペンシルバニア州アレゲーニー市で聖書研究を始める | 1870 | |
| 1876 | キリストの目に見えない再臨が1874年に始まり、異邦人の時が1914年に終わると述べた(クリスチャンは天へ帰還し、この世はハルマゲドンで終了する) | |
| 1878 | キリストの教会を構成する忠実なクリスチャンはこの年に復活すると考えられていたが、そうしたことは生じなかった | |
| 「シオンのものみの塔とキリストの臨在の先ぶれ」創刊号を出す(5000部) | 1879 | |
| 天に行く人の最終的な人数は14万4千人であると発表する | 1880 | |
| 忠実で思慮深い奴隷は一個人ではなく一つのグループであるとする C・T・ラッセル、ものみの塔冊子協会を設立 |
1881 | |
| 7月号のものみの塔誌で、「三位一体」を否定する | 1882 | |
| ものみの塔冊子協会を法人化する | 1884 | |
| ペンシルバニア州アレゲーニーに「聖書の家」が完成する(20年間協会本部となる) | 1889 | |
| ブルックリン・コロンビア・ハイツに新しい本部を建設する | 1909 | |
| 世界中で1200の会衆が機能する | 1914 | ハルマゲドンは起きず、クリスチャンが天に上げられることもなかった 「ハルマゲドン−1915年説」、さらに「ハルマゲドン−1918年説」が提唱される |
| C・T・ラッセル死亡する 年次総会にてJ・F・ラザフォードが会長になる |
1916 | |
| 5月7日 ものみの塔協会の会長を含む幹部8名に逮捕状が出される | 1918 | ハルマゲドンは来なかった |
| 5月14日 8人が釈放される 9月1〜8日 シーダーポイントで第一回、全国大会を開く(7000人出席) 「黄金時代」(現在の目ざめよ誌)創刊 |
1919 | |
| 野外奉仕の報告を伝道者すべて(8052人)が出すようになった | 1920 | |
| このころから、1925年にハルマゲドンが来るという期待が高まっていった(1925年は70回目のヨベルの年に当たると考えられていた) | ||
| グループで初めてものみの塔研究が組織される | 1922 | |
| 羊と山羊に関する例え話を説明し、羊はハルマゲドンを生き残って神の新秩序へ入る人々を表すと述べる | 1923 | |
| すべての組織を「神の組織」「サタンの組織」に分ける極端な見方を採用する 啓示12章の「女」と「男子」の説明を試みる |
1925 | ヨベルの年の預言は外れ、「終わり」は来なかった |
| 聖書の翻訳にエホバの名前を使用することの重要性が強調される | 1926 | |
| 日々の聖句と注解を載せた最初の年鑑が出る 米国にて寄付と引き換えに、本や冊子を配布する業が毎週日曜日に行われる |
1927 | |
| 十字架の使用はふさわしくないとの見解を明らかにする(1931年 使用禁止) キリストは十字架の上ではなく一本の杭にくぎ付けされたと主張する 誕生日、クリスマスの祝いが禁止される |
1928 | |
| 「エホバの証人」という名称を採用する | 1931 | |
| 長老の選出制が廃止される | 1932 | |
| 「大群衆」「他の羊」は地上の楽園で永遠に生きる人々であると発表する 国旗敬礼を拒否する 「王国会館」という名が用いられるようになる |
1935 | |
| J・F・ラザフォードが死亡し、N・H・ノアが三代目の会長となる 「神権宣教高等課程」開校(神権宣教学校) 巡回区が設けられ巡回訪問、巡回大会が始まる |
1942 | |
| ギレアデ聖書学校開校 (宣教者を養成する学校、100名が入学) |
1943 | |
| 「統治体」を強調しはじめる | 1944 | |
| 輸血を禁止する | 1945 | |
| 「目ざめよ誌」発行 | 1946 | |
| 排斥の取り決めが設けられる | 1952 | |
| 1966 | 人間創造の6000年は1975年に終了する、同時にその年はヨベルの年になっているのでキリストの千年統治は1975年に開始されると考えられた | |
| 統治体の成員を7名から11名に増員する | 1971 | |
| 1975年狂想曲、組織全体に鳴り響く | ||
| 統治体の成員を11名から18名に増やす | 1974 | |
| 1975 | 「終わり」は来なかった (かなりの成員が組織を去る) |
|
| 統治体に6つの委員会が設けられる | 1976 | |
| N・H・ノアが死亡し、F・W・フランズが会長となる | 1977 | |
| 組織支配が一段と強化される | 1987 |
| 年 代 | 伝道者数 | バプテスマ数 | 記念式の出席者数 |
|---|---|---|---|
| 1885 | 約300 | ||
| 1914 | 5,140 | ||
| 18 | 3,868 | ||
| 25 | 90,434 | ||
| 26 | 89,278 | ||
| 39 | 71,509 | ||
| 48 | 230,532 | 376,393 | |
| 58 | 717,088 | ||
| 70 | 1,384,782 | 164,193 | 3,226,168 |
| 74 | 1,880,713 | 297,872 | 4,550,457 |
| 75 | 2,062,449 | 295,073 | 4,925,643 |
| 76 | 2,138,537 | 196,656 | 4,972,571 |
| 77 | 2,117,194 | 124,459 | 5,107,518 |
| 78 | 2,086,698 | 95,052 | 5,095,831 |
| 87 | 3,237,751 | 230,873 | 8,965,221 |
※ 1914年、1925年、1975年、終わりの預言はずれる。
誠実なエホバの証人の多くは真理を心から愛しており、真理の神エホバにふさわしく生活しようと努めている。偽善的な組織の幹部とは異なり、彼らは真理の民としての責任を真剣に受け止めている。偽りや偽証、偽善は闇の業、サタンの業であり、エホバが最も忌み嫌われる事柄であることをよく知っている。
それで、もし次の点
が立証されるなら、心から真理を愛するエホバの証人は組織から出てくるはずである。
エホバの証人を救出するための最も効果的な方法は、ものみの塔協会が真理の組織、神の組織ではないことを明らかにすることである。
ここで大切なのは、しっかりと土台をすえること、確認作業をキチンとすることである。どの程度の成果を上げられるかは、この段階をいかに確実に行うかにかかっているといっても過言ではない。
適当な聖句があればどれでもかまわないと思うが、ヨハネ3章19〜21節は是非とも推薦したい聖句である。というのは、ものみの塔協会はこの聖句をキリスト教諸教会に適用して次のように宣伝してきたからである。
「エホバの証人が教会員の人々に伝道すると、そのうちの多く人は話し合いを避けて逃げてしまう。真実を明らかにする話し合いを拒むのは闇にいる者、偽善者の特徴であり、それこそ彼らが大いなるバビロン、サタンの組織に属している証拠である」と。
「19 さて、裁きの根拠はこれです。すなわち、光が世に来ているのに、人々が光よりむしろ闇を愛したことです。その業が邪悪であったからです。20 いとうべき事柄を習わしにするものは、光を憎んで光に来ません。自分の業が戒められないようにするためです。21 しかし、真実なことを行う者は光に来て、自分の業が神に従ってなされていることが明らかになるようにします」
諸教会の消極的な態度がものみの塔協会の宣伝に一役買っていたわけである。したがって、それをそっくりそのまま、ものみの塔協会に返してあげるのが最善ではないかと思う。
これらの確認事項は、できれば一緒に聖句を開いて確かめる方がよいと思うが、相手が十分に知っているようであれば口頭だけでもよいかもしれない。ものみの塔協会は狡猾で最後になるとなりふりかまわず権威を振りかざすので、逃げないようにするにはエホバの名にかけて約束してもらったほうがよいだろう。
ものみの塔協会が神の組織ではないという具体的な証拠を挙げ、相手のエホバの証人の返答を問う。
話し合いのための資料の中に載せられている証拠の手紙は小冊子を開いて見せるほうが効果的であると思うが、翻訳の欠陥や教義の間違いは直接論じ合う方が勝っている。
エホバの証人に関する文書は今までにも何冊か出版されてきた。おそらくまだ研究中の人や、すでに組織に疑問を抱いている人にはかなり効果があったのではないかと思うが、活発なエホバの証人にはそれほどインパクトはない。
理由としては様々な要因が考えられるが、内部の感覚で言えば主に以下の点を挙げることができる。これは本やパンフレットだけではなく、エホバの証人に伝道するときにも当てはまることである。
ものみの塔協会は伝統的なキリスト教の教理を批判、攻撃して成長してきた教団であり、組織の中で中核となっているのは伝統的なキリスト教にあき足りなかった人々である。加えて毎週開かれる集会では、伝統的なキリスト教の教えに対する攻略法の訓練が実にていねいに行われている。
「あなたがたは間違っている」といわれても、それが伝統的なキリスト教の教えを根拠にしたものであれば、「あの人たちは私たちの捨てた教えに基づいて批判しているに過ぎない。そういう解釈はすでに古い」というくらいにしか思わない。したがって、伝統的なキリスト教の教理で攻撃されても、ほとんど問題意識を感じないわけである。
C・T・ラッセルは商人の子供で、神学校も出ていない。彼は妻にもそむかれた、だらしのない夫であった。ラザフォードは刑務所に入れられていたことがある、エホバの証人は自分の救いのために雑誌売りをしている、等々。
こういう記述は感情的な人には訴えるかもしれないが、内部の人には著しく本の信用度を低めるものになってしまう。それどころか積極的な逆効果もある。「イエス・キリストも、当時のユダヤ人の主流にはさげすまされていたナザレの出身であった、教えと関係ない次元で非難を受けるのは、むしろ神に是認されている証拠である」という具合に、宗教心理特有の考え方をするわけである。
三位一体論、キリストの神性、十字架による救い、これらの教えは確かにキリスト教の根幹をなす重大な教えである。しかし、エホバの証人にとっては必ずしもそうではない。教義上の建前はともかくとして信仰を支える最も重大な教えは他にある。その点を扱わない限り、エホバの証人にはそれほど大きな影響はない。
エホバの証人にとっては、組織論と預言が信仰の最大の基盤である。猛烈な伝道のエネルギーもここから出てくる。この砦をくずさないかぎり、エホバの証人をものみの塔協会から解放することは不可能であろう。ものみの塔協会もこの点だけは必死で守ろうとするだろうし、エホバの証人の抵抗も強いとは思うが、攻略してしまえば最大の成果を上げることができる。
したがって、この小冊子ではエホバの証人の信仰の最大の基盤に焦点を当てることにした。また、伝統的なキリスト教の教理は使わず、ものみの塔協会の教理そのものの内部矛盾を突くという方針を取った。この小冊子の資料だけではまだ不十分だと思うので、多くの人々の協力により、さらに充実した資料が作成されることを期待したい。
今までに寄せられた報告からすると、組織内の人に最も大きな衝撃を与えたのは、「事件簿」で明らかにされた幹部の『公約違反』と『偽善』であった。
これはエホバの証人の信条からすると当然のことである。というのは、楽園に導く唯一の組織であると信じていた統治体、ものみの塔協会が『偽善の組織』だということになると、将来の楽園の約束が全く信用の置けないものになってしまうからである。それだけを楽しみにしてがまんして奉仕しているエホバの証人にとってみれば、これは実に深刻な問題となる。
加えてものみの塔協会の宣伝も良かったのである。純粋な人はそれを鵜呑みにして信じている。例えば、「二十世紀のエホバの証人」という小冊子(p.21)には、
「言うことと行うことが違うのは偽善であって、宗教上の偽善は多くの人を聖書から引き離してきました。…書士やパリサイ人もヘブライ語聖書を持っていましたが、イエスはそれらの人々を偽善者としてとがめました。…クリスチャンが正しい生き方を自ら実践するなら、それは幾時間もの説教に勝る説得力となります。」(下線は発行者)
また「王国宣教学校の教科書」(p.85)には
「あなた方の兄弟たちの間で聴聞を行うとき、あなた方は…義をもって裁かねばならない。」(申命1:16新)人々の命や関係に影響する問題を裁くのは重大な責任です。長老たちは…妥当な程度の完全な理解を得なければなりません。…どんな時でも、偏らずに行動しなければなりません。−テモテ第一5:21
と記されている。
これは間違いなくものみの塔協会の「公約」である。こういう主旨のことは、機会がある度にものみの塔誌や目ざめよ誌でも宣伝しているわけだから、この公約は守られているはずだと普通のエホバの証人は考える。まさか、不公正で不義に満ちた裁判がまかり通っているとは、模範とならねばならない幹部が率先して裁きを曲げているとは夢にも思わない。何しろこの人たちは千年統治でキリストの代理をして地球を治めると言っているのだから。
ところが、実態は宣伝とは大幅に異なっている。ものみの塔協会の『公約』がいかに信用の置けないものであるか、組織の幹部に都合が悪くなるといかに簡単に破られてしまうものであるかは、今回の広島会衆の事件が端的に示している(詳しくは、「事件簿」北海道広島会衆発行を参照)。おそらく大多数のエホバの証人は自ら経験しないと、なかなか信じられないのではなかろうか。
世界中で不当な裁判を受けた人々は膨大な数に上るものと思われる。組織に都合の悪い者は背教者にして片付けてしまう。このパターンの被害にあった人は少なくないだろう。広島会衆の問題は、ものみの塔協会の真実の姿を明らかにした典型的な事件であろう。
浮き彫りになった裁判の制度上の欠陥、組織の偽善、偶像崇拝の一部を以下にまとめて記す。
「エホバの証人に考えさせるべき点」
ものみの塔協会の審理委員会、その裁判制度は神の組織にふさわしいものだとはいえない(エホバの証人は裁判ではなく「審理」という用語を用いる)。
偽善的な体質を確かめるのは簡単である。幹部にとって一番都合の悪いところ、最も触れて欲しくないところを突いてみればよい。それでも良心的に行動してくれるなら、その組織は本物である。
しかし偽善者はそうではない。いかに仮面が厚くてもしだいに化けの皮がはがれてくる。最初はいかに調子がよくても、だんだん言うことが変わってくるし、態度もおかしくなってくる。最後は仮面がはがれるのを恐れて逃げてしまう。
一番聞いてほしくないところ、最も都合の悪いところを突っ込んで行くと、偽善的な組職は必ずこのようになる。日本支部のたどったパターンはまさにこうであった。
次のページの手紙は、日本支部の偽善の決定的な証拠といえるものである。
加藤さんは、「自分たちがエホバの裁きを行ったという確信があるなら、誰にはばかることなくその根拠と理由を明らかにできるはずではないか。当事者にも納得できるようはっきり聖書から説明すべきである」と日本支部に書き送った。この手紙はそれに対する返事として、日本支部が送ってきたものである。
|
ペンシルバニア州の
ものみの塔 聖書冊子協会 1985年11月4日 061-○○北海道札幌郡広島町○○○ 前 略 あなたは最近、当協会の奉仕者本間 年雄氏にご質問の手紙をお送りになられたようです。わたしたちは以前にもあなたから同様の手紙をいただいておりましたので、ここに当協会の見解をお知らせすることにいたします。 ものみの塔聖書冊子協会の職員もまたクリスチャン会衆内にあって聖職者の立場で働いている長老たちも自分たちの職務を果たす上で、聖書に定められている神の律法および法律が定めた種々の要求につき従うことを堅く決意しております。ご存じのように聖職者に対する刑法上の一つの規定は、刑法第二編第13章第134条にある秘密漏泄罪に関するものです。その一部をここに引用いたします。「宗教・・・ノ職二在ル者又ハ此等ノ職ニ在リシ者故ナク其業務上取扱ヒタルコトニ付知得タル人ノ秘密ヲ漏泄シタルトキ亦同シ」。 したがって、長老の職にある者(たち)がクリスチャン会衆内での特定の業務を取り扱った結果、当人から知らされた情報のみならず、推理や調査などによって知り得た秘密の事実をまだ知らない人に告知することは、漏泄罪に相当するものです。この理由によりあなたがお尋ねになっている件に関しては、当協会のみならずクリスチャン会衆内に聖職者の立場で仕えるいかなる長老もあなたの求めに応じて情報を提供することができないことをここにお知らせいたします。どうぞご了承ください。 聖書教育に励む
Watch Tower B.&T.Society of Pennsylvania 非営利法人団体 |
原本の画像は→こちら
ものみの塔協会は、実際はエホバよりも「組織」という名の偶像、「組織」という名のバアルを崇拝しているのではないか。
もし、組織崇拝でないというのであれば、ものみの塔協会は真理、真実を擁護するはずである。ところがものみの塔協会は、現実には真理、真実よりも「組織の取り決め」を優先しており、成員にもそのように指示している。次の手紙はその証拠となるものである。
これは「なぜ勇気を持って真理、真実を擁護しないのか。真のエホバの証人ならそうすべきではないか」という呼びかけに対して、審理委員会の一長老から届いた返事である。
|
DATE 1985・12・6 前略、金沢 司 様 度々 お手紙をいただいていますが、私としては、会衆の一長老として、全面的に、その組織の取り決めに従って歩む決意でいます。皆さんが現在、排斥者であるという事実は、私が今この組織にとどまっている以上、この件に関するエホバ神と組織の取り決めを踏み越えることはできませんので 一切の交わりを持てないことを意味します。それは単に勇気とか個人的な見解の問題ではありません。私が行動できるのは、「務め」の本のP 149、150の場合のみです。例外はありません。 上記お知らせします。 署 名 |
画像は→こちら
以下にこうした新世界訳聖書の欠陥を示す具体的な例を記す(詳しくは「欠陥翻訳−新世界訳」参照)。
「あなた方の中に、扉を閉じる者がだれかいるだろうか。そしてあなた方はわたしの祭壇に火を付けない−何の理由もなしに。わたしはあなた方のことを喜ばない」と、万軍のエホバは言われた。「あなた方の……供え物をわたしは喜びとはしない。」
文脈からも明らかなように、エホバはもっとたくさんの犠牲が欲しいといっているのではなく、むしろその反対で、まったく無価値な犠牲を捧げるのを止めるようにと促しているのである。そのような犠牲を捧げるよりは、神殿の扉を閉じた方が良いとみなすほど、神は偽善的な崇拝を嫌っておられたのである。
当然のことながら、犠牲を捧げるためにはその前に神殿の扉を開け、祭壇に火を付けねばならない。新世界訳のように訳すと、「どうして神殿の扉を閉じるのか。あなたがたは何の理由もなく犠牲を捧げようとしない」の意味になり、犠牲を捧げないことを叱責していることになってしまう。つまり、「もっと犠牲を捧げろ、もっと捧げ物を持ってこい」と要求する貪欲なエホバになってしまうのである。
「あなたがたがわたしの祭壇に、いたずらに火を点ずることがないように、戸を閉じる人は、だれかいないのか。……わたしは、あなたがたの手からのささげ物を受け入れない。」(新改訳)
ヨブを慰めに来た偽善的な三人の自称友は、ヨブが性的不道徳のような隠れた罪を犯しており、苦しみにあっているのは神がそれを裁かれたためではないかとほのめかした。この節はそれに対してヨブが自らを弁明しているところである。
「契約をわたしは自分の目と結んだ。それゆえ、どうしてわたしは自分が処女に対して注意深いことを示すことができようか。」
新世界訳のように「どうして注意深いことを示すことができようか」と訳すと、「そんなことはできない」と続くことになる。そうすると結局、ヨブは「処女に対して注意深くはない、言い換えれば用心、警戒していたのではない」ということになってしまう。それでは自ら不道徳を認めたも同然で、「目と契約を結んだ」と述べている前の記述と矛盾する。
「私は自分の目と契約を結んだ。どうしておとめに目を留めよう」(新改訳)
- 異国の者たちの手からわたしを自由にし、救い出してください。彼らの□は不真実を語りました。その右手は虚偽の右手です。
- 彼らは[言います]、『我々の息子たちは、その若いときに成長した小さな植物のようだ……
- 我々の牛はよくはらみ、裂傷もなければ流産もなく、我々の公共広場には叫びもない。
- [この]ようになる民は幸いだ!エホバをその神とする民は幸いだ!
この翻訳によれば、「不真実を語る異国の者=12節の彼ら、我々=15節の幸いな民・エホバをその神とする民」となる。剣でダビデを脅かし、偽りを弄して彼を欺こうとした異国の民が、何と、エホバの祝福を受ける幸いな民になってしまうのである。
- 私を、外国人の手から解き放し、救い出してください。彼らの□はうそを言い、その右の手は偽りの右の手です。
- 私たちの息子らが、若いときに、よく育った若木の……
- 私たちの倉は満ち、あらゆる産物を備えますように……
- 幸いなことよ。このようになる民は。幸いなことよ。主をおのれの神とするその民は。(新改訳)
こうすると、11節の「彼ら」と12節の「われら」は同じではなく、別の人になるので矛盾は生じない。
「そして、イスラエルがその地に幕屋を設けていたときであったが、ルベンは一度、父のそばめビルハのもとに行ってそれと寝た。そして、イスラエルはそのことについて聞いた。こうしてヤコブの十二人の息子が生まれた」
「こうして」という語は、前の部分を受けてその結果を表す接続詞である。この訳では、ヤコブの十二人の息子が生れたことの要因にルベンの淫行が関係していたことになってしまう。この記述をみたらヤコブの息子たちもさぞかし驚くことであろう。
「イスラエルがその地に住んでいたころ、ルベンは父のそばめビルハのところへ行って、これと寝た。……さて、ヤコブの子は十二人であった。」
新世界訳聖書の一つの大きな特徴は、ヘブライ語やギリシャ語のある特定の言葉に対して、同一の訳語が当てられているということである。これが不正確さの一つの要因になっている。
典型的な例の一つとして「気遣い」をあげることにする。広辞苑には、「気遣い」とは「あれこれと心を使うこと、心づかい、気がかり、心配」とあるが、今は主に他の人のために心を配るときに用いるのが普通である。「心配だ」というとき「気遣いだ」とは言わないし、「気がかりです」というのも「気遣いです」とは言わない。
こういう意味で見てみると、特にヨブ記に妙な表現が多いのに気付く。次に挙げたのはそうした聖句の中の代表的なものである。
(ヨブ7:13) 「わたしの寝床はわたしを慰め、わたしの床はわたしの気遣いを支えるのを助けてくれる」
(ヨブ10:1) 「わたしの魂は自分の命に対して確かに嫌悪を感ずる。わたしは自分についての気遣いを漏らそう。わたしは自分の魂の苦しみのうちにあって語ろう!」
(ヨブ15:4) 「ところが、あなたは、神の前に恐れを無力にさせ、神の前に気遣いを抱くのを少なくする」
(ヨブ23:2) 「今日もまた、わたしの気遣いの様子は反逆であり、わたしのこの手は嘆きのゆえに重い」
まず、7章13節の「わたしの気遣いを支える」という訳文であるが、分かりにくいのは「わたしの気遣い」という表現である。これだと自分を気遣っている(心配している)のか、それとも誰かを気遣っている(心遣い)のかよく分からない。加えて、「支える」の主語はわたし、つまり、ヨブなので、文意はヨブが自分で自分の気遣いを支えているという、何とも妙な文章になる。
ヨブの状況を考えると、ここはロバート・ゴルディスによる私訳のように「嘆き」か「苦悩」を用いる方がよい。
「わたしの臥所(ふしど)がわたしを慰め、わたしの寝床がわたしの嘆きの重さを共にしてくれる」
ヨブ15章4節はテマン人エリパズがヨブを非難しているところである。このエリパズという人は、ヨブを慰めにやって来た三人の偽善者のうちの一人であった。
15章4節を読むと明らかなように(ただし、神の前に恐れを無力にさせるというのは何のことかよく分からないが)、エリパズの「気遣いを抱くことを少なくする」という言葉は、ヨブに対する非難であることが分かる。このことからすれば、当然のことながらヨブは「神のことをあまり気遣ってはいなかった」ということになる。
ところが、10章1節の「わたしは自分についての気遣いを漏らそう(2節『わたしは神に申し上げることにする』から、この気遣いは神に向けられたものであることがわかる)」、23章2節の「今日もまた、わたしの気遣いの様子は反逆であり」から明白なように、ヨブは自分から進んで気遣いを漏らしており、しかもそれは毎日のことであったと考えられる。
一方で「少なくする」と非難し、他方で「毎日のように多い」という。これは明らかな矛盾である。
「わたしの魂は生きることをいとう。嘆きに身をゆだね、悩み嘆いて語ろう」(ヨブ10:1)
あなたは神を畏れ敬うことを捨て嘆き訴えることをやめた」(ヨブ15:4)
「今日も、わたしは苦しみ嘆き、呻きのために、わたしの手は重い」(ヨブ23:2)
ものみの塔協会は
「『新世界訳』を読む人はその言葉遣いによって霊的に覚せいさせられ、霊感を受けた元の聖書の力強い表現にすぐなじんで読むことができるようになります。あいまいな表現を理解しようとして何度も節を読み返す必要はもはやありません」(「霊感」p.330)
と宣伝しているが、実際はこれとは正反対である。
アダムとエバが住んだパラダイス、エデンは美しく肥沃な地であり、そこから四つの川が流れ出ていた。新世界訳によるとその川は四つの頭になったという。
「さて、川がエデンから発していて園を潤し、そこから分れ出て、いわば四つの頭となった」
普通「川が頭になる」といえば、まず擬人表現以外には考えられない。しかしここは事実をそのまま記述しているところであって、擬人表現を用いるような箇所ではない。
意味としてはエデンの地が四つの川の水源になっていたということなので、「四つの源となっていた」と訳すのが妥当である。
これはソロモンの知恵や繁栄に驚嘆したシバの女王の言葉である。あまりの素晴らしさに気が動転してしまったのであろうか、「?」と思うようなことを口走っている。
「あなたは知恵と繁栄の点で、私のお聴きした、聞かされたことをしのいでおられます」
「お聴きした、聞かされたこと」……? 誰でも一度は読み返すに違いない。何とも奇異な感じのする表現である。
息子アブサロムの反逆に遭い、逃走するダビデが自分に従ってきたギト人イッタイの安否を気遣い、戻るように勧めている場面である。
「あなたは昨日来たばかりで、今日わたしはどこか行こうとしているところへ行くところなのに、あなたを行かせて我々と共にさまよわせるというのか。戻って行き、あなたの兄弟たちを共に連れて戻りなさい」
突然の反逆に驚き、惑ったダビデ王は思わず舌がもつれてしまったのであろうか。「to go when I am going wherever I am going?」を上記のように訳したのであるが、中学生でもこういう訳文は作らないだろう。
新改訳の「私はこれから、あてどもなく旅を続けるのだから」や、日本聖書協会口語訳の、「わたしは自分の行くところを知らずに行くのに」ぐらいが自然な表現であろう。
人々は金や銀を求めて地底深く潜って行く。宝を得るためにはあらゆる困難をものともせず一生懸命に働く。
しかし、貴金属よりはるかに価値のある真の知恵はいったいどこに見い出すことができるのであろうか。はたして人はそれを探り出すことができるだろうか。その本当のありかは神だけが知っている。
こうしたことを詩的に表現した箇所の一部が、次の一節である。
「人は[人々が]外国人としてとどまっている所から遠く離れて立て坑を掘り下げた。足から遠く忘れられた所で。死すべき人間のある者たちは、ぶら下がり、ぶらぶらしていた」
何とも理解し難い訳である。前半の方は何とかわかるとしても、後半は思わず吹き出ししてしまいそうな訳になっている。これでは処刑される人かあるいは死のうとしている人がどこかに引っ掛かって、ブラブラしているような印象を与えてしまう。
ゲセニウスなどのヘブライ語辞典はこの聖句について、「ロープで体を縛った炭坑労働者が穴を昇り降りするときに、揺られる状態」と述べている。上記の訳のように笑いがこみ上げてくるようなものではなく、もっと危険な状況を表していたのである。
またあなたは、肉の大きなあなたの隣人、エジプトの子らと売春を行い、あなたの売春をあふれさせてわたしを怒らせた」
「ノフとタフパネスの子らもあなたの頭の頂きを食らいつづけた」
「心配のない者は、考えにおいて、消滅に対して侮べつを抱く」
「あなたは平和の地で自信があるのか。では、ヨルダン沿いの誇り高い[やぶ]の中ではどうするのか」
「わたしの目は注ぎ出されて、とどまることがない」
「それらはわたしの食物の中の変質のようだ」
「そして、離れ落ちてゆく者たちはほふりの業に深く下り、わたしは彼らすべてに対して訓戒であった」
「わたしは必ずその敵の地で彼らの心の中におじ気を入れる」
などなど、数え切れないくらいの迷訳、珍訳がある。
新世界訳はおびただしい数の接続詞や代名詞をそのまま訳出しているが、これがわかりにくさのもう一つの原因になっている。
実にくどい代名詞の例を一つだけあげる。
「それは、わたしがあなた方を追い散らし、あなた方が、あなた方もあなた方に預言している預言者たちもが、必ず滅びうせるためである。」(エレミヤ27:15 下線は発行者)
現在のものみの塔協会の体質の中で最も顕著なものは、何といっても、組織賛歌、組織主義、組織支配、組織崇拝、組織バアルである。すでに「組織」が偶像化され、崇拝を受けているのである。
その体質が反映されている問題の聖句は、出エジプト記14:31、19:9、フィレモン5節である。
「民はエホバに対して恐れを抱き、エホバとその僕モーセに信仰を置くようになった」(出エジプト14:31)
「するとエホバはモーセにこう言われた。『見よ、わたしは暗い雲のうちにあってあなたに臨む。わたしがあなたと話す時に民が聞くため、そして彼らがあなたに対しても定めのない時まで信仰を置くためである』。」(出エジプト19:9)
「わたしは、祈りのなかであなたのことを述べるさい常にわたしの神に感謝しています。あなたが主イエスとすべての聖なる者たちに対して抱く愛と信仰についてつねに聞いているからです」(フィレモン4,5)
このように訳すと、非常に重要な教義上の問題が生じてくる。つまり、信仰の点で、神と人間が同レベルになってもよいのか、人間が人間に信仰を持つことは正しいのかという問題である。
新世界訳委員会は、人間に信仰を持っても良いと判断したようで、エホバとモーセが同列に扱われているし、エホバ自らモーセに信仰を置くようイスラエルの民に勧めている。フィレモンの手紙の方は、パウロを含む聖なる者全員にフィレモンが信仰を持っており、パウロ自身もそれを誉めているということになっている。
それでは他の聖書もみなこのように訳しているのかというと、決してそうではない。例えば新共同訳は、
「というのは、主イエスに対するあなたの信仰と、聖なる者たち一同に対するあなたの愛とについて聞いているからです」
というふうに「信仰」と「愛」を分けて訳している。新改訳、現代訳の翻訳もこれと同様である。
結局は解釈の問題といえるが、どちらの翻訳を選ぶかは、人間に対して信仰を持つことが聖書の教えにかなっているのか、それともそうではないのかという教義上の判断によることになる。
聖書全体の教えや精神を考慮すると、どうしても聖書が人間に信仰を持つよう勧めているとは考えにくい。証拠は圧倒的に新世界訳に不利である。
例えば、コリント人への第二の手紙5章7節は、
「わたしたちは信仰によって歩んでいるのであり、見えるところによって[歩んでいるの]ではありません」
と述べて、クリスチャンの真の信仰は、見える者に依存しているのではないということを教えている。このように諭したパウロが、フィレモンには自らその逆のことを書き送るとは、まず考えられない。
さらに、詩編146編3節は、
「高貴な者にも、地の人の子にも信頼を置いてはならない。彼らに救いはない」
と明確に記している。
要するに、文法的にも聖書的にも「モーセに信仰を置く、聖徒に信仰を置く」と訳さねばならぬ必然性はまったくないのである。そうである以上、新世界訳の訳文はものみの塔協会の純粋な解釈または方針ということになろう。
これは組織支配、組織崇拝には非常に都合のよい翻訳である。なぜなら日本語の「信仰」の感覚では
「神・仏などを固く信じ、その教えを守り、それに従うこと(心)。また、ある物事を絶対視して、信じること(心)」(学研国語大辞典)
ということになってしまうからである(英語の「faith」も辞書を見る限りではあまり大差はない)。
ここで注目すべきは「信仰」のレベルになると、「絶対視」する傾向が出てくるということである。ものみの塔協会の場合、「現代の聖なる者」の代表は「統治体」という教義になっているので、これは統治体絶対、「組織盲従」の体質を生み出す翻訳になる。
加えて、「崇拝」とは「あるものに信仰を置くこと」なので、新世界訳は「組織」という名の神を拝むよう勧めている聖書であるともいえる。ものみの塔協会の偶像は「統治体」を頂点とする「組織神」である。
新世界訳委員会、ものみの塔協会、統治体は確かに意識して「信仰」という訳語を選んでいる。というのは、ものみの塔誌には次のように書かれているからである。
「エホバへの信仰、エホバが代弁者として用いておられる人々に対する信仰、そうですエホバの組織に対する信仰です! わたしたちが今日エホバへの奉仕に『出て行く』とき、そのような信仰を働かせるのは本当に重要なことです。」(ものみの塔 1984 7/l p.15,15節 、下線は発行者)
組織の代表者に対する信仰、組織そのものに対する信仰を持つべきであると断言している。
エホバの証人は「1914年に終わりの時が始まった、キリストの臨在は1914年に開始された」と堅く信じている。この教えは「神の組織、統治体」の教義と並んで、ものみの塔協会の最も重要な柱となっている。エホバの証人が終わりは近いと強調する最大の根拠は、1914年−キリスト臨在説である。
もっとも最近では、1914年という年が統治体にとってだいぶ重荷になってきているとの指摘がある。1975年が外れた直後は、「1914年から数えて一世代のうちに終わりが来ます。一世代は70〜80年の長さを指しています。やはりハルマゲドンは近いのです」とよく言っていたものであるが、はや限界の1994年もあとわずかになってしまった。
「世代は厳密な意味で長さを表しているのではありません。1914年当時の人々全体を指していますとか、その時代の特徴を象徴していると考えられます」といったふうに、世代の意味を変えてごまかそうとしているようであるが、いつまでもこのままではすまないだろう。 [STOPOVERによる注記:金沢氏の予想通り、1995年に解釈は変更された。参照(JWIC)]
この「1914年」という年を初めて提唱したのは、ものみの塔協会の初代会長C・T・ラッセルであった。
「C・T・ラッセルは、『異邦人の時、それはいつ終わるか』と題する記事を出しました。それは1876年10月号の『バイブル・イグザミナー』誌に掲載されました。その中でラッセルは『七つの時は西暦1914年に終わるであろう』と述べています。」(1976 年鑑 p. 37)
彼はまず、ルカ21章24節に記されている「異邦人の時」に関するキリストの預言に注目した。
「人々は剣の刃に倒れ、捕らわれとなってあらゆる国民の中へ引かれてゆくでしょう。そしてエルサレムは諸国民の定められた時が満ちるまで、諸国民に踏みにじられるのです。」(新世界訳)
新世界訳は「諸国民の定められた時」という表現を使っているが、一般的には「異邦人の時」として知られている。ラッセルはこの「異邦人の時」の長さを計算しようと聖書の中を探し回った。そして見つけたのが、ダニエル4章に出てくる「七つの時」であった。「異邦人の時」と「七つの時」、この両者を結びつけそれが同じ期間を指していると考えたのが、彼の新しい閃きだったのである。
計算は次のように行われた。
| 「7つの時」 | = 「7年」 | |
| 「1年」 | = 「360日」(太陰暦に基づいて) | |
| 「7つの時」 | = 「2520日」(360×7=2520) | |
| 「1日」 | = 「1年」(民数14:34、エゼキエル4:6に基づき、1日を1年として数える) | |
| 「7つの時」 | = 「2520年」 |
このようにして「異邦人の時」の長さは「2520年」と算定された。続いてラッセルは「異邦人の時」の起点をエルサレムがバビロニア帝国に滅ぼされたBC607年と考え、そこから「2520年」を流れ下り、「1914」年を導き出したのである(2520-607=1913になるが紀元0年はないので1を足す)。
最も強力な批判はダニエル書4章の解釈に向けられた。ものみの塔協会は、ネブカデネザルの見た夢のなかの「巨大な木」が「神の主権」を表し、「七つの時」は「異邦人の時」を表すと説明しているが、ダニエル書にはそのようなことが一言も記されていない(引用はしないが是非ダニエル書4章を開いて確かめていただきたい)。
ダニエルの解き明かしを読んでみると明らかなように、「七つの時」とは、ネブカデネザルが神によって王位を追われる期間であることがわかる。それ以外の意味は説明されていない。「異邦人の時」を示唆するようなことはどこにも述べられていないのである。
またキリストが「異邦人の時」について預言したときも、「七つの時」と関連するようなことは何も語ってはいない。ダニエル4章の幻を匂わせるようなことは、一言も話されなかったのである。つまり、「七つの時」と「異邦人の時」の双方を結びつける直接の記述は、聖書のどこにもないということである。
したがって当然のことながら、次のような批判が起きてくる。ダニエルもキリストも何も語っていないのに、どうして「七つの時」と「異邦人の時」を結びつけるのか。そのように解釈できる聖書的な根拠はどこにもないではないか。
こうした批判に対し、ものみの塔協会は次のように反論してきた。論点は主に二つであるが、これはかなり苦しい論議である。
まず(1) の点であるが、これはダニエル書を全部読んでみればそれではっきりする。確かにダニエル書が全体として「終わりの日」に焦点を当てているのは事実であるが、しかし、すべての幻や啓示がそうだというわけではない。例えば、5章の「壁に記された奇跡的な文字」などはその一つになる。
結局、4章の「巨大な木の夢」がどちらになるかは主観の問題といえる。ただ、ダニエル書の他のところは「終わりの時」に関係があればはっきりそのように書かれているが、4章には「終わりの時」を示す箇所は全くない。何も述べられていないことを論証しようというのは非常に苦しい。その方が不利なのは言うまでもない。
次に(2) の点であるが、これもやはり単に視点の問題にすぎない。ネブカデネザルは正気を失い動物のようになってしまったわけだから、そういう意味では「最も立場の低い者」ということができた。神は彼を再び王位に戻し、結果としてネブカデネザルは神を至高者と讃えることになった。当時の世界支配者が神の主権を、その至上権を確かに認めたのである。そうであれば「主権は誰にあるのか、それを疑問の余地なく明らかにする」というこの幻の目的は十分達成されたといえる。「巨大な木」がネブカデネザル以上のもの、「神の主権」を表しているというものみの塔協会の主張には何の根拠もないのである。
むしろ、幻の達成という点では、「七つの時」が終了したとされる1914年の方がはるかに弱い。というのは神の至上権を立証するような出来事は、1914年には何も生じなかったからである。
結論として言えることは、「異邦人の時」と「七つの時」を結びつける正当な聖書的根拠は何もないということである。
預言の解釈というのは実際の成就がすべてである。現実にその通りのことが起きて初めて正しい解釈といえるのであって、そうならなければ結局その解釈は間違っていたことになる。ラッセルの解釈は正しかったのかそれとも間違っていたのか、これは本当に1914年に「異邦人の時」が終了したといえる出来事が生じたのか、それともそうではなかったのか、それによって決定されることになる。
ラッセルが1914年について預言していたのは次の点である。
ところが、1914年が近づくにつれて、C・T・ラッセルは預言が外れた場合のことを懸念するようになったらしい。徐々にトーンダウンするような発言が多くなった。
例えば1912年12/1号のものみの塔誌では、
「最後に、わたしたちは、1914年とか1915年10月、あるいは他の何らかの日付までではなく、『死に至るまで』捧げた[献身した]ことを記憶しましょう。わたしたちが預言の計算を間違うことを何らかの理由で主が許されたとしても、時代のしるしからして、その間違いが大きいものであり得ないことを確信できます」
さらに1914年1/1号のものみの塔誌では、
「わたしたちは、時に関する事柄を教理的な事柄と同様の絶対的な正確さを付して読まないでしょう。なぜなら、聖書の中で、時は基本的な教理ほど明確に述べられていないからです。…もし、教会が1914年までに栄化されないことが後日はっきりしたなら、主のご意志がどのようなものであれ、満足するように努めるでしょう」
と語ったと伝えられている(1976エホバの証人の年鑑 p.74)。
またある時ラッセルは、私は個人として何らかの預言をしたのではなく、単に聖書預言の解釈をしたにすぎない、それを信じるかどうかは読者の判断に任せる、というような主旨のことまで述べている。
これを巧妙な事前の責任逃れ、責任転嫁と取るか、それとも愚直で正直な態度とみなすかは評価が分れると思うが、常識的には期待を抱かせて人々を集めている以上無責任だということになろう。何やらその後のものみの塔協会の対応を予示させるような発言ではある。
実際は、人々は天へ行く期待を大いに高め、ものみの塔協会の代表者たちもそれをあおった。
ドワイト・T・ケンヨン姉妹はこう語っています。「わたしたちが考えていたのは、戦争が革命へ、また無政府状態へと進展し、当時油注がれていた、つまり聖別されていた人々はその時に死んで栄化されるだろうということでした。ある晩、わたしはエクレーシア(会衆)全体が汽車に乗ってどこかに行く夢を見ました。雷といな光がすると、たちまち仲間の人たちがあたり一面死に始めたのです。わたしは、それがごく当然だと思って死のうとしましたが死ねませんでした。それにはほんとうにあわててしまいました。それから突然わたしは死んで、大きな解放感と満足感を味わいました。この古い世に関する限り、万事がまもなく終ろうとしていること、また、『小さな群れ』の残りの者が栄化されようとしていることを、わたしたちがどれほど確信していたかは、これでおわかりいただけると思います。」
「1914年のサラトガ・スプリング大会での出来事は、その年に天へ『帰還する』というマクミラン兄弟の考えを特に際立たせました。兄弟は次のように書いています。『わたしは、水曜日(9月30日)に、「万物の終わりが近づきました。冷静にし油断なく見張り、祈りなさい」という題の講演をするように頼まれました。…その話の中で、わたしは、「わたしたちはまもなく帰還するのですから、おそらく、これがわたしの最後の講演となるでしょう』というふさわしからぬことを言ってしまいました」(1975年鑑 p.72、73)
おそらく最近エホバの証人になった人は皆、ラッセルの預言は成就したと信じているはずである。ものみの塔協会は、「1914年に気を付けろ! それが町々を行く聖書文書頒布者たちの合言葉であった。この預言は異例の成就をみた。神はラッセル兄弟に異邦人の時が1914年に終わることを四十年近く前に啓示されたのです」という具合に宣伝しているからである。
だが、これは物事のほんの一面にすぎず、真実は大幅に異なっていた。確かに第一次世界大戦という大規模な戦争は起きた。そういう意味ではものみの塔協会の宣伝通り、預言は成就したと言えないこともない。しかし、ラッセルは第一次世界大戦が起きるという主旨の預言をしていたのではない。彼のメッセージの中心は、あくまでも当時の聖書研究者たちが期待していたように、ハルマゲドンと昇天からなっていたのである。
人々が最も期待した事柄は何一つ生じなかった。この世が終わることもなければ、会衆が天に迎えられることもなかった。1916年の暮れにはC・T・ラッセルが死亡し、1918年には第一次世界大戦が終了してしまう。ハルマゲドンが来ないことは決定的になり、失望した人々は組織から離れていった。ラッセルの預言は外れたのである。
組織存続のため見解の修正は急務となった。調整は次のように行われた。
「確かに1914年に異邦人の時は終わった。キリストは天で王位に就いたのである。すでに神の王国は天において支配を開始している。1914年から終わりの日という一つの時代が始まり、キリストは目に見えない様でその時からずっと臨在している。大患難は1914年に始まったのではなく、終わりの日の最終部分に生じる出来事である。ハルマゲドンは大患難の頂点をなす。信仰の篤い霊的な目を持つ人々はそれを理解することができるはずである。」
キリストの臨在、終わりの日の始まりは「1874年」から「1914年」に変えられた。ハルマゲドンの年は1914年から1915年、1918年、1925年、1975年と幾度か変更されてきたがことごとく外れてしまったので、現在では特定の年を指定することは止めてしまった。
要するに、ものみの塔協会は預言の成就を地上から天に移し替えたわけであるが、この地上から天に置き換えるという解決の仕方は、ものみの塔協会が初めて用いた方法ではない。
再臨派の代表的な人物として知られるウィーリアム・ミラーは、ダニエル8章の研究から預言的な「2300日」が1844年に終了するとの結論に達した。その年にキリストは再臨し、地上を清めると彼は考えたのである。しかし、ミラーの期待に反しキリストは再臨しなかった。
この外れた預言はどのように修正されたであろうか。E・G・ホワイト著「各時代の大争闘」(p. 137)には次のように記されている。
「こうして、預言の言葉の光に従った者たちは、キリストは、二千三百日が一八四四年に終了した時に、この地上に来られるのではなくて、再臨に備えて贖いの最後の働きをするために、天の聖所の至聖所に入られたのだということを知った。」
成就を天にしてしまえばもはや誰にも確かめようがない。
1914年に「異邦人の時」は終わった。ハルマゲドンは非常に近づいている。しかし、まだ全地にキリストの支配を告げ知らせるという主のご意志が残っている。それを果たさないうち最終的な終わりは来ない。ものみの塔協会はそのことを強調して人々のエネルギーを伝道に向けさせたのである。
「異邦人の時」とは「エルサレムが異教の民に踏み荒らされる、つまり異教徒に支配される期間」のことである。したがって当然のことながら、「異邦人の時」が終了すればエルサレムは回復されることになる。
「異邦人の時」の解釈でカギを握るのはエルサレムであるが、エルサレムを中東にある実際の都市と考えるにしてもあるいは天のエルサレムや神の支配の象徴と見なすとしても、「異邦人の時」がエルサレムを踏みにじることによって始まり、エルサレムの復興によって終わることに変わりはない。「異邦人の時」を見分ける基本的な特徴は、いずれの場合もまったく同じである。
ものみの塔協会は大幅な見解修正以来、エルサレムも異邦人も字義通りではなく、象徴的な意味に理解する立場を取ってきた。「異邦人の時」に関する典型的な説明は次のようなものである。
「2520年にわたる「七つの時」が終わったので、そのような御国の荒廃とその象徴的な首都の踏みつけも終わりました。どのように? ダビデ王と結ばれた御国契約にしたがい、神の国を再び設立することによります。この世の諸国家がその神の御国を踏みつけることはもはやできません。」(「御心」 p.102)
「西暦1914年の初秋に異邦諸国民がメシアの王権を踏みにじることが終わり、地上のエルサレムにではなく、今やダビデ王の主であるみ子がエホバ神の右に座している天で、メシアの王国が誕生することを意味していました。」(「とこしえの目的」 p.177)
神の王国、キリストの王国は天の王国なので、キリストが天のエルサレムで王位に就くというのは別におかしなことではない。「異邦人の時」が終了すれば当然メシアの王国は天で誕生するはずである。問題なのは「異邦人の時」を天で終了させて、それで終わりにしてしまったことである。
そもそも「異邦人の時」とは「地上」を異邦諸国民が自由に支配する期間のことであって、「天」を踏みにじる期間のことではない。地上の人間は天を支配することなどできないわけだから、これは当然のことである。天からすれば、地上における「異邦人の時」を認めるか認めないかということだけであって、文字通りの「異邦人の時」など天にはありえない。本当に「異邦人の時」が終わったのであれば、「地上」で神の王国の支配が始まるはずである。
この規準で1914年を見ると、1914年に「異邦人の時」が終了したとするのは100パーセント成立しない教義であることがわかる。というのは1914年には第一次世界大戦以外に何もなかったからである。異邦人は引き続き自由に地球を支配している。キリストが支配している現実の証拠は世界のどこにもない。
教理にあまり詳しくない人には、もしかしたらキリストの支配を霊的な支配にして(全世界で伝道がなされているとかエホバの証人の数が増えていることなどを根拠としてあげる)ごまかそうとするかもしれないが、霊的な支配であれば何も1914年を持ち出す必要はない。1914年よりはるか前、すでに西暦一世紀のペンテコステから、キリストの霊的な王国は支配を開始しているからである。世界的な伝道やクリスチャンの数が増えることであれば、一世紀でもすでに生じたことである。あらゆる意味で、1914年に「異邦人の時」は終了していないと断言することができる。
それでは、地上ではまだであっても、天においては「異邦人の時」が終わったというようなことがありうるだろうか。ものみの塔協会がどうこじつけようとも、そういうことは絶対にありえない。「異邦人の時」とは、あくまでも地上に関する期間である。天が終了したとみなしたのであれば、地上でキリストが支配を開始するはずである。キリストの支配がまだ地上で始まっていないということは、「異邦人の時」が1914年に終了したとするものみの塔協会の見解が間違っていることの絶対的な証拠にほかならない。
「1914年―キリスト臨在、終わりの日」説の最後の砦は、終わりの日のしるしが1914年以来成就しているという論議であろう。
統計の取り方の問題はあるかもしれないが、大旨ものみの塔協会の指摘は間違ってはいない。確かに、世界大戦、疫病、地震、飢饉、天変地異、不法の増大、偽キリスト、偽預言者、世界的な伝道などのしるしはこの二十世紀に顕著に現われている。
しかし、これらのしるしが現われているからといって、単純に終わりの日に入ったと結論することはできない。というのはこれらのしるしをどう位置付けるかという問題が残っているからである。ものみの塔協会のように「すでに終わりの日に入ったしるし」と考えるか、それとも「終わりの日が近づいているしるし」と解釈するかによって、しるしの意味はかなり異なってくる。
マタイ24章、マルコ13章、ルカ21章に記されているキリストの預言と調和するのはどちらの方であろうか。全体の主旨を検討してみると明らかなように正しいのは後者の方である。
キリストは繰り返し「これらのしるしが現われても終わりはまだである、終わりはすぐには来ない、それはキリストが “すでに到来した” しるしではなく “近づいている” しるしである」と語っている。
ものみの塔協会のようにしるしを見てすぐに騒ぐのは、キリストの主旨キリストの警告に反している。落ち着いてキリストの再臨を待つようにと教え諭すのが、あるべき姿であろう。
「神の組織」に関する教えはものみの塔協会にとって最大の意義を持つ。「神の組織」というこの概念は、ほとんどあらゆる教理の土台になっているからである。預言の成就の決定、規則や戒律の設定などだいたいこの教理を規準として定められている。
またこれは、統治体を始めとするものみの塔の幹部には非常に都合のよい教理でもある。格好の言い訳や口実を与えてくれるのみならず、同時にそれがエホバの証人をものみの塔協会に引き止めておく最も強力な理由となっているからである。
「神の組織に敵対する者は皆サタンです。決して惑わされてはなりません。エホバは組織を確かに導いておられます。たとえ、組織に間違いや問題があってもやがてエホバが正してくださいます。あなたは組織の中にいてその時をじっと待つべきです。組織を疑うようになりサタンのワナに陥ってはなりません」というぐあいに用いるのである。神の組織、神の組織とあまりに強調されるので、すでに強迫観念になっている人もいる。組織の否認は神の否認、組織の是認は神の是認である。
この教理こそ、ものみの塔協会の最大の武器といえるものである。
「神の組織」の定義(サタンの組織の場合は「神」を「サタン」に変えればよい)
ある組織を100パーセント神の組織、サタンの組織と断定するのであれば、その組織は100パーセント神の取り決めに従っているか、サタンの取り決めに従っているかでなければならない。
ところが現実には、はっきりそのように言い切れる組織などほとんどない。たいていの組織、人は、あるときは神であったりあるときはサタンであったり、またある部分は神であったりサタンであったりする。
ものみの塔協会の場合はサタン的なところを指摘されると、「人間は不完全だから」といってごまかしている。
神の組織かサタンの組織か、一体誰がそれを判定すべきであろうか。いうまでもなくそれは神御自身である。ものみの塔協会のように神の判定を待たずして人間が勝手に断定すべき問題ではない。
神の組織の定義を当てはめると、ものみの塔協会は困ることになる。なぜならものみの塔協会は聖書の取り決めから出てきた組織ではなく、C・T・ラッセルがカエサルの律法に基づいて作った組織だからである。神が直接ものみの塔協会を作るようにと指示したわけもなく、そういう言葉が聖書に載っているわけでもない。
事実、協会の会長や副会長、会計秘書などの役員は、神権的な方法ではなく民主的な選挙で決められている。「ものみの塔協会を作るようにという神の取り決めは聖書のどこに記されていますか」と問われたら、おそらく返答に窮するであろう。
神は常に一つの組織しか用いられなかったのでしょうか。もちろんそうですとものみの塔協会は主張する。
その主張を整理すると以下のようになる。
1.〜6.の項目は基本的には正しい。ただし、これらの根拠をもって神の組織が常に唯一であったとするのは、聖書の歴史と現実を忘れたあまりにも単純な見方である。
組織の最小単位は家族と考えることができる。そういう意味では地上に神の組織が一つしかなかったときがある。エデンの園の時代には神の設けた取り決め以外のものは何もなかった。
次に神の組織がはっきりしたのはノアの時代である。箱舟を作るようにとの神の定めに従ったのはノアの家族だけであって、他の人々はその取り決めに加わろうとはしなかった。やがて大洪水は「生き残った8人」対「滅ぼされた邪悪な人々」という形で、「神の組織」と「サタンの組織」を明確に区別するものとなった。
さらに、神が律法契約を通して組織された国民はイスラエル民族だけであったという点も指摘されよう。神がイスラエル以外の国民と契約を結んで、何らかの組織を作ったということはない。また、紀元1世紀ペンテコステの日にクリスチャン会衆が発足したとき、聖霊を注がれたのは12使徒を中心としてエルサレムに集まっていた人々だけであった。他にどこかで聖霊が注がれて、独自に別のクリスチャン会衆が組織されたというような記録は全くない。
こういう事例ばかり見せられると、ものみの塔協会の主張は正しいとエホバの証人は考えるだろうが、忘れてはならない。これらの例は聖書の歴史からいうと、ほとんど例外的なことなのである。多くの場合、神の組織とサタンの組織の明確な区別はつかない。
ものみの塔協会が主張するほど事実は決して単純ではない。これは一律に神、サタンと簡単に決められるようなテーマではない。この問題には神の組織の意味合い、取り決めのレベル、預言的な時節等の様々な要素が関わってくる。
出エジプトしたイスラエルの民はシナイ山でモーセを仲介者とし、神と律法契約を結んだ。その時以来、イスラエル国民は組織された神の民となった。それはキリストがやって来て律法契約を終了させるまで続いた。この間、神の組織は一つしかなかったのであろうか。
律法契約を結んでいる以上、それを破棄しない限りは確かに神の組織ということはできる。そういう意味では、つまり「契約上の意味合い」「法的な意味合い」においては、神の組織は一つしかなかった。しかし、神の組織にはもう一つの側面がある。すなわち「実質的」に神の取り決めに従っているかどうかという問題である。本当に神の取り決めに従っているのでなければ、法的意味と実質的な意味の双方において神の組織とは言えないのである。
法的な意味においては神の組織は一つ、しかし、実質的な意味においてはそうではないという状況は、イスラエルの歴史上普通のことであって決して珍しいことではない。むしろ、国民全体が背教してしまい、神の組織とは名目だけであって、実質的にはサタンの組織と言えるような場合が非常に多い。
典型的なのは、バビロニア帝国に滅ぼされてしまった時のイスラエルの状況である。この時イスラエルは法的には神の組織であった。形式的には、ソロモンの建てた神殿でエホバの崇拝を続けていたし、律法契約も依然として有効であった。しかし崇拝の実質においてはどうであったろうか。エレミヤ、エゼキエルなどの預言者たちの糾弾からわかるように、イスラエルはもはや神の組織とは言えないような状況にあった。行っていることは神の取り決めなどとはほど遠いサタン的な精神に満ちたものだったからである。
当時の状況についてエレミヤは次のように述べている。
「盗み、殺し、姦淫し、偽って誓い、バアルに香をたき、知ることのなかった異教の神々に従いながら、私の名によって呼ばれるこの神殿に来てわたしの前に立ち、『救われた』と言うのか。お前たちはあらゆる忌むべきことをしているのではないか。」(7:9,10)
神の組織とは表面的、神が律法契約を破棄していないというだけの法的意味、実質的にはむしろサタンの組織になっていたと言えるのである。
イスラエルの最初の王となったのはサウルである。彼は当初は神に忠実な良い王であったが、やがて神の指示やその取り決めを無視するようになり、ついにはエホバに捨てられてしまう。
その後油注がれて王になるよう任命されたのはダビデであった。しかし彼はすぐに王位に就くことができたのではない。サウルにねたまれて命を付け狙われ、逃亡を余儀なくされる。そして荒野を何年間も放浪した後ようやく即位するのである。それでもただちに全イスラエルの王になったわけではなく、初めは二部族の王にすぎなかった。サウルの家とは七年余に及ぶ戦争があった。
ここで問題になるのは、サウルがおかしくなってからダビデの王権が完全に確立されるまでの期間についてである。この間、神の組織はいったいどうなっていたのであろうか。
もちろん、サウルもダビデもイスラエル国民に属し、共に律法下の体制にいたので、そういう大きな意味では組織は一つであったと言える。しかし、実際には二人はいつまでも同一の組織の中にいたのではない。やがてダビデはサウルのもとを離れ、二人はそれぞれ独自の組織を形成するようになった。
イスラエルの体制全体を掌握していたのは、サウルの方である。ダビデのもとに集まったのはごく少数の人々であった。サムエル記上22章2節はその時の様子について「困窮している者、負債のある者、不満を持つ者も皆彼のもとに集まり、ダビデは彼らの頭領になった。四百人ほどの者がかれの周りにいた。」(新共同訳)と記している。ダビデに付いたのは反主流派の人間ばかりであった。
ではダビデのもとに形成されつつあったこの組織は、どちらの組織になるのであろうか。一般的にはアビガイルの愚かな夫、ナバルの「ダビデとは何者だ、エッサイの子とは何者だ。最近、主人のもとを逃げ出す奴隷が多くなった」(サムエル記上25:10)という受け止め方が普通であったと思われる。まさかサウルが「私はダビデをねたんで彼の命を狙いました。ダビデは仕方なく逃げ出したのです」と素直に真実を語るはずがない。当然「ダビデは逃亡者だ、主人を捨てて逃げたのだ、王位をねらうよからぬ輩だ」と宣伝したに違いない。サウルが実際どんなことを行ったのか、詳しい記録はないが、ナバルの言葉は当時の一般的な見方を反映したものであろう。
しかし、この間ダビデが神の是認を得ていたのは確かなことである。イスラエルの体制からは捨てられても神から見捨てられることはなかった。そういう意味ではダビデの組織はまさに神の組織であり、決してサタンの組織などではなかった。
ダビデの組織が実質的には神の是認を得た組織であったとすれば、サウルの組織の方はどういうことになるのであろうか。ものみの塔協会のいうように神の組織が一つしかないと仮定するなら、ダビデを認めればサウルの方は否定するしかない。もしそうだとすると、実質的にはサウルの組織はサタンの組織だったということになるが、そうすると今度は別の困った問題が生じてくる。
ダビデとヨナタンといえば、美しい友情の代名詞のようになっている。ものみの塔協会もヨナタンを高く評価し、千人に一人の人物、勇敢で、忠節で、利他的な人と述べている。(1980年2/15号)まさかこのようなヨナタンを、サタンの組織の一員ということなどとてもできないであろう。
ではヨナタンを神の組織の成員とすると、どういうことになるであろうか。現実にはヨナタンはダビデの組織の中にいたのではない。彼はサウルの子であり、その後継者としてサウルの組織を代表する人物であった。ヨナタンを神の組織の一員、彼が属する組織を神の組織とすると、サウルの組織も神の組織ということになり、現実には神の組織はダビデの組織と合わせて二つあったという結論になってしまう。
ところがサウルが不忠節になってからは、サウルの組織は神の取り決めに真っ向から反することを再三にわたって行うようになった。サムエルを脅かし、ダビデの命を付け狙い、祭司の町ノブの住民を虐殺している。こういう命令を発するほどサウルは悪霊的になっていたのである。聖書は、サウルが神の霊的裁きを受けて聖霊を取り去られると、すぐに悪霊の攻撃に悩まされるようになったと記している(サムエル記上16:14)。いうまでもなく、このような組織のトップの状態や行為は神の組織の業ではありえない。
このように考えてくると何とも妙なことになる。法的契約関係からいえば、神の組織は一つ、しかし現実には神の組織は二つに分かれて争い合っている。実質的には神の組織とサタンの組織が入り乱れているという複雑な状況になっているのである。
こうしたことは何もダビデの時代に限ったことではない。規模や関係の程度はそれぞれ異なっても、様々な時代に見られることである。アブラハムとロト、ヨセフの家とイスラエルの民、追い出されたエフタとイスラエルの家、イエス・キリストの伝道期間、小麦と毒麦の時代のキリスト教等々数多くの例を挙げることができる。
結局、神の組織は一つであるといっても、「一つ」の意味が問題になるのである。これは意味の意味を考えずに単純に論じられるようなテーマではない。「この世には神の組織とサタンの組織しかない。神の組織はただ一つ、あとは皆サタン」というものみの塔協会の教義は、現実とは遠く掛け離れたあまりにも単純で短絡的、一義的、御都合主義的な教義である。
「聖書から論じる」(p. 297)は「今日のエホバの見える組織をどのように見分けることができますか」という見出しで、神の組織を見分ける七つの条件をあげている。
- (1) それはエホバを唯一のまことの神として真に高め、そのみ名を大いなるものとしている。−マタイ4:10。ヨハネ17:3。
- (2) それはエホバの目的におけるイエス・キリストの重要な役割、すなわち、エホバの主権の立証者、命の主要な代理者、クリスチャン会衆の頭、支配するメシアなる王としての役割を十分に認めている。−啓示19:10-13;12:10。使徒5:31。エフェソス1:22,23。
- (3) それは神の霊感によるみ言葉に堅く従い、教えと行動の規準をすべて聖書に基づいて定める。−テモテ第二3:16,17。
- (4) それはこの世から離れている。−ヤコブ1:27;4:4。
- (5) それは、その成員の間に、道徳的に非常に清い状態を保つ。エホバご自身が聖なる方であられるから。−ペテロ第一1:15,16。コリント第一5:9-13。
- (6) それは、その主要な努力を、聖書がわたしたちの時代のために予告した仕事、すなわち神の王国の良いたよりを証しのために全世界で宣べ伝える仕事のために傾ける。−マタイ24:14。
- (7) 人間の不完全さがあるとしても、その成員は、神の霊の実、すなわち、愛、喜び、平和、辛抱強さ、親切、善良、信仰、温和、自制を培い、かつ実際に示し、それによって一般の世とは異なるようになる。−ガラテア5:22,23。ヨハネ13:35。
この条件をものみの塔協会に当てはめるとどうなるであろうか。
こうして見てみると、ものみの塔協会は誇大宣伝ならいざ知らず、厳密にはとうてい神の組織とは言い難い状況にあることがわかる。組織としてはだいたい神とサタンが半々くらい、幹部ほど偽善的でサタンに近くなる―これが現実的な評価であろうか。
ものみの塔協会の最後の切り札、都合が悪くなった場合の最後の逃げ道は「やがてエホバが正して下さる、それを待てない人は不信仰だ」である。
どのように、いつ…それは誰にもわからない。すべてはエホバによることなのだから。神が定めの時に御意志にかなった方法で行って下さるはずであるということになる。具体的な保証は何もない。皆が忘れてくれればそのままうやむやにしてしまう。どうしても扱わなければならないものは、まず一生懸命理屈を考える。これで成員を納得させられる、あるいはごまかせるという有力なものが見付かると、ただちに「やはりエホバの組織です」という顔で堂々と行う。ちょっと弱いな、根拠薄弱だなというものは、記憶が薄れた頃にさらりと変更してしまう。
現実にはものみの塔協会の対応のパターンはこの程度なのだが、エホバの証人はエホバの名を出されるとどうにも弱い。組織の中にいると幹部のへ理屈に簡単に瞞されてしまう。
よく考えてみるとコラとダビデの場合は全く違うのである。この相違はモーセとサウルの違いに基づいている。二人とも神の組織、イスラエルの指導者であるという立場は同じであった。ところが決定的に異なっていたのは、サウルは霊的な裁きを受けてすでに神から否とされていたのに対し、モーセは神の義認を得ていたという点である。このゆえに、サウルに対するダビデの離反、反逆は必ずしも神に対する反逆にはならなかったが、モーセに対するコラの反逆は神に対する反逆を意味するものとなったのである。
モーセの場合は、何らかの過ちや間違いを犯しても、神の義認を得ていたので全体としては神が導いていることになった。その過ちや間違いは神の義認を失うほどのものではなかった。したがって、イスラエルの民は問題があっても神が正して下さることを期待して待っていればよかったのである。
しかし、サウルの場合は事情が大いに異なっていた。彼は神の義認を失っていたので、その過ちや間違いは致命傷になっていった。やがてエホバが正して下さるのではないかと待ち続けていたらどうなったであろうか。おそらくサウルの家と共に滅んでしまったに違いない。
組織と個人、何が神に対する忠節か、いずれの道が神への忠節になるのか、カギとなるのは神の義認である。エホバの霊的な裁き、聖霊の判決がどうなっているかがターニングポイントになる。
その組織が本当に神の義認を得ているなら、その中に留まって神が行動されるのを待てばよい。しかし、そうでなければすべての努力はやがて徒労に終わる。神がいやし不能とみなしたものは、誰もいやせないからである。
このままでゆけば間違いなくものみの塔協会はサウルになるであろう。彼らは一貫して真実に敵対しているからである。統治体を筆頭とする幹部に対する神の義認が取り去られたことは、今回の事件によって法的にも実質的にも立証された。エホバの天の法廷が実際に機能しているのであれば、神の霊的な判決の影響は間もなく明らかになるはずである。
ものみの塔協会は、キリストの千年王国で共同支配者になるのが14万4千人、そのほかのクリスチャンは地上の臣民になると教えている。
この説の根拠とされているのは以下の聖句(すべて新世界訳)である。
「それでわたしは、ちょうどわたしの父がわたしと契約を結ばれたように、あなた方と王国のための契約を結び、あなた方がわたしの王国でわたしの食卓について食べたり飲んだりし、また座についてイスラエルの十二部族を裁くようにします。」(ルカ22:29,30) 「恐れることはありません、小さな群れよ。あなた方の父は、あなた方に王国を与えることをよしとされたからです。」(ルカ12:32)
「あなたはほふられ、自分の血をもって、あらゆる部族と国語と民と国民の中から神のために人々を買い取ったからです。そして、彼らをわたしたちの神に対して王国また祭司とし、彼らは地に対し王として支配するのです。」(黙示録5:9,10)
「またわたしが見ると、見よ、子羊がシオンの山に立っており、彼と共に、十四万四千人の者が、彼の名と彼の父の名をその額に書かれて[立っていた]。
これらは、神と子羊に対する初穂として人類の中から買い取られたのである。」(黙示録14:1,4)
キリストの追随者の中には王国の支配者となって裁きを行う人々がいる。彼らが天に行く目的は王また祭司として地球を支配することである。彼らは「小さな群れ」と呼ばれているので、限られた少数の人々であることがわかる。シオンはかつてダビデの行政府が置かれていたところである。天のシオンにキリストと共にいるのは14万4千人と述べられている。したがって、天に行く人の数は14万4千人と考えることができるのである。
もし「ものみの塔協会」のこの教理が正しいとすると、キリストが伝道を開始した西暦1世紀から現在までの間に天に行くことを許された人の数は、わずか14万4千人しかいないということになる。言い換えれば、1900年以上もの間に神の是認を受けた真のクリスチャンは、たったの14万4千人しかいなかったということになってしまうのである。
果たして本当にそうであろうか。キリストが「招かれる人は多いが、選ばれる人は少ない」(マタイ22:14)と語ったのは事実である。しかし、例えそうであったとしても、ものみの塔協会の教理は神の神性とも歴史の事実とも全く調和しない。天に行くことを表明した人々はあまりにも多い。その数は14万4千人より圧倒的に多いのである。14万4千人以外はみな天から締め出されてしまうというのは、どう考えても愛と憐れみに富まれる神の属性とは一致しない。
1世紀当時から現代に至るまでのクリスチャン総人口を厳密に知ることはできないが、聖書の記述と一般の歴史的文献にある程度の目安を見ることができる。以下はその資料である。
| 使徒 1:15 | キリスト昇天の日に120人の弟子たちが集まっていた |
| 使徒 2:41 | 五旬節の日に3000人がバプテスマを受けた |
| 使徒 4:4 | 男の数だけで5000人が信じた |
| 使徒 6:7 | エルサレムで信者が非常に増える |
| 使徒 9:31 | ユダヤ、ガリラヤ、サマリヤの全地で増える |
| 使徒 9:35 | ルダとシャロンに住む人はみな主に立ち返った |
| 使徒 9:42 | ヨッパで多くの人々が主を信じた |
| 使徒 10:44 | コルネリオと共にいたすべての人に聖霊が下った |
| 使徒 11:19,21 | フェニキヤ、キプロス、アンテオケの大勢の人が主に立ち返った |
| 使徒 11:24 | アンテオケの大勢の人が主へと導かれた |
| 使徒 13:48 | ピシデアのアンテオキアの異邦人も信仰に入った |
| 使徒 14:1 | イコニオムでユダヤ人、ギリシャ人の大勢の人が信仰に入った |
| 使徒 14:21 | デルベでかなり多くの人を弟子とした |
| 使徒 16:33 | テアテラで看守とその家の者全部がバプテスマを受けた |
| 使徒 21:20 | ユダヤ人の中で信仰に入っている者は幾万となくいる |
| コロサイ 1:6 | 福音は世界中で実を結んでいる |
キリスト教がローマ社会に広まっていった結果、ユダヤ人よりも異邦人の信者の方が問題にならないくらい多くなった。ユダヤ人だけで幾万人もの信者がいたわけだから、全部のクリスチャンの数は少なく見積もっても1世紀だけで10万人をはるかに越える人数になる。AD70年のエルサレム滅亡前の段階で、すでに14万4千人を越える状況であったと考えられるのである。
キリスト教は大いに拡大していった。1世紀末にはすでに次のような状況になっていた。
第1世紀末ローマに反キリスト教的指令の発布されたとき、クレメンスの手紙によれば、宮廷に属する者からも迫害に遭った人があり、政府軍人の階級もその対象とされたらしい。ドミティアヌス帝の姻戚さえ「無神論者」の疑いを帰せられて迫害・追放を受けた者があった。トラヤヌスやマルクス・アウレリウスのごとき平和的治世の下においてさえ、イグナティオスやポリュカルポスやユスティノス等の殉教記録が残っているのは、キリスト教普及の反証と見られる。小プリニウスがビティニア州総督に赴任したとき、その地方民の大多数が「無秩序な迷信」に惑わされているのに驚き、いかに処置すべきかという方針について、トラヤヌス帝に報告しかつ指示を仰いだ往復文書が残されている。キリスト教分布の程度は地方により同じくないが、ローマの統治官をかように当惑させた地方もあったのである。(「キリスト教の源流」石原謙著 p.80)
1世紀の末には下層階級の人々ばかりではなく、ローマの宮廷の中にもキリスト教が浸透していた。地方によっては住民の大多数がクリスチャンというところもあったのである。
「世界の歴史5 ローマ帝国とキリスト教」より
「キリスト教徒は実に数が多くて、都市ばかりでなく農村にも、さらに草深い田舎にも広がってい(た)」(p.345)
「二世紀の末、『護教論』を書いたテルトゥリアヌスのころ、迫害の強化にもかかわらず、信徒の増大と組織の強化は着々とすすめられていた。その勢いを抑えるために201年に出された法律は、ユダヤ教とキリスト教への改宗を極刑をもって禁ずるものだった」(p.380)
「キリスト教史1」半田元夫・今野國雄著より
三百年代になると、エウゼビオスが「キリストの祭壇は今やすべての村々や町々にみられる」という状況になっている。…
小アジアでもフリュギアのはるか北の地方で発見されたおびただしい碑文は、帝室領の田舎の人々が公然とキリスト教の信仰を表明していたことを示しており、墓碑銘に好んで描かれている鋤、鎌は、彼らの出自が農民であることを語っている。( p.167)
この時代になると、もはやクリスチャンの数は数十万人どころではない。ローマ帝国の隅々までキリスト教は普及していたのである。
次の図はその状況を示したものである。
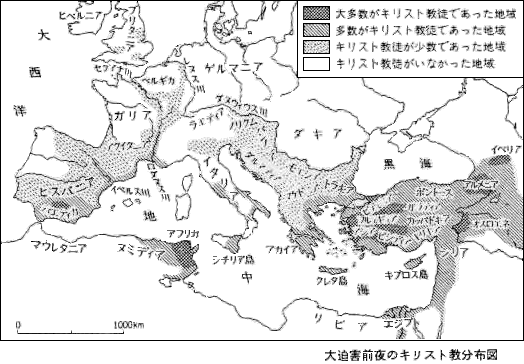
マタイ13章に記されている「小麦と毒麦(雑草)のたとえ話」にあるように、あらゆる時代に真のクリスチャンはいたはずである。もちろん正確な人数はわからないとしても、約1400年余に及ぶ期間であることを考えると、その数は決して少なくないはずである。
エホバの証人は一年に一回主の記念式を開く。その時パンを食べ、ぶどう酒を飲む人が天へ行く人々で、何も食べない人が地上での永遠の命をめざす人々である。
| 象徴物にあずかった人数 | ||
|---|---|---|
| 1899年3月26日 | 2,501人 | (不完全な報告) |
| 1917年4月 5日 | 21,274人 | |
| 1919年4月13日 | 17,961人 | (不完全な報告) |
| 1925年4月 8日 | 90,434人 | (これは出席者数であるがこの当時は地的な希望を持つ人は記念式に招待されなかった) |
| 1939年世界の伝道者数 | 71,509人 | (他の羊が集められはじめたばかりなので大多数は天的クラス) |
ものみの塔協会は
「そうした集める業が過去18世紀余なされた後の、この二十世紀の時代までには、代わりとして用いられねばならない人々は比較的少数、あるいはごく少数しかいないはずです」(ものみの塔誌1975年2月15日号 p.120)
と指摘している。
少数といいながら、ピーク時には何と「9万人」を記録しているのである。
この矛盾に対する答えとして、ものみの塔協会は「天へ行く人には非常に高い規準が求められる、不滅の命を与えられるため絶対に不忠節にならないことが要求される、ゆえに選ばれる人は14万4千人しかいないのである」と教えてきた。
しかし、この点も今や完全に否定された。レベルの高い人々の代表であるはずの統治体が、偽善者の集団であったからである。聖書の原則を擁護しない人々をキリストが共同統治者に選ぶことなど絶対にありえない。
彼らが組織崇拝というバアル崇拝を止め、偽善と偽りを正して、組織を神の名にふさわしい状態にするよう努力しない限り、天に召されるという彼らの希望は空しいものに終わるであろう。
「統治体、Governing Body」…この語の意味は辞書を調べてみればはっきりする。英語の語源は別としても、ものみの塔協会の宣伝するような「導く、水先案内をする」といった意味はない。現代の意味は「支配する、治める、統治する」である。まさに組織支配に腐心する「統治体」の実態にふさわしい名称なのである。
「統治体」とは「クリスチャンを導く一団の人々」などではない。その真実の姿は、キリストの権威に違反した「クリスチャンを支配する一団の人々」なのである。
さらに、この「統治体」という称号はキリスト教の精神に真っ向から反している。キリストの精神、その教えは「統治体」という称号とは全く逆である。
「また、『指導者』と呼ばれてもなりません。あなた方の指導者はキリスト一人だからです。」(マタイ23:10新世界訳)
この聖句は次のように言い換えることができる。
「あなた方は『統治体』と呼ばれてはなりません。あなた方の統治者はキリスト一人だからです。」
一世紀当時エルサレムには、諸会衆を管轄する「統治体」という指導機関があったとものみの塔協会は主張しているが、実際はそうではなかった。以下にその理由を列挙する。
11 わたしの兄弟たち、実はあなたがたの間に争いがあると、クロエの家の人たちから知らされました。
12 あなたがたはめいめい、「わたしはパウロにつく」「わたしはアポロに」「わたしはケファに」「わたしはキリストに」などと言い合っているとのことです。
ものみの塔協会の主張するように本当に神の組織「統治体」が全世界のクリスチャンを指導していたのであれば、誰か一人くらいは「私は組織に従います。わたしは統治体に従います」と言ってもよさそうなものであるが、パウロの記述から明らかなようにそのような人は一人もいなかった。
パウロとケファ(ペテロ)があげられているではないかというかもしれないが(ものみの塔協会はパウロとペテロが「統治体」の一員であったと教えている)、それは「統治体」存在の証拠にはならない。この記述は、彼らが「統治体」という組織としてではなく、パウロ、ペテロという個人としてみられていたことの証拠になる。
「彼らは初め必ずしもユダヤ教に反対せず、むしろその戒めと道徳的規範とに従ったが、イエスの信仰を中心として共同生活を行い、一致して義と愛とを実践し、互いに助けささえて独自の団体をなした。これが原始教会(初代教会ということもある)と呼ばれる集団で、イェルサレムから始まり、しだいに広まり、独立した教会をなしたものもあったが、ことにシリアの首都アンティオキアではユダヤ人以外のいわゆる異邦人をも交えた団体が形作られ、ここにユダヤ的律法に制約されない、すなわち純粋に信仰のみによって結ばれた新しい教会形態が始まった。」(下線は発行者) (「世界大百科事典−キリスト教会の発展史」平凡社 p.56)
「この集団の指導者層には使徒団が、とくにパウロが『柱』と呼んだ(ガラテア2:9)ペテロ、ヨハネ、それに主の兄弟ヤコブ、この三人から成る三頭政治が目立っていた。使徒行伝もこの三人には、とりわけ重要な位置を与えている。
…十二弟子は何よりもまず、エルサレムの教会、およびはやくからパレスチナに設立されたその枝教会の、霊的な指導者であって、はじめは定住していた(ガラテア1:22 。使徒行伝9:31)。彼らの権威、また彼らを通しての母教会の権威は、改宗したユダヤ人のみならず、後にパウロ書簡が証しているように、異邦のキリスト教徒にまで及んだのであった。十二弟子と教団とのスポークスマン格はある時はペテロ、ある時はヤコブであった。ヨハネはこの二人のどちらにも従属した位置にあったようである。
…エルサレム教会は、使徒の段階でも、王朝の段階でも、堅固な構造を保っていた、ヘレニストの伝道に続く、ペテロ、ヨハネのユダヤ、サマリヤ地方巡回視察(使徒行伝8:9)、ペテロのアンテオケその他の地への伝道旅行、パウロが伝道していく先々で組織的に整然となされたユダヤ教化の反宣伝等々は、はじめ異邦人伝道にかなり消極的でありながら、形成期のキリスト教界全体を自分の権威化において、思うままに形づくろうとするエルサレム教会の意志を、はっきり示したものであった。
それにくらべてパウロ教団の組織は、はるかにゆるやかなものであったようである。十二弟子は霊的な職分のうち、枢要なものは自分たちの手に集中させていたらしいのに対し、パウロ教団では、専門的に分化させていったことが分かる。」(「原始キリスト教」マルセル・シモン著 p. 44,45. 103)
ものみの塔協会が「統治体」の聖書的根拠としてあげる最大のものは、使徒15章に記されているエルサレム会議である。割礼の是非をめぐる論争によって開かれたこの会議が、ものみの塔協会によれば「統治体」の会議であったということになる。
しかしこの会議については全く逆の見方が成り立つ。つまり「統治体」に相当するような組織がなかったからこそ開かれた会議であると。むしろこの方が自然な見方であろう。
まず、会議が開かれるに至った動機であるが、直接のきっかけとなったのは、エルサレムの教会と何らかの形で関係のある人々が、パウロたちの活動しているアンテオケ教会に来て、異邦人でキリスト教信仰に入る者に割礼を施すことを要求したため、混乱が生じたという事情であった。この人たちは、キリスト教はユダヤ教の枠内にあるとの理解に立っていたことになるが、これはその当時にあっては特に異とすべき考え方ではなかった。
しかし、アンテオケ教会 ― その指導者たちはやはりユダヤ人であったが ― の見解は、これとは異なる。それは、異邦人は異邦人であるままキリスト教信仰に入ることができるとし、またそれに従って実際に事を運んできていた。…アンテオケ教会、特にその指導者たちにとっては、ユダヤ主義者たちの言いなりになることは、先に述べたような彼らの信仰理解、またそれに基づく今までの実績から考えて、もちろん論外であった。しかし他方、このユダヤ主義者たちの影響を自分たちで排除することも、彼らにはできなかったようである。アンテオケ教会は、それとは別の道を選んでいる。すなわち、教会はその最高指導者であるバルナバとパウロとをエルサレムに派遣し、ユダヤ主義者たちが自分たちの背後にあるとしているエルサレム教会の指導者たちに会って、じぶんたちの福音理解と宣教活動の実際とを伝え、彼らの理解を求めさせたのであった。」(「使徒パウロ−エルサレム会議」佐竹明著 p.122,123)
この本の指摘通り、エルサレム会衆とアンテオケ会衆は、ある程度異なった路線、独自の路線を歩んでいたと考えられるのである。
エルサレム教会では割礼を初めとするモーセの律法を守ることが普通に行われていたが、アンテオケ教会ではそうではなかった。この相違は割礼の論争が起きてから生じたものではない。むしろ、相違があったからこそ論争が生じたと見るべきである。
そうであれば、この会議は「統治体」存在の証拠ではなく、逆に「統治体」などはなかったという強力な証拠になる。というのは、もしエルサレムを中心とする組織上の絶対権を持つ「統治体」が存在していたのであれば、そもそもこういう論争など生じなかったはずだからである。エルサレムからの指示に異議、異論を唱える者はすべて、ものみの塔協会で行われているように、背教者として処分されていたはずである。